サクラメントからの手紙で「そちらに向かう」と便りがあったのはもう二週間以上前になる。何の前触れもなく、あまりに突然のもので些か驚いた。最後にやり取りがあったのは結婚の報告があった時で、かれこれ一年以上はお互いにだんまりが続いていた。
その頃彼はワシントンにいて、陸軍の任務と演習とで奔走していた。時代はまさにシヴィル・ウォーの前夜で、社会全体に暗雲が立ち込め、日々悪い報せが世間を駆け巡る中に国民は不安に寝付けぬ夜を過ごしていた。
長く仕事を空けることは認められない時勢であったが、それでも一日だけ休みを許されてニューヨークの港に彼らを迎えに行った。
パナマ地峡とを連絡する黒い外輪船はハドソン川の河口に集う数多の移民船や貨物船の中では決して目立つようなものではない。だがその存在の大きさは他を圧倒するものである。埠頭にはその日も西部を目指す若者や外国人の家族などがひしめき合っていて、よくも海に落ちる者がいないものだと感心すらした。
入港した船から梯が下ろされると、それを渡って乗客が降りてくる。その手には長い船旅に手放せない必需品を込めた鞄を抱えて。埠頭で待つ家族や仲間の姿を探しては次々に再会を喜ぶ姿が見られる。自分の目当ての人物はなかなか現れないので、一つしかない梯を見逃そうはずもないのに通り過ぎてしまったかと心配になった。けれども乗客がおそらく半数を過ぎよう頃に彼は姿を現した。
「ワトキンス!」
彼の名前を大声で呼んで周りを憚らずに大手を振る男は、彼の兄貴に違いなかった。
「久しぶりだ、お前もすっかり軍服が似合うようになったな。」
そう言う兄貴は以前より太って見えて、髭も濃くなっていた。若い頃の親父に似てきた。
兄貴の隣に女性が立っていた。ワトキンスが視線を向けると、彼女は柔らかく微笑んだ。後ろで緩くまとめたブロンドの、青い瞳が印象的だった。この人が話に聞いた兄貴の結婚相手で、ワトキンスの義姉にあたる人らしかった。
「初めまして。結婚式には出席できず申し訳ない。」
「お会いしたかったわ、ワトキンス。この人にそっくりですのね。」
兄貴は「そんなことないだろ」と不平を漏らした。ワトキンスは右手を差し出してから、彼女が両腕で抱えるものに目を止めた。包み込むように抱きかかえられたそれは植物の蔓で編んだかごで――ゆりかごだった。まさかと思って彼は目を丸くして兄貴を見た。すると彼はニヤリと笑って手のひらで指し示す。
「紹介するよ、僕たちの『家族』だ。」
ワトキンスはかごを覗き込んだ。いっぱいに敷き詰められた白い布団の中央に、玉のような赤子が一人寝転がっていた。彼は長い船旅を終えて漸くお目覚めになって、青い瞳をぱっちりと見開いた、ワトキンスはそれと目が合った。
「ロバートだ、お前の甥っ子だよ。」
――それが吾輩とロビンとの最初の出会いだった。
頼まれて用意してあった宿に向かう車の道すがらで彼らは種明かしをした。
「急な事でごめんなさいね、でもこの人が内緒にして驚かせようって言うから。」
義姉さんは笑いながら隣に座る兄貴の肩を叩いた。
「親父やお袋より先にお前に会わせようって決めてたんだ。そしたら予想以上の反応で嬉しい限りだ。」
二人は顔を見合わせて笑った。兄貴と結ばれるなんて義姉さんは物好きな人だろうと思っていたが、やはり彼と気が合いそうな性格なのだと分かった。息子は母親の腕に抱かれてガタガタ揺れる車内でぽかんとしていた。
「ここまで来るのは大変だったろう。」
「まあな、妻の肥立ちがよくなったからこっちに渡ることにしたんだ。」
聞けばロビンは生まれて一年も経っていなかった。それくらいの幼子を連れて旅をするというのは大変なことだが、それでも新しい家族を一刻も早く見せたいと思ったのだろう。急にこちらへ来ると便りを寄越したのも頷ける。
「何だってそんなに早く来ることもなかったのに。せめて世の中がもう少し落ち着いてからでも……」
「こういう時だからこそ、行動は早い方がいい。それに、息子に広い合衆国を見せてやらないとな。」
「そういうのはもう少し大きくなってから言うことじゃないか。」
「この人、気が早いから。」
兄貴はにこにこしていたが、すぐに表情を戻した。
「……お前の方こそどうなんだ?サクラメントは大したことないが、こっちは……かなりきな臭くなっているそうじゃないか。」
ワトキンスは腕組みをして後ろにもたれかかった。
「大方は新聞に報じられる通りだ。労働者の座り込みが激しくなっている。ニューヨークでも時々そういったことが起こる。」
「大変なのね。」
「合衆国軍はどうしているんだ?」
「仕事だから詳しいことは言えないが、必要があれば作戦行動に出ることもあるだろう。何にせよ、我々はリンカーン大統領を信じている。」
「合衆国がよもや国内に敵を抱えるなんてな。」
「ウエストポイントにいた頃の俺なら信じなかったがな。」
二人して重苦しい雰囲気になったのを変えようと義姉さんは声を上げた。
「うちの人から聞いたわ、立派な軍人さんなんですってね。」
「それほどのものでもないが。」
「そんなことないって、みんなを守って戦うんでしょう。自慢の弟だって、人に言い聞かせているのよ。」
「兄貴が?」
ワトキンスは彼の顔を見た。
「『寝小便小僧』にしては、な。」
「あれは兄貴がやったんだろ。」
「お前、寝ぼけてて覚えてないんだよ。」
「罪を擦り付けたくせに。」
「やめなさい!」
青い目を鋭くして叱りつける義姉さんはどこかお袋に似ているような気がした。
宿の部屋に着くと夫婦はやっと長旅から解放された風で安堵していた。ワトキンスがいる手前平然と振る舞っているが、実際は今すぐにベッドに体を放りたいくらいであった。
ベッドの縁に腰掛けて、義姉さんはロビンをあやした。それで彼は再びはっきりと甥の顔を眺めた。頭の毛は薄くて、白い手足は丸く、頬はリンゴのように紅潮している。宝石のような瞳が母親と見つめ合って、表情が微笑みに変わる。義姉さんは彼にワトキンスの方を向かせて、「ロビン、あなたの叔父さんだよ」と声をかけた。
「この子には、叔父さんのような強い人になってほしいわ。」
思いがけず、彼女がそのようなことを言うのでワトキンスは何も答えられなかった。
「これからこの国はどんどん発展する、その流れの中で、この子にも自分の道を進んでほしい。」
その赤子には言葉の意味が分かってはいないだろう、それでも、母親の願いはその手を通じて伝わっているはずだ。
不意に兄貴が彼に問いかけた。
「お前は結婚しないのか?」
結婚、その言葉には思わず躊躇うものがあった。
「いくつか見合いの話は上がったが、縁が無かった。」
「そうか」と兄貴は答える。縁が無かったというのは婉曲的で、実際は全て断っていた。家庭を持つことへの希望が無かったし、家を外し、やがては路傍に伏す軍人にそれは必要ないと思っていた。
「いいものよ、家族は。」
義姉さんは顔を上げた。
「お前は粗野で女心も分からないから敬遠されたんじゃないか?」
「なんて言い方するの!」
義姉さんは彼の肩を持ったが、兄貴の言い分も一理あったかもしれない。
「いずれにせよ、いつかは……」
その言葉が口を突いて出た。まんざらでもなかった。兄夫婦の姿を見ていたら、どこか憧れのような、尊敬のような、そんな感情が湧いてきたのだから。「それがいいわ」と義姉さんも笑った。
やがてロビンはぐずりだした。義姉さんはしばらくあやしていたが、きっとお腹が空いたのだろうと言って乳を飲ませた。抱きかかえられて乳房を顔の前に差し出されると、先ほどまで泣いていたのもどこへやら、ぱっと静かになって夢中で吸い付いた。
幸せがそこにあった。カリフォルニアの開拓者たちが掘り出した宝よりも美しい、黄金の風景は確かにそこにあったと思う。
ワトキンスは彼女が乳を与えているのを見ているのがどうにも気恥ずかしくなって、兄貴に向かって言った。
「明日には仕事に戻るから、用事があれば今のうちに頼む。」
「そうか、お前は忙しいんだな。親父とお袋には僕から伝えておく。」
そんなことを言いながら柄にもなく残念そうな顔をするのでワトキンスは狼狽えた。
「わざわざ出迎えてくれてありがとうな。いろいろ大変な時期だろうが、お前ならうまくやれるだろう。」
「兄貴こそ、家族を大切にな。」
黙って頷いて、「僕は僕の家族を愛してる。」と言った。それから妻の隣に座って、満腹になってご満悦の息子に指を触れた。
「なあ、ワトキンス……」
「ん。」
「もし僕たちに何かあった時は――ロビンのこと、頼めるか。」
ワトキンスは固まった。
勿論答えは決まっている、その赤子は自分にとって甥であるから。分からないのは、なぜ兄貴がそんなことを言い出すのかだった。合衆国に忠誠を誓って戦いに身を投じ、明日をも知れぬ軍人と、文民で血気盛んな一家の長、どちらが先に死のうなど、誰の目にも明らかではないか。
きっと彼は可能性の話をしているのだ。家族ができれば、万が一に自分がただならなくなった時のことを考えてしまうのだろう。その時はそうやって自分で自分に納得をつけた。
――その「もしも」が、本当に起きるなんて。
兄夫婦が亡くなったと一報を受けた時、ワトキンスは完全に信じてはいなかった。だがそれは虚報ではなかった、それも、まだ言葉もろくに喋れないような幼い息子を遺して。
彼らは忘れ形見を残してこの世を去るにはあまりに若すぎた。ロバートが気の毒で仕方がなかった。合衆国にいる親戚は叔父のワトキンスと年老いた祖父母のみであり、叔父が後見人に選ばれるのは必然であったし、実際彼はそのように申し出た。その頃はシヴィル・ウォーの最中であって彼は戦争遂行という大役を抜けることができなかったが、終わりの見えない争いに漸く終結の兆しが見えてきた折で、ワトキンスもまた発展目覚ましい西海岸の管区に移される話がにわかに持ち上がっていた。そこで一足早くサクラメントに邸宅を構え、使用人を雇って幼いロバートを住まわせたのである。サクラメントは彼の故郷であり、亡き両親との思い出が残る地で暮らすのが彼にとってもよいと考えた。
ワトキンスが甥に再会すること叶ったのは戦火が殆ど消えつつある終戦の前の年、冬のことである。カリフォルニアに渡った彼はロバートと再び相まみえた。彼は四歳であった。両親を喪った日のことなど覚えていようもなかったが、それでも自分がもう二度と彼らに会えないことを肌で分かっていて、自分は目の前の男に匿われて今でも生きていられるのだと幼心に理解していた。
全くの初対面に等しい甥にどう声をかけてよいものか困った。これで自分が義姉さんのように人当たりの良さそうな女性だったら不都合も無かろうが、軍服のいかつい男が入ってきたのでは彼もすっかり小さくなってしまった。仕方がないので二、三言葉を交わした後は世話を使用人に任せてそそくさと退散した。
翌年、シヴィル・ウォーの終結と共に彼の異動が正式に決まって、ワトキンスとロバートの奇妙な共同生活が始まった。
ロバートは大人しい少年だった。自分から話しかけてくることは殆どなくて、いつもおどおどしたように構えている。無理もない、逆の立場であればワトキンスもそうしただろう。彼は叔父に対してのみならず、使用人や教育係に対してもどこか顔色を窺うようなところがあった。彼は聡い子だ、目の前の男の機嫌を損ねてこの家を追い出されたのでは、今度こそ自分に生きる場所はなくなると直感していたから、そうならないように必死に振る舞っていたのかもしれない。いずれにせよ、気の毒なことであるがワトキンスの側からはしてやれることがなかった。
初等学校に通えば級友に囲まれ性格も変わるかと思ったが、必ずしもそのようなことはなかった。教師からは勉強はできるが常に物静かな子だと聞いた。同級生と上手く打ち解けられていないのにも理由の一端は想像がついた。シヴィル・ウォー戦中からワトキンスは戦功を度々大々的に報じられ、「名将」として称えられた、これはリンカーン大統領の報道戦略でもあった。戦後にはその印象はすっかり定着し、それどころか虚実入り混じって逸話が言い伝えられるようになって、名声は不動のものになっていた。それは子供でも知っていることだった。「グレイヒル将軍の甥」と知られて彼は学級内で浮いた扱いをされていたのだろう。結局はこれも自分が原因だった。
兄貴と義姉さんの言葉が思い出された。せめて、彼に叔母が――愛を注いでくれる者がいれば明朗な性格に育ったかもしれない。自分が男やもめに意地を張っていなければ……。今更結婚しようが、その相手が血の繋がらぬ甥に無償の愛を与えてくれる保証はない。
ロバートはそんな様子だったから、川でエマソン家のご令嬢を助けたと聞いた時は耳を疑った。エマソンといえばサクラメントで知らぬ者はいない術士の資産家である。この縁で当主であるエマソン卿とも知り合うことができた。ロバートも幼いながらに勇敢な心を持っているものだと感心した。そして何より驚いたのは、卿の邸宅に招かれた時の彼の振る舞いである。彼は卿の書斎に強烈な興味を惹かれた、ただでさえ人前で積極的に行動しない彼なのに、である。その様子が卿にいたく気に入られて、彼がニュージャージーの名門に進学する費用を援助すると提案された。それならばワトキンスの給金でも問題なかったのだが、結局は厚意を受け取ることにした。
このことに関して、ワトキンスは深く安堵した。甥が何かに興味を持ち、志高くその道に進むと決意したことで、漸く彼の人生が拓けた気がした。あのままグレイヒル邸で人形のように成長してしまっては、彼の両親に合わせる顔がない。ロバートは大陸横断鉄道で東海岸へ渡った。それからは月に一度ほどワトキンスと、それから卿とも文通を行っていたようである。今日は何を教わったとか、講師の誰に会ったとか、学問の用語はさっぱり分からなかったがとにかく日々が充実しているであろうことは分かった。
ロバートが中等学校の最終学年に上がって、彼から一つの提案が届いた。ニューヨークのウエストポイント陸軍士官学校に進学したいというものだった。そこはかのトーマス・ジェファーソンによって創立された士官学校の名門で、ワトキンスもかつて軍人を志して士官になるための教育を受けた学校である。彼が綴った通り、そこでなら学問の勉強と軍人になることとを両立できる。
一軍人として、甥の決意は喜ばしかった。頭の良い彼ならきっと知将になれる、そう確信した。実際に士官学校の合格通知を受け取った時は自分のことのように喜んだ。
それが大きな間違いだった。
最初は手紙の頻度が少なくなったことからだ。中等学校の頃は遅くとも二か月に一通は届いていた筆まめなロバートが、半年かそこいらに一通しか便りを寄越さなくなった。その程度ならば生活が変わって忙しいのだと納得した。ところがクリスマスにもサクラメントに帰ってこなくなると、これは不審であった。いくら実家の居心地が悪いとはいえ、休暇の帰省を欠かすような彼ではなかった。
「退学した」と連絡がきたのは、入学から一年と半年経たない冬のことである。
久しぶりに会ったロバートは憔悴しきっていた。ワトキンスとは決して目を合わせようとせず、俯きがちで、青黒く染まった頬を見えにくいように少し首を傾けたままの姿勢で言葉少なだった。ワトキンスははっとした。
元々、陸軍士官学校に「しごき」の風習が根強いのは否めない。それは彼の時代にもあって、へまをした者に理不尽な罰が課されることがあった。しかし「グレイヒル」に対するそれは度を超していた。「名将」の甥で、彼を後見人に持つ「二世」であるロバートは教官も上級生も特別に目を向けていた。彼らは念入りにしごきを加え、それはワトキンスが受けたものには到底比べようもなかっただろう。彼はそれに耐えるしかなかった。
自分のせいで謂れのない執拗な暴力を振るわれたことに、憎悪をぶつけてくれればむしろ気が晴れた。だが彼は叔父を恨んでなどいなかった。優しい彼は自分が志半ばで折れたことで「名将」の顔に泥を塗ったことをひたすらに悔いていた。身体中に刻まれた生傷の上に、一生癒えない心の傷まで負わせてしまった、それはすべて自分のせいだ。ワトキンスは漸く理解した、この子は吾輩の息子ではない、兄貴と義姉さんの子だ。
思えば彼が陸軍士官学校への進学を希望したのも、育てられた叔父へ孝行せねばならぬと義理を感じていたからだろう。「吾輩の後を追う必要はない」と、どうして一度でも伝えることができなかったのだろうか。
失意のままに邸を後にするロバートを止めることはできなかった。彼はその後サクラメントに電信技士の仕事を得て細々と働き始めた。士官学校になど行っていなければ、有名な大学で偉大な師の下についていたであろう男がである。同じ街に住んでいながら疎遠になり、精々何かあれば便りを送るくらいが二人の関係になった。
これまで二度、三度ならず自分のせいで甥を苦しめてきたが、その上にまたしても過ちを犯すとは本当に情けない話だった。
ワトキンスがウエスティングハウス氏と知り合ったのは西海岸での彼の事業を通じてのことである。全米で開発が進む電気事業については合衆国軍も戦略的に注目しており、彼とは価値観を共有していた。実業家であり技士としても名高い氏であるから、ともすればロバートを見留めてくださるかもしれない――そう思い立つべきではなかった。
ワトキンスからの紹介となれば、彼に断るという選択肢はなかったのだろう。断れば名声を傷つけることになると、彼はまた気遣ったのだ。最初にこなせる仕事かどうかを懇ろに尋ねておくべきだった。止める機会は他にもあったはずだ、「研究のためにアリゾナに行く」と聞いた時に、無理を言ってでも仕事を中断させるべきだった。最後の最後まで甥を助けることができずに、かろうじて非難を逃れる手段だけを与えた。
共にいるだけで彼を傷つけてしまうのなら、自分は彼から離れよう。もう二度と「名将の甥」の肩書を背負うことも、世間に顔を出すこともしなくて良いから、この広い国のどこかで平穏に暮らしてほしい――。
――そう思っていたのに。
その日、全国の新聞を同じ言葉が飾った。「僕は決して諦めない」、それは会見で確かに彼が発した言葉らしかった。事前に用意した内容をすべて覆すその発言は、ロバートの確かな精神だったのだ。それが実感を伴って感じられるうちに、ワトキンスにはある一つの疑問がふつふつと沸き起こった。
――自分は果たしてロビンと向き合っていただろうか。
例の研究に対する彼自身の思いも、叔父に対する思いも、もっとずっと昔――自分が彼を引き取った時も。内気な性格だと決めつけて、彼は自分と顔を合わせたくないだろうと思い込んで、遠くへ、遠くへ、遠くへ、彼を追いやって見えないふりをしていたのは自分の方こそではないか。その青い瞳の奥に、確かに燃え上がるような熱情を秘めていたというのに。
これは、吾輩が向き合うことを拒み続けたロビンの真なる精神に違いない。
世間は彼に厳しい言葉を浴びせかけている。宣言破りの「黒」技士だとか、術士を抹殺しようとしているとか、シヴィル・ウォーの再燃だとか、何も知らずに彼を謗る者を吾輩は許さない。ロバート・グレイヒルは吾輩の家族だ。今度こそ家族を救い、そして次に会った時には本心で向き合おう。……だが天はそれすらも許さなかった。
ロバートの家が火災で全焼したと報道があった。夜の街に銃声が響き、警察は事件性を疑っている。
実際、現時点でも彼の生死は定かではない。ネバダで目撃情報もあるし、誰かと一緒だとも言う。鉄道沿いに東に向かうように事件が発生している。これが彼の足取りなのか。ワトキンスはこの数日、彼のこと以外は何も手につかなかった。頼むから、生きていてほしい。
ブジ ナカマ トモニ アリテ オッテヲ ノガル
ワシントンの陸軍省に届けられた電報、送り元はソルトレイクシティの電信局、送り主は、ロバート・グレイヒル。
たったこれだけの文章、ワトキンスは感涙に咽び泣いた。ロビンは生きている!
喜びと同時に、彼が追われていることも明らかになった。甥を守らなければならない、何をもってしても。今度こそ約束を果たすのだ、彼を一番愛した二人と交わした約束を。
彼はついに立ち上がった。
ワシントン――コロンビア特別区は、アメリカ合衆国の首府である。いずれの州にも属さない連邦直轄地であって、この国の政治の中心である。合衆国の父、ジョージ・ワシントンはポトマック川沿いの湿気た低湿地に新しい国の首都を建設することを決定した。偉大な大統領の名を冠したワシントン記念塔は前年完成されたが、そこを起点に東西に緑地が伸びていて、東側にあるのが立法、司法の最高機関たる合衆国議会議事堂と合衆国最高裁判所。そして記念塔の北側にあるのが行政の中枢、「ホワイトハウス」と呼ばれる大統領公邸。大英帝国との戦争によって焼け落ちた公邸を再建するにあたって、焼け残った旧公邸の壁を白く塗り直して再利用したことからその通称ともなる白銀の建築が完成した。ホワイトハウスでは国民によって選ばれた大統領が居住し、その執務を行う。まさに合衆国の「顔」である。
ワトキンスはこの日、午前からホワイトハウスを訪れていた。普段は陸軍省にのみ出入りする彼がここを訪ねるのはあり得ないことであるが、これは自分から掛け合ったものだった。目的は勿論一つ、この「家」に住む男に相まみえることである。
入口の前で少し待たされてから、やがて中に通された。なるほど、行政機関にしては随分住宅のような設えをしていて、ここが彼にとっての家なのだと分かる。
大統領執務室は中央棟の二階に構えられる。ワトキンスは室の前に立つと、まもなく側近によって扉が開かれた。
南北に長軸を持つ楕円の部屋、南に三枚の大きな窓があって、残りの三方は扉が一つずつ。いくつかの本棚と椅子が部屋の隅にあり、一か所に暖炉がある。幾何学模様で飾られた壁紙とタイルの床を見ながらまっすぐに視線を奥へ伸ばすと、一つのデスクがある。そこには太陽を背にして一人の大柄な、軍人のワトキンスにも劣らないほどの大男がこちらを見据えていた。
「失礼します。」
男は黙って頷いた。ワトキンスが前へ進み出ると、彼はすっくと立ち上がった。
「お初にお目にかかります、クリーヴランド大統領。小生の名はワトキンス・グレイヒルであります。」

「や、噂はかねがね、グレイヒル大佐。」
グロヴァー・クリーヴランド――第二十二代アメリカ合衆国大統領。ニュージャージー州に生まれ法律を学んだ弁護士はバッファロー市長とニューヨーク州知事を歴任し、今年、長く続いた共和党政権を破ってこの国の大統領に就任した。
ワトキンスはクリーヴランドと握手を交わした。その手の大きいこと、リンゴなどすっぽり収まってしまいそうなほどだった。
「お忙しい中突然の連絡を差し上げたことをお詫び申し上げます。」
「構わないよ。私も話を聞きたいと思っていたところだ。将軍と顔を合わせたのはシヴィル・ウォーの終戦記念式典以来だろうか、もっともこうして言葉を交わすのは初めてだね。」
「光栄です。」
クリーヴランドは椅子に掛けて斜め上に部屋を見上げた。
「どうかな、リンカーン大統領の頃とはここも変わったろうね。」
「ええ、そうですね。」
「そこいらの設えも、この机も私の物に変えてしまった。良い仕事をするには仕事道具に妥協は許されないものだ。」
確かに、かつてのリンカーン大統領の机はこのように特別大きく、側面に繊細な彫刻が入ったようなものではなかった。
「私にはね、将軍、大統領として絶対の信念がある――誠実だ。私は正義と真実を愛し、嘘と不正を憎む、それはこの国の誰よりもだ。それにつけて、一つはっきりさせておきたいことがあってね。リンカーン大統領と共に付き従って戦ったあなたのことだから、民主党の私は嫌いかね。……なに、答えようによって何かしてやろうというつもりはない、ただ誠実に答えればそれでよい。」
「軍人は指揮官に従うが常。偉大な指導者にこそ従うものです。時の大統領が彼でなく別な者であったら、その男の命を受けたまででしょう。その上で、小生は上司を好きとか嫌いだとかで判断はしかねます。」
「そうかね。」
「つまらないことを訊いたね」とクリーヴランドはその話題を片付けて本題に取り掛かった。
「それでそちらからの話というのは、報告かね、提案かね。」
「敢えて言うなら請願と呼びましょうか、大統領閣下への。話は無論、我が甥についてであります。」
「うん、続けなさい。」
「彼に対する小生の立場は今朝の報道にある通りであります。」
「うん、あれは間違いのないことなんだね。しかしなぜ周囲に伝えることもなく突然の発表に至ったのかね。」
「それは当人の目に入るようにです。」
「ふむ。」
クリーヴランドは机に向かっていた体勢を変えて腕を組んだ。
「昨日、甥と思しき者から速達電報が陸軍省に届きました。それによれば、彼はその時点で同行者と共にソルトレイクシティにいたようです。さらには、彼が追手を逃れているとも書かれていました。これはサクラメントでの火災、銃撃事件、日毎に起きている鉄道沿線での事件と関連が疑われます。つまり、甥は何らかの理由で追われ、危険な状況にあると判断できます。その「何らかの理由」にはおそらく、世間で物議を醸している彼の研究が関係しているでしょう。……結論を端的に申し上げます。合衆国政府は国家安全保障上の事由からロバート・グレイヒルを保護すべきであり、大統領令を発動していただきたく存じます。」
クリーヴランドは目を瞑って石のように固く動かなかった。ワトキンスは電信柱のように直立していた。重苦しい空気が体にまとわりついて呼吸をも阻害するようで、彼はそれを辛抱していた。
クリーヴランドは目を開いて顔を上げた。
「証拠はあるのかね、ないのかね。」
「ありません。断片的な情報を繋ぎ合わせた推測です。」
「将軍、あなたは自身の推測をもとにアメリカ大統領に命令を出すことを『請願』したのだね。」
「はい。」
「さらなる情報収集に努めるとか、精査するとか、確実性を上げる努力をしなかったのだね。」
「事実であれば早急な対応が求められる故、確認を待たずに参りました。」
「すると私にはね、あなたが甥っ子を助けてくれと頼むために、大統領の前に立っているように見える。どうなのかね。」
ワトキンスは拳を握りしめた。
「その通りです。我が甥は命を追われる謂れなどございません、お力をお貸しください。……仮に、誰からも、如何なる協力が得られなかったとしても、小生は甥を救うために決起する所存です。そのためには「名将」の肩書も軍人の職も最早必要ございません。」
肩を震わせながら言い切る。クリーヴランドはまたも黙り込んでいて、ワトキンスが部屋を後にしようかと頭をよぎった時、不意に大統領は髭の下の口角を上げて彼を見上げた。
「どうか早まらないでくれ、シヴィル・ウォーの名将を離反させたでは方々に示しがつかない。まずは私の見解を話そう。」
ワトキンスは大変驚いて答えを強く促したくなるのを堪えた。「聞いてくれ」とクリーヴランドは語り始めた。
「君の甥、ロバート・グレイヒルに関する一連の騒動については外交問題に関わるので早くから政府機関が情報収集を進めていた。そして数日前に彼を取り巻く状況は一変した。実際のところ、将軍の予想は大方正しいといってよいだろうね。彼の自宅が火災に遭った夜に、彼は襲撃を逃れてエマソンという術士資産家の邸宅に避難した。それからはその家のお嬢さん、アンジェラ・エマソンと日本の軍人岡田稲熊、リニーというインディアンの少女と共に鉄道で東に向かっている。その道中で数度の戦闘を繰り広げながら。電報も本人が送ったことを確認済みだ。将軍、あなたの言う通り確かに甥は危険のただ中にある。」
「やはり……、敵は何でしょう。」
「不明だ。複数の犯罪組織に実行を依頼しているらしく、首魁は見えない。ただし、目的を探ることはできようね。鍵になってくるのは勿論彼の研究だ、実際に彼は今も自身の研究成果のすべてを肌身離さず持ち歩いている。だとすれば彼を襲う武装組織の目的はそれを手に入れることか、もしくは抹殺すること、そう考えるのが自然ではないかね。例の研究は合衆国社会の混乱を招くのみならず、諸外国が懸念を示し、名指しで非難すらしている。聞き及ぶ『術と時化を封じる』ことが本当ならば、社会に与える影響はあまりに大きい。いずれにせよ、我々はその全貌を知らない。将軍は本人から聞いたかね。」
「いえ、ですが『報道は事実だ』と言っておりました。」
「そうか、そうなのか。」
クリーヴランドは丸い顎をさすった。
「大統領、やはり彼の存在は戦略的に重要です。改めて保護するように命令を発してください。」
「待ちなさい、まだ私の見解を話していないだろう。ロバート・グレイヒルを保護するということは、彼の研究をも保護するということだ。研究の破棄は彼自身の意思によってのみ決定されるもので、合衆国政府は彼の内心を強制することなどできないからだ。しかしそれを行えば大きな反発を招くであろう。国内の術士を中心にヴィエナ宣言を遵守する技士や、教会の宗派などが。社会の混乱が引き起こす大きな悲しみを我々は知っているね。シヴィル・ウォーは二度と起こしてはならないよ。それだけではない、この件について諸外国から既に多数の通知を合衆国は受け取っている。あなたの甥の研究を保護すれば、それらの国から非難を受ける。それが行き着く先は、軍人であるあなたなら分かるね。列強のすべてを相手取って戦う戦力など合衆国は持ち合わせていない。それが重要なものであるとはいえ、一人の若者を救うために国民のすべてを危険に晒すわけにはいかない。――と、普通の政治家は考えるだろうね。」
語りながら、クリーヴランドの目の色が変わっていった。
「私は大統領だ。国民の生命と財産を守るのが使命だ。それならば、一人の若者もまた、星条旗の下に集うこの国の民に違いない。何度でも言おう、私は正義を愛する大統領だ。悪の試みによって合衆国の若き魂が失われるのをむざむざ見逃すつもりもない。」
「――公聴会を開こう。」
大統領は言った。
「これは合衆国の命運を左右する大きな決断だ。広く意見を聴かずして、どうして決定が下せようか。政府と議会に、各界を代表する実業家と術士とを召喚して私の最終的な判断を決めたいと思う。どうかね。」
ワトキンスは渋った。大統領がこれほどまでにロバートの救済を考えていることは何よりも心強い、まさしく正義の士であった。そしてその判断も合理的である。ロバートと合衆国とを天秤にかけるのなら、国民にだって意見する権利がある。だが一分一秒が惜しいこの時に、会議の席を設けることが如何に厳しいことか。その間にもロバートは命を落とすかもしれないのに。クリーヴランドはそんな彼を見やって優しく声をかけた。
「辛いがこれも試練だよ。この国は幾度となく試練に見舞われてきた。同胞に仇なす敵や危険が待ち受ける大地。万里の波濤を乗り越えても、新天地にあるのは試練ばかりだった。だがそれを乗り越えてきたのが我々の歴史だ。今再び試練の時が訪れている。そして国を背負って立つならば、彼もまた苦境を堪え忍ばなければならない。それができて初めて、一国が全身全霊を懸けて救うべき男になるのではないかね。」
「……その通りです、大統領。」
「さあ、公聴会を開く大統領令を出そう。時間がないぞ、列車を出せ、明後日の朝までに皆をワシントンに集めるんだ。」
突然の号令にワシントンが右へ左への大騒ぎの間、ワトキンスは鉄道を利用して次なる訪問地へ向かっていた。
ニューヨーク近郊にはハドソン川を挟んで郊外住宅地が広がっている。いずれも高所得者による住宅で、個々が広い前庭を持つ宅地を進んでいくには車が欠かせない。ワトキンスを乗せた車は一軒の住宅を目の前にして歩みを止めた。英国風の自然庭園には大小の垣根が不規則に植えられており、その間々に立つ低木は赤い花を咲かせている。石畳の道の突き当りに玄関があり、出窓を備えた日当たりのよい部屋が左右に見える。
ワトキンスは呼び鈴を鳴らして扉の前に立ち尽くした。しばらくして扉が開き、燕尾服の紳士が彼を出迎えた。
「グレイヒル将軍、お久しゅう。まさかこちらでお会いできるとは思いませんでした。」
「同感です。幸か不幸か、二人揃って東海岸にいるとは――エマソン卿。」
卿はワトキンスを迎え入れた。入って右側の室に招き、太陽降り注ぐ庭が見渡せる応接間に座らせた。
使用人が茶を出すのも待たず、ワトキンスは出し抜けに本題を切り出した。仰々しい社交辞令は不要、彼はそう考えていた。
「電報は届きましたか。この半日でかつてない早さで報せが回っておりますが。内容は勿論、我が甥、ロバート・グレイヒルへの対応についての公聴会です。」
「懐かしい名ですな、それを聞くのは何年ぶりか。質問の答えは『はい』です。」
「出席なされますか。であれば小生と共にワシントンへ戻りましょう。」
二人の前に茶が出される。卿は小皿ごとそれを手に取って、口の辺りに近付けた。
「そうする他ありますまい。」
目を閉じてカップを口につける。ワトキンスはそれを見て自分も目の前に出されたものを一口飲んだ。
「小生は午前に大統領と面会しました。その際に、彼らの現況についていくらか聞き及んでおります。卿はどれほど知っておられるのですか……貴公のご令嬢について。」
「その前に尋ねてもよろしいですか。将軍、あなたの本件に対する態度は今朝の新聞で表明された通り、それでよろしいですか。」
「間違いありません。小生は甥を全面的に支持します。研究の内容については、精査する余地があると考える。」
「そうですか」と卿はそっけなく答えた。それから、
「私にはあやつが分からない。」
と呟いた。
「サクラメントで銃撃があった日の行動については使用人と警察とを通じて知り得ている。夜中にロバート君は銃撃する追手を逃れて我が邸に逃げ込んだ。招いたのは我が娘のようだ。それ以前の昼間、あやつは警察署長に直通電話を繋いで火災があった通りの夜間巡回を大幅増員するように強く求めている。実際、それがいくらか功を奏したようだが……娘は昼間の内から何かを察知していたようだ。」
「現在の状況は?」
「使用人は数日前に彼らが邸宅を出たと。ただし目的地は意地でも答えぬ、娘がそう指示したらしい、ふざけたことを。」
卿は横目に窓の外を眺めた。
ワトキンスは今の言葉で確信した。ロバートには何らかの目的があって移動を続けているということが。鉄道という足跡を残す手段を使ってまで移動を続けているのは、どこかに目的地があるのだ。それはソルトレイクシティよりは東にある。
「ロバート君はなぜあのような研究をしたのかね。少なくとも中等学校に通っていた頃は実直で勤勉な少年だったのに。」
「お待ちください、エマソン卿。甥は術士に対する悪意を持って研究を行ったのではない、それは自信を持って言えることです。世間の評価は不当に歪められている。」
「では、あの会見は何でしょう。シヴィル・ウォーを収めたあなたがあのような会見を認めるのですか。」
「卿、どうかご理解いただきたい。あなたが、我々が思っている以上に彼は変わっていないかもしれないということを。」
卿はこれ以上将軍に対して語ることは意味がないと分かっていたので、「まあよいでしょう」と打ち切った。彼は蝶ネクタイに手を触れた。
「それよりも私に重要なのは娘のことです。私にはあやつが分からない。彼女が何を考えているのかが。」
「家庭を納められない家長など全くお恥ずかしい話ですがね」と語る彼は呆れ返っていた。
「ロバート君のことはしかと覚えておりますよ、私も、娘も。ですが将軍もおそらく噂にご存知の通り、あれは平民への理解が浅く排外的な者です。それがどうしてあなたの甥を助け、行動を共にしているのか。そもそも終ぞ今日まで交わること無かったであろうに。」
ワトキンスは眉を上げた。
「エマソン卿はご存知ないのですか。」
「何をですか。」
「我が甥と、貴殿のご令嬢のことです。彼らは先日まで共に居りましたが。」
ワトキンスはロバートとエマソン嬢との間柄について知っていることを話した。二人はロサンゼルスで会っていて、それから研究のためにアリゾナへ向かったのに同行していたこと。話を聞いている間、卿の表情は驚きから怒りへ、呆れへと絶え間なく変化した。
「卿はご存知のことかと思い込んでおりました。」
「初めて聞いた。全く、とんだ大馬鹿者だ。」
「代わってお詫び申し上げます。」
「いいえ、よい。謝られると私はロバート君のせいにしてしまう。実際にそうした以上、あやつの意思があるでしょうから。ですがしかし、あれが嫁入り前の娘であることは考えてほしかったですが。」
ワトキンスは返す言葉が無かった。卿は首を振った。
「ということは、あやつは彼の研究について何かを知っているから行動を共にしているのでしょうか。」
「それについては推察しかねます。ただしご令嬢が危険の中にあることは看過できません。甥は何故追手がある中か弱きご令嬢を連れているのか、それほど無責任な男ではありますまい。」
「いや、そうとも限らないのです。」
卿は何か言いかねたように暫し口ごもった。
「私はサクラメントの近くに森林を持っていまして、娘はよくそこに滞在していますが、そこで……鳥撃ちをしている。」
「狩りですか。」
言いながら卿は頭を抱える。
「確かに、術士は古来より自然と共に生きる民ですが……あやつは何か履き違えているのです。全くお恥ずかしい限りですが、とにかく、あやつは猟銃を取り扱うことができるのです。」
「なるほど。」
逞しいご令嬢ですね、とは言わなかった。これ以上は何も言ってやるべきではない。
「卿はお認めにならないかもしれませんが、小生はエマソン嬢に感謝しております。何であれこの状況で我が甥を支持してくださるなら小生にとっても喜ばしいことです。それに小生に代わって甥の傍に付いていると、これほど心強いことがありましょうか。エマソン卿、強いるつもりはございませんが、今一度強く訴えたい。今は世間のすべてそして未知なる刺客までもが彼らの敵である、我々以外に誰が彼らを擁護することができましょうか。」
「……申し訳ありませんが、私はまだ判断できません。」
「よろしい。公聴会は明後日に執り行われます。お答えはその時に。」
外出の準備がある卿に先んじてワトキンスは邸宅を後にした。庭先の花は色を変えず午後の日差しに輝かしく咲き誇る。
ソルトレイクシティのリゾオトに別れを告げ、列車で街を出て数時間、一行は既にワイオミング準州に到達している。
北は自治領カナダはブリティッシュコロンビアから、南はニューメキシコ準州のリオグランデまで、アメリカ西部を南北に貫く長大な山脈の名をロッキイという。「火と硫黄の国」とも称される神秘のイエローストーン国立公園をも有するこの山脈は標高一万フィートを優に超すような山々が連なり、「到達不可能」と探検家たちは語った。「到達不可能」なロッキイ山脈は大陸横断鉄道を建設するユニオン・パシフィック鉄道の最後の壁として立ちはだかった。この非常に困難な大仕事はアイルランド人の労働者によって成し遂げられ、この山々から東側へ向かう者は同会社が敷いた路線を進むことになる。目指すはオマハ、それで最初の大陸横断鉄道を辿る旅は終点を迎える。
谷間の駅、ロック・スプリングズで列車は暫く停止している。ここまで非常に長時間の鉄道旅を続けてきた四人の疲労は激しい。長旅の要領は停車時間に外へ出て凝り固まった身体を労わることだ。
列車が入る前と打って変わってホームは乗降車する者とくつろぐ者とで少々賑わいを見せている。これ幸いとばかりにつばが広い帽子を被った紅い頬の少年が商品を乗せた盆やら金を詰める鞄やらを携えて「新聞、ソーダ、シガレット」などと威勢のいい声を張り上げる。見慣れた物売りの光景である。
ロバートはベンチの傍に立って背中を伸ばしていたが、少年が目の前まで来たのでちょいと声をかけた。
「新聞をおくれ。」
「まいど。ソーダはいらんかね。」
「結構。」
ロバートは差し出された手に新聞代を置いた。細い指の手はそれを握って、引っ込めずにそのままでいた。少年は訝し気に上目遣いで彼を見るので、不審に思えた。
「足りなかったか?」
少年はまじまじと見つめる。
「おい、早くくれよ。」
「あんちゃん、グレイヒルじゃないの?」
突然名を呼ばれるのでロバートは身構えた。だがそれは少年の純粋な興味らしいと察してすぐに知らんぷりを決め込むことにした。
「誰だ、それは。」
「新聞読んでないのかよ、ロバート・グレイヒル!昨日ソルトレイクシティにいたって話だぜ?」
「生憎、新聞は誰かさんのせいで読めてないんでな。」
「やっぱりそうだよ、おれ新聞の写真で見たことあるもん。満員列車の中で銃を持った奴を狙い撃ち、あれ本当?」
「人違い。」
「絶対似てるんだけどな。」
ロバートは帽子に手をやって頭を抱えた。
「……分かったよ、ソーダも買ってやるからさっさとあっちへ行きなさい。」
「まいど!何本?」
「何本も要らない……いや、四本。」
どうせなら全員分用意しようと言い直した。少年は鞄から新聞を一部とコルク栓のついた透き通った瓶を取り出した。ロバートが金を出すとそれと交換した。
「ねえ、やっぱりグレイヒルなんだろ?」
「君、しつこいぞ。」
ロバートがボトルと新聞とを抱えるのに難儀していると、ホームの向こうで風に当たっていたアンジェラが寄ってきた。
「ロバート、何していて?」
その瞬間彼は顔をしかめてアンジェラを睨みつける。少年の顔がぱっと明るくなった。
「何よ。」
「やっぱりグレイヒルだ!」
ロバートは矢継ぎ早にソーダ瓶を彼女に押し付ける。
「あのな君、『ロバート』がアメリカに何人いると思ってるんだ。それだけで僕をグレイヒルだと決めつけるつもりか。」
「絶対そうだ!」
アンジェラは漸く事を理解したようで、眼光鋭く少年の様子を窺っていた。ロバートは新聞を丸めて彼の前で振った。
「ほら、用が済んだらあっちへ行く。僕は暇じゃないんだ。」
「ちぇっ……。」
悪態付きながら物売りの少年は向こうへ歩いていった。聴こえない距離まで行ってからロバートが「リニーと稲熊も近くにいたらまずかったな」と呟く。
「敵ではなさそうね。」
「僕も名が知れたものだ。」
アンジェラは渡されるがまま胸に抱えた四本のソーダを見る。ラベルはなく、ガラス瓶の内側で気泡がコルクの方に向かって浮いていくのが見える。
「ところであなた、コルク抜き持ってる?」
「……稲熊が切ってくれるだろ。」
お構いなしにロバートは新聞を開いた。
「『名将』、支持を表明」
ロバートは思わず目を見開いた。アンジェラが隣から覗き込む。
「ワトキンス・グレイヒル大佐は甥のロバートを巡る騒動に対して彼に全面支持の立場を表明」
「彼の研究内容がヴィエナ宣言に反するか否かについて『精査の余地あり』と述べた」
「『我が甥の自由と権利を脅かすすべての行為を断固非難する。』」
「一部からは『身内贔屓ではないか』との反発も」
二人は顔を見合わせた。アンジェラの表情が驚きから笑顔に変わる。
「やったわね!」
彼女はロバートの首に腕を回して頬を摺り寄せた。
「……冷たっ!」
首筋に冷ややかな感覚が走って肩がこわばる、ガラス瓶の尻が触れていた。すぐに身を引いたにをアンジェラはふくれて、不意に彼の頬に瓶をぐいぐい押し付けた。
「やめ……やめろって。」
ロバートは瓶を押し返して新聞をもう一度開いた。軍服に身を包んだ見慣れた顔の写真が大きく載せられている。
「叔父さん……。」
目頭が熱くなるのを抑えられなかった。
甲高い声が二人の背後で上がった。
「やっぱりグレイヒルじゃんか!」
機関車は懸命に客車を牽いて高地を進む。先が膨らんだ金剛石型の煙突が蒸気を噴き上げる。
初期の蒸気機関車は湯を沸かせば噴き上がるような飽和蒸気を推進力にしていた。その後技術開発が進んでボイラーで念入りに過熱した蒸気を用いるようになり、機関車の効率は格段に上昇した。それでもアメリカの広大な土地を進む機関車は補給を行わずして走り続けることはできない。線路上には補給塔という地下水か近くの水場から汲み上げた貯水槽がいくつもあって、機関車は数時間おきにそこで停車して水やその他の消耗する素材を補給する。
彼らを乗せた列車は補給塔を前にして徐々に速度を落としていた。辺りは広葉樹の森林が深く生い茂って豊かな場所である。
思わぬ「追跡者」に見つかってしまったことで、ロバートらは同乗する乗客にその正体が知られてしまった。今は誰もいなくなった最後車を広々と使えている。どこかきまり悪いような心持ちであるが、襲撃を察知しやすいという点においてはこの状態は望ましくもある。
列車はやがて完全に停止した。前方には水を蓄えた円筒形の水槽が見えて、そこから管が炭水車の直上に伸びている。水の補給をしているのだ。
客車の中央辺りの席に座って四人は悠々とした時間を過ごしていた。
稲熊は心置きなく刀の手入れをしている。
「ロバート、叔父上がそのように表明なされたならば、これより世間の風向きは変わるか如何。」
叔父の写真が載った新聞はロバートが座る席の脇に畳んで置いてある。
「勿論変わるだろう、だけどどの程度かは分からない。世論の成り行きによっては叔父さんの影響力が小さくなるだけかもしれない。無論そうさせるつもりはない。どう変わるかはむしろ僕の行動にかかっていると言える。」
「主、ニューヨークに届かずして公に姿をあらわすつもりか。」
「必要に迫られれば、あるいは。」
「いかがなものかしら。ただでさえ行程に大幅な遅れが生じていてよ。」
「それもそうだ。」
戦闘によって各地で足止めを食っているので、当初の予定より遅れているのは事実である。それによって旅の負担が少しずつ彼らに乗った重しを増やしていた。
「それにしても叔父さんの助け舟は大切にしなければ、彼には返さなきゃならない恩が……」
言い終わるより早く、猛烈な爆音がロバートの耳を劈いた。
倒れ込んだ体に四散した車体の細片が降り注ぐ。
耳鳴りの音を聴き、霞む視界を凝らしながらかろうじて起き上がった彼は一変した車内の様子を見た。壁がない。進行方向左側の壁の一部が消し飛んで、外の森が見えている。通路を挟んで反対側の座席はいくつかがまるごと無くなり、いくつかは背もたれがどこかへ消えてしまった。客車には大きな大きな風穴が空いていた。
周りを見れば三人も倒れている。助け起こそうとして、ロバートは非常にくぐもった自分の声を聞いた。
「大丈夫か!?」
幸いなことに皆は倒れ込んだ時の打ち身といくつかの木片に当たった程度で、大事には至らないようである。仲間の声ははじめひどく遠くに聴こえて、徐々に近づいて聴きとれるようになった。
「何が起きたの。」
「爆弾だ。向こうの席に座っていたら命は無かった。立ち上がれるか。」
そう声をかけてからロバートは銃を抜き、車体に空いた風穴の縁に立って外を窺った。爆弾を投げ込んだ敵が近くにいるはずだと思って眺め回してみたものの、そこには敵の姿が無かった。十ヤードくらい先にある線路脇の木立の奥に潜んでいるのだろうか。
「ダメだ、敵が見えない。」
「野砲でも撃ち込まれて?」
アンジェラは頭を抱えながら床に置いたライフルのケエスを解錠する。上面の埃を払い落とし、開いた中からライフルが顔を覗かせる。
「分からない、そう遅くないうちに次が来るぞ。」
「一旦外に出る?」
「他にも敵がいるかもしれない。通路に伏せて。耳を塞いで、口は開けているんだ。」
通路に匍匐してロバートは尚も外を窺った。車体の穴は足元から天井に至るまで、たっぷり二列分は空けられている。
最初の爆発から一分以上が経っている、野砲なら次弾を撃ち終わっていてもおかしくないが。
――ヒュッ。
炸裂、凄まじい音を立てて今度は四人の頭上に天井の木材が降ってきた。見れば窓の上から天井の半分以上までに穴が空いて、青空が覗く。ロバートはそれを見上げていると、頭の中に違和感が湧き上がってきた。
何かおかしい。何が?爆薬を投げ込んでいるとしたら、爆発寸前の風切り音は何だ?野砲の類なら着弾の後に砲声が轟くのでは?そもそもこの森の中で野砲が展開できるのか?
――違う、そうではない。
「ダイナマイトだ!」彼は声を上げた。
「投げ込んでる敵は見えないのでなくて?」
「これはおそらくダイナマイト砲だ。上を見てみろよ。」
彼が指さすように皆は客車から見える青空を仰いだ。
「砲弾はその質量と火薬の両方でもって目標を破壊する、だからこうして着弾点だけに穴が開くのは妙なんだ。だとすれば弾はもっと軽い――ダイナマイトだ。」
「ダイナマイト砲とは何ぞ。」
「圧縮空気でダイナマイトを飛ばす小口径の砲だ。ポムプで空気を圧縮して……つまりでっかい『吹き矢』だ。砲声も煙も無いから発射位置を悟られにくい。」
「何でもいいけど、このままじゃ列車ごとダイナマイトで吹き飛ばされてよ!」
「次弾に手こずってるところ、一門しかないらしい。発射地点を特定して叩くぞ。」
ロバートは身体を起こし、残っている座席を遮蔽物にして木立の様子を窺った。
「車両の前半分は無傷だな……アンジェラ、そっちに移動しろ。あいつらにもう一発撃たせるから、発射位置を特定して君のを撃ち込んでくれ。」
「ま、待ってよ。確かに拳銃よりは射程があるけれど、向こうは砲でしょ?」
「いいんだよ。ダイナマイト砲は精度が悪いんだ、射程は最大でも精々九百ヤード、この森で射線を通すにはもっと近付かないといけない。数百ヤード以内に必ずいる。それなら君の擲弾筒が届く。」
彼は「頼んだぞ」と一言告げて返事は待たず、砲撃の影響を受けていない反対側の壁に貼りついて車窓から外を覗き込む。
「稲熊、あの三本木のところ、見えるか。」
隣の窓に貼り付いて稲熊も外を見る。三つ並んだ木の陰にこちらを窺う人影がいくつか見える。
「とどめを刺すための別働隊だ。僕が外に出てあれを引き付けるから、前の扉からこっそり出て裏に回り込めって言ったら……」
「承知。」
ロバートは微笑んだ。
「頼もしいな。」
「私も行く。」
彼の後ろから一緒に様子を窺っていたリニーは立ち上がった。
「左の二人は任せて。」
「よかろう。」
「時間がない、行くぞ!」
言い切るなり、ロバートは車体の穴から飛び出して下の地面に降り立った。そのまま列車の後ろまで走って線路の盛り土に身を隠した。これで背後の敵影からの攻撃を遮れるが、この位置は砲撃の正面に身を晒している。先刻の間隔をもとにすれば、もう三十秒もしないうちに撃ち出される次弾に身を引き裂かれる。その前に線路の向こう側に渡ってもう一度身を隠さねばならない。
三本木の陰に向かって一発撃ち込む。この距離で当たるはずはない、精々注意を惹きつけるための陽動だ。アンジェラは配置についている、稲熊とリニーはロバートと反対方向から外に出て木立に駆け込むところだ。二人の支援が間に合うか、そこが重要だ。
拳銃の銃身を線路に置いて狙いをつける。これで多少マシになるが、これでも身を庇いながら命中させるには容易ではない。拳銃は近距離用の銃器、相手が持っているであろうライフルに比べたらずっと精度が悪いのだ。
すぐそばの線路がカツンと甲高い音を立てた。鋼鉄の表面に擦れた跡を残す。数インチ横にいたら当たっていてもおかしくない。ロバートは背筋が凍える思いだった。
弾倉の弾を撃ち尽くした、まるで当たらなかった。あとは二人頼みだが――姿が見えない。今にも背中にダイナマイトが撃ち込まれるやもしれないのに。
早く――。
実のところ二人はしっかりと視界の中にいた。幹の陰にぱっと現れたので、ロバートは驚いた。鮮やかな身のこなしで瞬く間に敵を打倒し、反撃の隙を与えない。やがてロバートに対して合図を送ったのを皮切りに、彼は線路を踏み越えて倒れ込むように線路の反対側へ跳んだ。
――ヒュッ。
爆裂、耳鳴り、降り注ぐ土。首筋から服の中までも入り込んでくる。頭に降る分だけは帽子が守ってくれる。
何も聞こえないし、土煙が目に入って痛い。背中が重い。いつまでも伸びていられないと、左手で地面を押して上半身を上げる。至近距離での爆発が平衡感覚まで失わせるが、汚れていない手の甲で目を擦って何とか周りの景色が見えるようにする。
アンジェラが車両のデッキに立っている。ライフルを抱えて、こちらに何かを伝えようとしている。晴れやかな顔だから、きっとやれたんだろう。こちらも無事だから何か反応をしてやろうとする。
稲熊とリニーとが木立から駆け寄ってきてロバートに手を貸した。ロバートはようやく耳が使えるようになってきた。
「大事ないか。」
「ああ……」
「間一髪だったね。」
アンジェラの声も聞こえてきた。
「列車が出るわ、急いで!」
列車は補給を中断して発車の用意が整っていた。
「立てるか。」
「ああ。」
彼は稲熊に手を引かれながら立ち上がった。列車に向かって歩き出そうとして、すぐに足元から崩れ落ちてしまった。
「ロバート!」
自分でも何をやっているんだと立ち上がろうとして、その時初めて彼は脚に痛みを覚えた。地面に肘をついて後ろを振り返れば、両脚のゲートルが見慣れない赤色に染まっていた。
爆発で弾けた線路の部材が彼の脹脛を裂いていた。
最後車両に致命的な損傷を受けた列車は最寄りの車両基地、すなわちシャイアンで再整備を余儀なくされた。
シャイアンはワイオミング準州最大の都市。高い鐘塔を持つ駅舎を中心として草原地帯に広がる新興都市は、ほんの二十年前には存在しなかった。
大陸横断鉄道の建設に際して前哨基地としてこの土地に最初の駅が設置されてから、ここには線路建設の労働者やその生活を支える商店主などが住まい始めた。以来人口は急激に増加し、大陸横断鉄道の開通と共にシャイアンは沿線の「都市」に成長するまでに至った。かつて都市あるところに路線を引いていた鉄道は、今では路線あるところに都市が開拓される。シャイアンは現在もユニオン・パシフィック鉄道の車両基地が置かれ、その存在を中心に街が動く、紛れもない「鉄道の都市」である。
幸いにして列車内に揃っていた品々で応急処置を施すことができたロバートは大事に至らず、自身で行った手際の良さは後で医者に診せても感心を受けるほどだった。現在は宿に転がり込んで安静にしているが、ベッドで楽にしていてもズキズキと痛むのは手の施しようがなかった。
ベッドに仰向けになって膝を直角に曲げる。脹脛がリネンにつかないようにし――それでも痛むものは痛む。それだと言うのに這う這う筆記用具を持ち出して論文の続きを書こうとするので、底抜けの熱心さは感心に値するがついには没収されてしまった。とうとう気を紛らわせるものが無くなって彼がぼんやり天井を見上げて呻いていると、アンジェラがそれを見ていて急に「買い物に行ってくる」と外に出る支度を始めた。先日の件もあって単独行動は慎重にならざるを得ないと言ったが、リニーを連れて心配するロバートをよそに外へ消えてしまった。
部屋に二人残されると、稲熊は近くの席に座って刀の手入れを始めた。ロバートも思い立って傍に置いた拳銃を抜いて各部の部品を点検した。
回転式拳銃は機構が単純でよい。ライフルと違って弾倉で目詰まりを起こさないし、雨や土に晒されたってすぐに立ち直る。自然、ならず者、インディアンの狩人、それらすべてが敵になりうる西の荒野を開拓するのはこれが無くては成し得ない。
黒鉄の銃身、弾倉と引き金との間にある部品には尊敬する叔父さんの名前が刻まれている。彼はそれを右手で構えて奥の壁に狙いをつけた。撃鉄を起こし、呼吸を整えて、引き金を引く。軽い駆動音を鳴らして撃鉄は空を叩いた。
「一体、あとどれくらいこれを使うことになるんだろう。」
そんな言葉が彼の口から洩れた。稲熊は顔を上げて何も答えずに銃を撫でる彼のことを見ていた。
「腕が無事でよかった、腕があればこれが使えるし、ペンも使える。」
「歩くことはできるか。」
「歩くだけなら我慢すれば問題ないさ、かなりぎこちない歩き方をするだろうがな。激しく動かすのは当分難しい。」
「走れぬか……。鉄道に乗りし内はそれでよいが。」
「いいんだ、退いてばかりの人生、逃げられなくなるくらいがちょうどいい。」
弾を込め直して銃をしまう時に足を動かしてしまい、またもズキリと痛み、顔を歪めた。
一時間以上は経った頃、部屋の扉を叩く音がして「帰ったよ」とリニーの声が続いた。稲熊が立ち上がって扉を開けてやろうとしたら、アンジェラが「下の炊事場を借りてくるから」と言って足音が遠くに行ってしまった。残された二人は目を見合わせて首を傾げた。
高級なホテルでもなければルームサービスのコーヒーが出てくるはずもないので、必要な飲み物を自分で淹れる場として炊事場が解放されている。勿論鍋も使わせてくれる。街の安宿では食事の類は自分で用意する方式であるところが少なくない。
木炭式のストオブが置かれた横に調理台があり、アンジェラは真上のラムプを点けて台の上に持ち帰った品を並べた。近くの酒場で買った蒸留酒に、籠に入っているのは丸い葉、深緑の草、早熟の実に小さな白い花など。これらはすべて街外れの草原で採った野草である。彼女は一つ一つ確かめながら「あれがなかったけれど構わないわ」などと呟く。
「お湯を沸かしましょう。」
ストオブに火が入り、鍋で湯が沸かされる。それを待っている間、アンジェラは野草を一つ一つ選り分けて使い物にならないのをはじいてゆく。リニーはその隣に立って覗き込んだ。
「やっぱり、これって……」
「あの人の傷に効くようにね。作り方が分かるの?」
彼女は頷いて、隣で同じ作業を始める。
「我が家に伝わる薬草の調合の仕方、昔お母様に教えてもらってよ。」
「白人の術士にも同じものがあるんだね。」
「調合は親から子へ代々伝えられる、その家系ごとに独自のやり方があるのよ。術士が森の中に住み、魔術師と呼ばれていた時代から続く。中世には『魔女狩り』の時代を経たけれど、それでも魔術師として自然と共に生きることを辞めなかった。産業革命の時代に彼らの生活は一変してしまうけれど、魔術師の暮らしの知恵は脈々と受け継がれてきたって。そしてそれは、アメリカでも。新大陸の新しい動植物を前にして術士たちはまた新たに薬草の調合を覚えた、ある程度はインディアンの知恵も借りてね。」
「だから私が教わったものと同じなんだ。」
野草の選別を終えると、アンジェラは深い皿に蒸留酒を出して、そこに野草を浸けた。
「アルコールで薬効を引き出すの。」
「懐かしいな。」
鍋の火加減を見ながらリニーの口からこぼれ出た。
「リニー、故郷には帰らなくて?」
「寄宿学校のみんなを助けるまでは、帰れない。」
「それじゃあ半年や一年の間に帰れるようなものではないわね。」
「うん。ひょっとしたら、もっと先かも。」
「一度帰ったら?部族の同胞が力になってくれるわ。」
「私が行ったらむしろみんなが危ないから。」
「そうだとしても、お父様やお母様はあなたの顔を見たがっていらっしゃるでしょう。」
「本当は、帰りたいよ。」
リニーは屈んだ。木炭が全体を真っ赤にして強力な熱を放っていて、覗き窓のついた鉄扉越しに熱気が顔にも届く。それは機関車の火室を覗いた時と似ている。
「お母さんとお父さんに会いたい。みんなと過ごしてたあの頃に戻りたい。」
瞳に映り込んだ炎が揺らめく。顔が熱い。
「でも、進んできた道を戻ることはできない。私たちはこれまでと違う生き方を見つけなきゃ。」
リニーは腰のナイフを抜き取った。戦いの最中もしっかりと結び付けてあって失くしたことはない。たった一度没収されたのを除けば。刃になっている黒く光沢のある石は、ガラスのように表面が滑らかだ。遠くの火山帯で採れる特別な「火の石」なのだと聞いている。いくつもの部族の間を渡って彼女の先祖に辿り着いたという。
「これは、酋長の家系に伝わる祭祀用のナイフ。邪を斬り祓い、部族を導くもの。これを持っている私は、みんなを導かなきゃ。私がみんなを、救わなきゃいけない……」
刃が削れた面ごとに炎の光を反射している。手が震えるごとに違う面から反射した光が目に飛び込んでくる。
不意に彼女は肩を抱かれた。真後ろにアンジェラが床に膝を着いて、背中から彼女を抱きとめていた。直に感じる柔らかい体温の中に、リニーは耳元で優しい声を聞いた。
「一人で頑張らなくたっていいじゃない。あなたの仲間はみんな、一人ではここまで来られなかった。だからあなたも、一人で行かなくたっていいわ。」
リニーは自分を抱く手に触れた。決して冷めることのない熱をその手に感じながら、一人で最後の涙を流した。
湯が沸き上がるのを合図に二人は作業に戻った。
薬草を湯がいて紙などにくるんで絞ると薬液を抽出することができる、それからは温度を保ちつつ匙を使って分量を厳密に量りながら調合を進めていく。一部の素材は砕くなりして混ざりやすくしてからその中に入れる。
薬液をかき混ぜているアンジェラにリニーは母親について尋ねた。
「あなたのお母さんはどんな人なの?」
「……どうかしら。」
「『どう』って?」
「私にはよく分からなくてよ。」
アンジェラは調合を続ける。
「あまり感情を表に出すことが無くて、家の外ではいつもお父様の隣について押し黙っている。術士資産家の妻としてあるべき姿を知っていたのね。いつか私もあんな風にならなければいけないと思ったらそれが嫌で、気付いたらお母様のこともあまり好きではなくなっていた。向こうは向こうでそれでいいって思っているでしょうね。」
思いの外冷え切った答えが返ってきたのでリニーは衝撃を受けた。
「薬の作り方を教わった時は?」
「私が子供の頃に『大事なことだから』と丁寧に教えてくれてよ。今思うとあれも本当の顔だったのかは分からない。術士として子孫に技術を継承しなければならなかったからそうしたのでしょう。」
「でも、立派な人なんだよね。」
「そうでしょうね」と、短く答えた。
「ロバートはいつも、あなたのお父さんのことをそう言っているけど。」
「社会的には非の打ち所がない人でしょう。家族に対しても社会的に当然の振る舞いをしているだけなのよ。でもそれは私にとって良い父親ではなくてよ。……こんな話をして悪いわね。」
奇妙なことに、それから彼女はふふっと笑った。
「でもねえ、こんなのはもうやめようかと思っていてよ。ライフルを担いで森の中を歩くのも、あれこれと人に当たり散らしてひんしゅくを買うのも。近頃は考えが変わってきたの。」
「そうなの?『アンジェラ風』で悪くないと思うけど。」
「何よそれ。」
「冗談。」
アンジェラは訝しげに彼女を覗き込んだが、それからすぐに元に戻った。
「私にとって彼がそうであったように、彼にとって私は良い娘じゃなかったって。きっかけはいろいろあるの。一つはロバートを助けるために我が家をまとめ直したこと。一つは彼の研究について行って旅したこと。――フロンティア・スピリット、お父様に耳に胼胝ができるほど言われたことが、悔しいけれど、やっと分かってきたの。――はい完成。」
小鉢には強いとろみのついた緑色の液体ができている。鼻を近付けると野草の香りが鼻の奥でツンとした刺激として感じられた。
「これを『技士さん』のところに持って行くわよ。」
炊事場を手早く片付け、小鉢に匙を乗せて階段を上る。手すりに片手をかけながら上っていると後ろからリニーが話しかけた。
「アンジェラって性格が悪いと思ってたけど、そうじゃなかったんだね。」
「誰がどう言おうと私は私よ。」
「ロバートのためなんでしょ?」
「どうしてあの人の名前が出てくるのよ。」
部屋の扉を叩くと、稲熊が出迎えた。彼は見慣れない小鉢を覗き込んだ。
「其は何ぞ。」
「彼のためにいいもの作ってあげたのよ。夜中に痛くて騒がれたのじゃこっちが大変でしょう。」
訝しげに見つめながらも二人を迎え入れる。怪我人はベッドで研究資料の一部を眺めていたが、二人が帰って来ると振り向いた。
「随分遅かったな。」
「ほら、これお飲みなさい。」
ロバートは顔の前に突き出された小鉢に目を寄せて覗く。
「何だこれ。」
「怪我人ならこれをお飲みなさい。」
「なるほど、薬か。」
席に戻った稲熊は納得してしきりに頷く。
「これ、もしや術士が調合するっていう薬か?君が作ったの?」
「勿論。」
「アンジェラが真心込めて作ったんだよ。」
口元にぐいぐい近付けられる小鉢に彼は仰け反って距離を取る。さらに小鉢が近付く。避ける。
「現代医学が発展した世にこんなものが通じるのか?……なんだかそこらのどぶをさらってきたような臭いがするんだが。」
「失礼ね、薬だって言ってるでしょ。減らず口ばかり利いてないで早く受け取りなさい。それか口をお開けなさいな。」
「わ、分かったから近付けないでくれないか。」
ロバートは受け取った小鉢の液体を匙でかき回す。深緑のどろどろした液体はラムプの明かりに照らされて恐ろしげに光る。中にザラザラと細かいものも入っているらしい。三人の視線を感じながら、仕方なしに一杯掬って匙の先がつくかつかないかという程度の量を口にした。
次の瞬間、彼は舌を突き出して顔をしかめた。
「苦い!!」
「子供じみたこと言ってないでよ。」
「良薬は口に苦きものぞ。」
「想像を絶している!」
「うるさいなあ、ちゃんと飲まないと元気になれないよ。」
「僕は元気だ!」
「どこがよ!」
「ご厚意は大変ありがたいのですが結構です!」
小鉢をベッドの脇に置いて倒れ込む。ロバートは目を固く結んでそのまま転がっていたが、リニーの呟きで目を開けた。
「……二人で頑張ったのに。アンジェラなんか、あんなに苦労して野山に分け入っていたのに。」
アンジェラは俯いて、放置された薬を手に取った。
「あなたが辛そうだったから、少しでも役に立てればと思ったけれど、余計なお世話だったわね。捨ててくる。」
「待て」、立ち上がる彼女にロバートは言った。彼女の手から薬を奪い取ると一息にほとんどかきこんでしまった。震える指でコトンとかろうじてそれをベッドの脇に置くと、枕に顔を突っ込んだきり動かなくなってしまった。
二人の女が顔を見合わせてしてやったりとにやけ顔になるのを見て、稲熊は身震いした。
小鉢に残った薬を寄せ、アンジェラは顔を上げた。
「稲熊、怪我していたわね。残ってるから飲んでおきなさい。」
「げ。」
彼の顔が薬液のように青ざめる。
「某は完治しておる。」
「ウソ。」
「待たれよ……」
ロバートの腕がふらふらと上がる。ロバートは身をこわばらせる稲熊の方に向けて、弱々しく十字を切った――。
ベッドに二人の男がうつぶせで枕に顔を突っ込んでいる。すっかり空になった小鉢、アンジェラは寝る支度を始めようかと動き出した時、はたと気が付いて「ああ」と声を上げた。
「お砂糖を入れるのを忘れていてよ。」
虚しく枕を叩く音だけが部屋に響いた。
――しかし、いくらか悔しさが滲むくらいに、薬の効き目は良かった。ロバートの脚は安静状態では痛みも感じられなくなって、ともすれば怪我していることを忘れて動かしてしまうくらいだった。傷口も確実に快復に向かっていた。
あまりの効果に驚いて、翌朝彼はアンジェラに何が入っていたのかと尋ねた。
「教えないわ。」と彼女はそっけなく答えた。
「なんでだ。」
「薬の調合は家族以外に教えてはいけなくてよ。そういう決まりなの。」
「そういうものなのか。」
「他にも熱冷ましとか酔い覚ましとかあるけれど、全部駄目。いい加減な調合で真似されたら困るのよ。実際のところ、無責任に市場に出回るには良くない成分も時として含んでいるからでしょう。」
「なるほど、れっきとした薬物というわけか。」
「――家族になれば教えてよかろうな?」
稲熊が傍から横槍を入れた。
「うん、確かにそうだ。そしたら教えてくれる?」
「は?」
「冗談だよ。」
彼女はむっとして向こうへ行こうと背を向けた。数歩歩いてからロバートに呼び止められてふっと振り返った。
「何よ。」
「気持ちは嬉しいが、あまり単独行動するなよ。君に何かあったら大変だ。」
それを聞いて、アンジェラはふふんと鼻で笑う。
「元々の配合にはなかったけれど、『あれ』を入れた効果があってよね。」
「……何?」
「冗談よ。」
すたすたと行ってしまう。ロバートは喉仏に手をやって昨日の味を思い出し、無意識に顔が歪む。
「……魔女だ。」
「魔女だな。」
ネブラスカ――中西部の『海から最も遠い』州、大西洋も太平洋もメキシコ湾も、大海原を目にするには少なくとも三つの州ないし準州を越えなければならないのである。無限の大平原、グレイトプレーンズは州の大部分を占め、どこまでも広い土地で耕作や放牧が営まれる。
白人が到達する以前、数千年の昔から平原のインディアンたちはこの地で獣を狩って暮らしてきた。十九世紀の初めにこの地に分け入った探検家は平原の中に聳える尖岩を発見した。この有名な史跡はチムニイロックと名付けられ、西へ向かう人々の道標となった。ネブラスカは「西の始まり」の地点であり、ここを越えた開拓者たちには過酷な冒険が待ち受けていた。それでも彼らは尖岩の向こう、太陽が沈みゆく大地に栄光を透かし見ていただろう。
もう一つの「西の始まり」は西経百度線である。大陸の気候は西経百度線を境にして大きく変わり、その様子は景色にも現れる。すなわち、「緑豊かな東部」から「砂混じりの乾いた西部」へと表情を変えるのである。その西経百度の境はまさしくネブラスカ州の中央を貫く。西海岸、カリフォルニアを出発した四人の旅はいよいよ大陸の中央を越え、東側へと渡ろうとしていた。
列車はネブラスカの平原を走る。プラット川の流れに沿ったこの路線は自然豊かで車窓にも緑が多く、長らく赤や褐色の荒野ばかりを目にしてきた四人にとっては目を楽しませるものであった。
今朝の朝刊でロバートは合衆国政府が彼と彼の研究に対する処遇を決めるための公聴会を予定していることを知った。政府内の人間に政治家、資本家、有力な術士などが一堂に会して行われる公聴会というのは、全く前代未聞のことである。各方面がいかに「ロバート・グレイヒル」という存在を憂慮しているかを窺い知ることができる。こういった会議は本来であれば当の本人が関与すべきであろうに、その機会が得られないのは残念だ。もっとも、彼は叔父さんに整えてもらった会見を大波乱のうちに終わらせた張本人であるから人前で弁明をするのはもううんざりだった。
公聴会ではロバート・グレイヒルに対する処遇が議題として扱われる。この公聴会をもとにロバートに対する政府の対応が決定されるということで、それは合衆国政府が味方になるか敵になるかという重要な決定に他ならない。もし、叔父さんの思い叶って政府が彼の権利を守るとなれば研究は守られ、彼を謂われなく謗ったり命を追う者はアメリカの敵になる。逆に政府が研究をヴィエナ宣言に反する非倫理的なものだとして彼を訴えれば、ロバート・グレイヒルは国家の敵となってこの旅も単なる逃亡とされる。公聴会の成り行き次第で彼の生命が決まる、ロバートはまな板の上に乗せられて隣でフライパンの油がバチバチと音を立てているのを聴いている気分だった。これから如何様に調理されるのだろうか。
「『九枚……十枚、十一枚、十二枚……』」
稲熊が演技っぽく手を動かしながら数字を数える。
「『――十五枚、十六枚、十七枚、十八枚。』」
彼は首を動かして別な登場人物を演じた。
「『やいお菊、皿は九枚しかないはずなのになぜ十八枚も数えるんだ。』」
「『分かんないかね、明日は休むから二日分数えたんだよ。』」
最後の台詞を言うと彼は黙った。しばらく列車の揺れる音だけが響く。全員が目をぱちくりさせる。
「……分かった?」
彼の隣に座るリニーが眉を顰めて尋ねると、ロバートとアンジェラは揃って首を横に振った。
「その幽霊、ヘンでなくて?」
「左様。」
「幽霊っていうのは生者に何かを伝えるために現れるものだろう。井戸で皿を数えるだけなら、幽霊になることないだろう。」
「だから、これは冗談なのだ。」
「話の設定が不自然だって言ってるのよ。」
「それがご愛嬌也。」
稲熊はすっかり不貞腐れてしまった。ここにいる外国人たちときたら、滑稽な話をしてもくすりともしない割に、話だけは真剣そのもので聞くのだから、どうにも収拾がつかなくなるのだった。
「日本の冗談話は前置きが長くてよ。」
「否、話の途中にいくつも滑稽な箇所があったであろ。むしろ、滑稽なのが『パンチライン』のみのアメリカン・ジョークこそ趣がなかろう。」
「どこがよ?」
「ぬう。」
「……なんとなくは分かったかな。」
こうして例の如くきまり悪くなるが、つまらないと言う割に彼らは日本のことを訊きたがった。そういう時には落語を話してやるのが一番会話が盛り上がったので、結局はこれが好評なのだ。
大平原の中を列車は走る。会話も一段落して今はまどろみの中にあって、ロバートだけは熱心に物を書いている。この段階では頭の中にあるものを文字に起こすだけなので、以前のように資料を食卓におっ広げる必要もない。アンジェラに教化されたわけではないが、全く反省がないわけでもない。その彼女は今、隣でうつらうつらやっている。そうするくらいならぐっすり眠ってしまえばいいのに、人が書き物をしている隣で眠りこけるのは気の毒だと感じているのだろうか。
ロバートは何の気なしに車窓に視線を移した。窓枠の格子を挟んで向こうの草原と空――小さな違和感に気付いた。それを確かめるために彼は窓を開けて首を外に出し、列車の足元の辺りの地面を眺めた。彼が突然奇妙なことを始めるので、三人は目が覚めて彼を見た。
「どうかした?」
「……やっぱり。」
彼は席に直って外の景色を見るよう促した。
「遅いんだ、列車が。この分だといつもの半分に満たない、時速二十か、二十五マイルってところだ。」
三人も車窓を眺めて互いに頷いた。
「何か理由があってか。」
「時化だ。時化そのもので機関車の速力が抑えられているか、もしくは時化の兆候があって安全のために速力を落としているかだ。どちらにせよ、すぐに収まらないならこの列車に術機関士は乗ってないな。」
「杜撰ね。事故が起きたらどうするの?」
「珍しいことじゃない。」
「私が行ってこようか?」
リニーは半ばそう決めて立ち上がる前に確認をとろとした。しかしロバートは「待ってくれ」と止める。
「これが敵の攻撃である場合のことを考えてる。」
「前みたいに敵の術士が?確かめるには先頭車両に乗り込むしかなくてよ。」
「やめておこう。あれをもう一度やるのはあんまり危ない。」
「列車を止めるでなく、暴走させるでもなく、『遅くする』とは如何。」
「そうだな。これが攻撃だとしたら、列車の速力を落とすのは下準備……。」
ロバートは荷物を片付け始める。
「アンジェラ、ライフル……」
「言われなくっても。」
足元のケエスは解錠されていて、中のライフルは弾倉に弾が入っている。
「敵が用意しているなら、正体が見えるまでそう遅くはないだろう……」
明らかに列車の走行音とは異なる音が方々から聴こえてきた。いくつもの音の重なり――まるで地鳴りのように――その一つ一つは蹄が土を蹴る音だった。列車の左右から響く、外を見た彼らは何十頭もの馬が、鞍の上に銃を持った男たちを乗せて列車と併走しているのを目にした。
「インディアンだ!」
赤褐色の肌に布を巻き、装飾を身に着けた戦士たちは徐々に列車に並ぼうとする。四人はすぐさま中央の通路に屈んで身を寄せた。
「インディアンの襲撃だと?大陸横断鉄道の建設作業中ならまだしも、今更こんなことがあるか?」
「馬で駆けて追いつこうなんて、現代の機関車なら到底無理でしょう……速力が落ちていることを知っていなければね。」
銃声。近くの壁を貫く。
「標的が何両目に居るか知っておるらしい。」
「これは間違いないな。」
ロバートは膝を浮かせて外を窺い、すぐに体勢を戻した。ざっと見回しただけでも二十騎を超えている。
「アンジェラ、擲弾筒はある?」
「あと数発。窓の外に身を乗り出して狙いをつけるから、その間は守っていてくれる?」
「やめておこう。機関車の速力を戻して置き去りにする。」
四つん這いで車両の前方に向かう。相変わらず蹄音は続いているが、標的を見失って銃声は止んでいる。ロバートは車両の扉に辿り着いてもたれかかった。
「デッキを渡る時が危険だ……」
「ねえ、何故彼らが襲ってくるの?敵は外国の組織か、少なくとも先住民ではないのに。」
リニーは問いかける。
「これまでも間に合わせの殺し屋を送ってきただろう。彼らは金で雇われたか、そんなところだろう。」
「じゃあ私たちが悪者だって騙されてるの?」
「……そうかもしれない。」
「話せばわかるかもしれない。」
そう言うなり、彼女は振り向いて立ち上がる。ロバートらが制止の声を上げるも、彼女は窓を開けて併走する騎馬隊を見下ろした。
平原のインディアンたちはライフルを持って手綱を繰っていた。服装は見慣れないが、リニーと同じ肌と目の色をしている。騙されて理不尽な襲撃に加担しているのなら、彼らも被害者に違いなかった。
一人でも、英語を話せる者がいればよいのだが……大きく息を吸い込む。
――お下げ髪の花飾りが宙に舞い、花弁の部分が視界に入る。頭の横の車体が軋み音を上げて穴を穿たれる。
列車の音もしない、馬の脚運びの一つ一つをしっかりと確認できる。ひどくゆっくり流れる景色の中で、こちらに向けられた銃口から硝煙が平原の空に立ち昇っている。
「……え?」
リニーは気が付けば客車の床に引き倒されていた。稲熊は彼女の肩を抱え、呆然と天井を見つめる視線の先に塞がった。
「馬鹿者!例え悪しき者の手に掛けられておろうと、同じ先住民の同胞であろうと、是は敵ぞ!武器を構えし者に相対する手は武器の他に無し!」
首を回せばロバートもアンジェラも近くで屈んでいた。彼の喝で酔いが醒めたみたいに、徐々にはっきりとしてくる頭でなぜこんな無謀なことをしたのかと後悔の念が湧き起こってきた。
「……ごめん。」
リニーは身体を起こして姿勢を正した。花飾りの片方は落としてしまった。耳の上のところは黒髪に触れる感触だけがある。
「機関車まで行って時化を直せばいいんだよね。」
「きっと前の車両は混乱状態だ。君が行かない方がいいだろう。」
「いいよ、いつもみたいに屋根に上がるから。」
「危険よ、何せこの敵の数だから。」
「見たところ、騎兵はこの車両にだけ張り付いておるようだが……。」
「大丈夫。」
力強く頷く。それでロバートも頷いた。
「援護する。」
中央辺りの車窓からロバートが顔を出した。戦士の一人はそれを見つけて敵発見の哮りを上げ、呼応するようにして各々がライフルを向け始める。向かい側でもアンジェラと稲熊が同じようにして敵の注意を引き付けた。
激しい銃撃が始まる。木製の車体は脆く、しょっちゅう弾丸が貫通する。それを防ぐために座面の一部を引っぺがして車体との間に挟んでやった。これでも貫かれる可能性はあるが。隙を見てリニーは前の車両との間にあるデッキから屋根によじ登って前方に向かった。その姿を見送って、三人は再び通路の中央に集まる。
「このまま注意を引き続けて、前に行かせるな。」
その時、視線の先で最後部の扉が開く。ライフルを構えた一人の戦士が入ってきて、物珍しそうに車内を見回す。ロバートはその隙に銃を向けて一発、敵をデッキに押し戻した。
「乗り移って来てるわ!」
「車両の最前で迎え討つ!稲熊、前方から乗り込んでくるのを止めてくれ!」
「承知。」
再び車両の最前に進み、一番前の座席の陰に身を隠した。背後では半開きの扉が開いてさらに敵が入ってくる。二人はそれを迎え討ち、稲熊は前の扉を開けて連結部のデッキを覗いた。こちらからも左右には数騎見える。
「この車両に乗り移らせて、リニーが機関車を再加速させてくれたら連結を切って車両ごと置いてけぼりにしてやろう。」
言うなりロバートは荷物を抱えて前の車両のデッキの上に投げ置いた。
敵は次々に乗り込んでくる。はじめの内は扉を開けた途端に狙い撃つことができたが、それも追いつかなくなった今では後方の座席に何人もが潜んでいる。抵抗の甲斐なく侵入者を押し返すには至らず、彼らは一歩、また一歩と座席を前に前に進んでくる。外では残る騎馬隊が併走を続けている。かなり肉薄し、窓のすぐ外から撃ち込んでくる。
「ロバート、前方からも迫っておるぞ!」
「分かってる!」
「ねえ、あなたあと何発持っていて?」
再装填の最中にアンジェラが尋ねた。
「これでおしまい。」
「そう。……こっちはもう撃ち尽くしてよ。」
「もっと早くに言ってくれ!」
列車はまだ加速を開始しない。迫る敵の最前線は車両の中央を越した。進撃を抑えるために威嚇の射撃などをしている余裕はなく、幾ばくの猶予もなかった。
「前の車両に移れ!」
合図と共に三人はデッキへ飛び出した。車両の扉を閉め、前の車両に飛び移る。外を走る敵はいなくなった代わりに、じきに目の前の扉が開いて車内から押し寄せてくる。
車両の外壁に並んで背中をつけ、それぞれが自分の武器を確認した。至近距離で擲弾筒は役に立たないから、拳銃に残った一発を除いて銃弾は底をついた。アンジェラのライフルは既に単なる鈍器と化している。
「ところで連結器ってどうやって外すの?」
「僕がやるよ。無防備になるから援護を頼む。」
言い終わるとロバートは車両の隙間に上半身をするりと突っ込んだ。二人が慌てて止めようとするも彼は「放せ」と言って聞かない。そうするうちにとうとう扉を破ってインディアンたちが現れ、車両のあちらとこちらで格闘が始まった。
視線のすぐ先で、瞬きの内に枕木が何本と通り過ぎていく。速力が低下しているとかは関係なく、ここで下に落ちればすなわち轢死する。目が回るような景色をなるべく見ないようにして、ロバートは片手で身体を支えながら腰まで身を乗り出して台車に手を伸ばした。連結器の解放装置は車体下部についており、本来ならば列車から降りて行うものなのでこうして乗ったまま操作することは想定されていない。先に空気ブレエキ管を外しておく。上は戦闘、下は車輪の音が響いて壮絶な場所に身を置いている。ロバートはやっと装置に手が届いてそれを引いた。だがそれは片手ではビクともしなくて、ついに彼は柵を掴んでいた手を離して両手でそれを引いた。
連結器が重い音をたて、まもなく頭上から光が差し込んだ。連結器のもう半分は少しずつ視界の隅に消えていった。ちょうど機関車が加速を開始したようで、列車は惰性で走る最後車をぐんぐん突き放していく。
ロバートは胸を撫で下ろした。上体を戻そうと足に力を入れたその時、すっかり忘れていた傷が痛んで思わず力が抜けてしまった。
「あ。」
ずるずると身体が下がっていく。連結器が顔の横を通り過ぎ、鼻の先に線路が……。
「危ない!」
ズボンを掴まれ、強い力でぐいと引き戻される。線路は遠ざかって彼の視界には青空が飛び込んだ。
客車はもう随分遠くで大平原に小さく浮かんでいる。インディアンたちは孤独な車両から虚しくこちらを見つめることしかできないでいた。
「落ちるまで身を乗り出すのはおやめなさい!」
「装置が思ったより固くて……」
「一時は危うかったが、難を逃れたな。」
線路に落ちかけたにも関わらず、帽子は逞しく頭の上に戴っている。まるで彼の頭に貼り付いているかのようだ。ロバートは顔を上げて両隣を見た。
「無事か?」
「うむ。」
「痛……」
ライフルを肩に掛けてアンジェラは腕を押さえていた。その服が赤く汚れていたので彼は驚いて声を上げた。
「平気よ、少し殴打を受けただけ。」
「だって、血が……!」
「これは返り血。誰かさんがたいそう刀を振り回していてよ。」
反対隣では稲熊が胡坐をかいて刀の血を拭き取っているところだった。黒い軍服で分かりにくいが、彼の服もよく汚れているらしかった。ロバートは安堵して向き直って、彼女の白い頬についた血を手で拭った――。
「あ。」
鮮血の代わりに、触れた部分に指の形に黒い跡がついた。彼が自分の手をよくよく見ると、機械油で真っ黒く汚れている。アンジェラもそれを見てみるみる顔を歪めた。
「なんてこと!最悪!」
すぐさまハンカチを出して頬を強く擦る。それでも拭いきれずに油が広がって頬の半分が薄黒くなっている。
「すまない、そういうつもりは……」
「ええそうでしょうね!」
いつもの調子ならここから激しくまくし立てただろうが、今日はきっぱり黙り込んでしまった。怒る気力すら今は残っていないのだ。彼女は壁に背中をつけ、足先をデッキの外に投げ出してぼんやりと座り込んだ。ロバートも衣服を汚さぬよう両の手に拳を結んだまま半ば放心して景色を眺めている。
そのまま眠りにでもついてしまいそうなものだったが、やがて彼は荷物をまとめて立ち上がった。
「戻ろう。ここは冷えるから。」
「左様。」
先ほどの襲撃など無かったかのように、一つ前の車両は平和そのものである。リニーの様子が気になって前に行こうかとしていたところ、向こう側の扉が開いて機関士の服装をした男とリニーが入ってきた。
「あんたたち、この娘の連れか?」
「ああそうだ……。!!」
男に片側の肩を支えられたリニーは力なく、身に着けたポンチョが赤黒く染まっていた。
三人はすぐに駆け寄った。
「前にも、敵がいて……しくじった。」
「しっかりしろ!」
「大丈夫、死ぬほどじゃない、から。」
「待ってろよ、駅まで飛ばすからな。」
機関士はもと来た道を戻っていく。
リニーの身体を見てみれば、左の肩から血が流れ出ていた。
「気を確かに、すぐに駅に着くから。」
「うん。ごめん。」
腕に抱かれて時々苦痛に表情を歪める少女を周りの乗客は騒然として見つめていた。
ネブラスカ州の東端、アイオワ州、ミズーリ州との州境はミズーリ川という大河によって隔たれている。南北に向かって蛇行する河道に沿った境界の、その中ほどに位置するネブラスカ第一の都市はオマハという。長らくプラット川に沿って進んだ路線はやがてこの都市に至る。オマハといえばユニオン・パシフィック鉄道の拠点にして大陸横断鉄道の東起点。この夜をもって四人は合衆国最初の大陸横断鉄道を踏破した。一九一一マイルに渡る途方もない路線は当初の鉄道会社の広告では四日とかからずに渡れるという話だった。現代では機関車技術の向上によりさらに早く渡り切ることができたはずだが……追手を退けつつ進んだ彼らの旅はそれよりも長い時間を要するものだった。
オマハという都市を特徴づける一つの重要な産品がある――食肉。街のほど近くにある工場では、小さい区画に区切られた柵の中に多数の家畜がひしめいているのを見ることができる。日々この街に集う家畜は人口をも凌駕する。豊かな平原で放牧された畜牛がオマハで加工され、ミズーリ川の向こう側、東部の消費地へと運送されていくのだ。こうした加工工場はかつてシカゴなど消費地に近い場所にあった。運送技術の発達によって新鮮な食肉をより早く輸送できるようになり、加工工場の所在地は次第に放牧場に近付いていった。
街の病院でリニーは目を覚ました。左肩に食い込んだ弾丸を抜き取る施術をしてから、落ち着いて一眠りしたのだった。記憶は鮮明に思い出される。今は肩を動かさぬようにと左腕ごと布で巻かれているから不自由の身である。不思議なことに今となってはそこまで痛むこともなくて、何かしら薬が効いているのかもしれない。
リニーは起き上がって周りを見た。ベッドから少し離れた場所にラムプが灯る他は明かりに乏しく薄暗い部屋だ。窓際の席に座って刀を磨いている男の他には、ここには誰もいないようだった。
「起きたか、調子は如何。」
「もう平気。……あの二人は?」
「弾薬を買い出しに行きて、しばらく経つ。」
「二人だけで大丈夫なの?」
彼はリニーをちらりと見た。
「それは用心のためか、又は彼らの気質の故か。」
「どちらかといえば、二つ目の方。」
二人は目を見合わせてくすりと笑った。
リニーは肩に手を触れてみる。まだ痛い。銃創の痛みがどれほど続くものかは知らないが、完治するのには時間がかかりそうだ。
「昼間はありがとう。」
「礼に及ばぬ。」
「でも、やっぱり駄目だった。」
稲熊は刀を磨く手を止めた。納刀して膝の上に置き、彼女の話に耳を傾ける。
「考え直したつもり、だったんだけど、彼らの中の一人を目の前にして、判断が鈍った。この怪我はそのせい。」
「致し方あるまい。某がかつて故郷の朋友に対峙せし時も、主と同じようなものだった。」
「故郷の?……何があったの。」
身体を回そうとしたら刺すように肩に痛みが走り、稲熊が安静にするよう促した。
「日本で内乱があってな……軍人である某は反乱軍を制圧した――彼らは故郷の藩士だった。実家からは反乱軍に加わるようにと達しがあったが、それを無視したどころか、敵として迎え討った。これに依りて某と岡田家との縁は切れておる。」
「そんなことが。大変だっただろうね。」
「今は昔のこと。」
「それってシヴィル・ウォーみたいな?」
彼は腕を組んだ。それは分からなかった。
「寡聞にしてかの戦のことは存ぜぬが、ある面ではそうであるし、またある面では違うであろう。」
「グレイヒルさん、ロバートの叔父さんは言っていた。自らは英雄と持て囃されているけど、その実は合衆国民の同胞を傷つけてきたのだって。」
「何時の世も内乱とは斯くあるものか。」
稲熊はベルトに紐を結び付けて、刀を提げる。テーブルの上で照るラムプの光の玉を漆黒の鞘は細長い身に映す。彼は立ち上がって柄に手を掛け、抜刀して具合を確かめた。抜刀は戦いの開幕に関わり、すなわち一瞬で生死を分ける要素でもある。奥の壁に影を落としながら輝きを放つ刀身は、新月の後から三日目の夜に見る月にも似ている。
彼はまた席に戻って、今はその手に何も持たずに背筋を正している。
「故郷の家族を、想ったりはしない?」
彼女の質問に少し黙り込んで、そうして「する」と答えた。
「されど想うのみぞ。例え家族が過去を水に流そうとも、己が罪を赦すまじと、誓って家の敷居は跨がじと、そう心に決めておったが――。」
逆説に続く言葉をリニーは待った。
「いずれは交わることもあろう。元より某が誓って会うまじと決めておったのは骨を埋める心づもりで海の向こうの外国に渡ったが故なのだ。ところが近頃は考えが変わった。合衆国で得た知見と意志とを日本に持ち帰るが我が使命と心得た。ならば国に帰りてもう一度故郷の土を踏むことがないと誰が言えようか。――某はかつて死に損ないて、故郷を裏切って朝敵を滅ぼし、今はここに居直っておる。なればこそ、この道を進み続けるが道理。」
「よく分からないや。」
「所詮聞くに及ばぬ戯れ言よ。」
「つまり、稲熊にもやることがあるんだよね。」
彼は頷いた。
「じゃあ私と一緒だ。」
「主は同胞を救うのであったな。」
「それだけじゃない、私たちと、この国の先住民が皆生きられる道を開拓しようと思う。」
彼女と目を合わせ、稲熊は目を細めた。
「良きまなざしをするようになったな。会った頃はロバートに付き従う妹娘のようであったが。」
「そう、かな。」
部屋の扉が開いて賑やかな二人が舞い戻ってきた。
「戻ったぞ。リニー、お目覚めかい。」
「調子はいかがかしら。」
「平気。明日には出られるよ。」
「いや、それなんだが……明日はこの街に留まる。」
荷物をばらばらとあちこちに置きながら身軽になった二人は空いている席にどっかり座った。
「私のことなら平気だよ。」
「それはよかった。だけどな、弾薬買うついでにアンジェラのライフルを点検に出してきたから、それが明日までかかるんだ。」
見れば荷物の中に彼女の臙脂色のライフルケエスは無かった。
「使って、しまい込んでを繰り返していたから、もう長いこと部品の交換をしていなくてよ。」
「得物の手入れは基本。」
「岡田先生のお言葉だ。」
「暇さえあれば刀を磨いている男は言うことが違うわね。」
その言葉に稲熊はむしろ得意気になった。
「それに、明日はワシントンで公聴会があるだろう。あれを前に叔父さんに追って連絡を入れておいたんだ。政府の結論は後で知ることになろうが、せめて明日くらいは列車で暴れずに静かにしておこうかと思ってね。」
「電報には何て送ったの?」
「一にも二にも自信を崩しちゃ駄目だ、多少調子のいいことを書いておいた。」
言葉通りに彼は調子づいてにこにこしている。これまでの付き合いからやけに調子のいい時のロバートは要注意だと三人は知っていた。
「仕事柄、他人が送る電報を読む機会は多かった。単語課金制の仕様上、料金を抑えるために電文は短いものになるが、大切なのは『含意』だと僕は気付いたのさ。」
凡そ自らの生命が懸かっているとは思えない奔放さに呆れでもするべきところ、これまでの付き合いからロバートの自信には裏付けがないわけでないのを三人は知っていた。
「まあ、どうぞご勝手に。」
アンジェラは肩をすくめる。
「話は変わるが、主ら、飯はどうした。某は腹の虫が泣いておる。」
「ああ、それがさ……」
ロバートはテーブルに放ってあった包みを持ち上げた。大きな塊で、四角い。
「まさか、パンだけか?」
「それがパンでなくてよ。」
包み紙を開いて、脂取り紙の中から出てきたのは幾重にも折り重なったステーキであった。一つの大きな塊の如く積み上がり、まだ温かい。
「この街、どこ行ってもステーキしかなくて。」
「怪我人に肉の塊をあげるのかって、私は言ったのよ!」
「仕方がない、選択肢が無かったんだ。」
「某はやぶさかではない。リニー嬢、怪我には肉こそ一番の妙薬。」
「嘘……でしょう。」
ベッドに座って彼女は少し引きつった笑いを見せていた。
その日の道路は交通が多く、個人の馬車が渋滞を起こすほどに路上に溢れていた。それも当然のことで、彼らが目指している場所は揃いも揃って同じなのだから。ワシントンの中心部にある公会堂が未だかつてない規模の公聴会に使用される。
予定より遅れて会場に到達したワトキンスは正面入口でごった返す人の群れを見た。我先にと群集を抜け出そうとする参加者たちは回転式のガラス扉で目詰まりを起こし、外側ではそれに加えて会場に入ること叶わなかった記者たちが自分勝手に動き回っては、参加者に声をかけて取材を申し込む。予定開始時刻は三十分後に迫っているが、これでは遅らせざるを得ない。
正面入口の脇をすり抜けてワトキンスは公会堂の中に入り、上階へ上がった。廊下に並んだ小部屋の一つでは大統領が当の昔に会場に到着していて、他の仕事をしながら会場が整うのを待っていた。
ワトキンスが入室すると、クリーヴランドは手元の資料から視線を上げて軽く手を挙げた。
「遅ればせながらただいま参上しました。」
「や、仕方ないね、これは。開始時刻はやはり遅らせようと思う。正直なところ、急な用件にも関わらずこれだけの人数が集まったのはあまり例のないことだ。その意味が分かるね。」
「それだけ世間の注目を集めているということでしょう。」
「そうだね。」
クリーヴランドは資料を片付けて机の隅にあるコーヒーカップを手に取った。
「将軍、あなたには最初に発言の時間を与えるからね、心してかかりなさい。それが甥の運命を分かつかもしれないのだよ。」
「現時点で政府の対応は想定されているのですか。」
彼はカップを口につけてから、髭の下の唇をすぼめた。
「私はあくまで世論と共にあるよ。」
公聴会を行えど、最終的に政府の判断を決めるのは目の前に座る大統領の他にいない。彼は言葉の陰で既に腹を決めているのだろうか、それはどちらに転ぶのだろうか、ワトキンスにはまだ分からない。
「ところで、君の甥からまた電報が届いたそうだね。」
「はい。」
「どこから?」
「オマハです。」
「オマハか。やはり彼らは東に向かっているんだね。それで何て?」
「『スベテ テイコクドオリ』と。それ以外にはありません。」
ワトキンスは懐から電報を取り出してそれを開く。オマハの電信局から発せられた、ロバート・グレイヒルによる短い言葉が記されていた。
「『全て定刻通り』か。私には詳しいことは理解しかねるが、それはつまり彼は無事であると考えてよいのかな。そしてもう一つ、彼は当てもなく放浪を続けているわけではないということだ。」
「ええ、それは間違いないでしょう。」
「何か彼には希望があるんだね。今はそれに向かって進み続けているように、私には思える。……ロバート・グレイヒル、彼は私がはじめに思っていたより胆力のある男だ。そういうところは将軍に似てかね。」
「いいえ……小生が知らなかっただけで、甥は元々そのような気質だったのかもしれません。」
ワトキンスの背後で扉が開いた。若い娘――ロバートくらいの年齢のが、「クリーヴおじさん!」と声を上げながら入ってきた。
「やあフランク、よく来たね。」
クリーヴランドは立ち上がって女性を自らの腕の中に迎えた。
「大変だったろう、ここに来るまで。」
「ええとっても。外はまだまだ落ち着く気配がございませんの。」
女性は彼から離れて、すぐそばに立っていたワトキンスと顔を合わせた。見れば、彼女は正装をした品の良い女性で、いかにも名のある方の娘という風情である。
「申し訳ありません、お邪魔してしまって。」
「いえ。」
合衆国の大統領を親しげに「おじさん」と呼ぶところも、何か縁の深い娘さんらしい。
話は中断されたが、それ以上の用件がなかったのでワトキンスはその場を女性に譲ろうとした。するとクリーヴランドは彼を呼び止めた。彼女を隣に立たせる。
「戻る前に紹介させてくれ。彼女はフランシス・フォルサム。亡き親友の娘で、今では私が後見人を務めている。フランク、この方がグレイヒル将軍だよ。」
彼は一度被り直した帽子を取ってフランシスと握手を交わした。
「初めまして、グレイヒル将軍。お噂は存じ上げておりますわ。どうぞよろしくお願いします。」
「よろしく。」
彼女は朗らかな笑顔を見せた。
フランシスはクリーヴランドと親交が深かったある術士の令嬢である。その男は若くして妻子を残し天国へ旅立ってしまったので、クリーヴランドが後見人となって生活を助けてやっていた。クリーヴランドはフランシスが赤ん坊のことから彼女を知っており、自分の娘のように溺愛していた。フランシスもまた幼い頃から彼を「クリーヴおじさん」と呼んでたいそう慕っているのだった。
「フランクは今日の会に参加したいと言うので、私が特別に席を取っておいたんだよ。フランク、静かに聞いていなさいね。」
「はいおじさん。」と明るい返事をした。随分と社会問題に熱心な娘さんなのかとワトキンスは思った。
「将軍はグレイヒル技士の叔父様でいらっしゃいますのよね。先日の表明は感銘を受けました。わたくしは将軍を応援させていただきますわ。」
その言葉には驚かされた。術士は皆ロバートの研究に反感を抱いているものと思い込んでいた。実際はごくわずかだとしても、彼に共感を示す術士もいるのだ。
「将軍は彼を大切になさっていらっしゃるのでしょう。そのお心が伝わりましたわ。」
「ご理解に感謝申し上げます。」
「お尋ねしますが、グレイヒル技士はおいくつですか。」
「確か、二十五ばかりかと。」
「それでしたらわたくしの四つ上ですわね。」
フランシスは口を覆って笑顔を見せた。
「健闘をお祈り申し上げます、将軍。それではまた後ほど。」
そう言って彼女は部屋を後にした。別れ際にクリーヴランドに手を振るのを、彼は笑顔で応えた。
「いずれあなたに紹介しようと思っていてね。あの子を見ていると、将軍、あなたのことも全くの他所事には思えなくなってくるんだ。」
ワトキンスもまた、親しげな二人を見て自分が最後に甥と話した時のことが思い出されるのだった。
公会堂の外観は白壁に、階段と溝の彫り込まれた白柱を正面に構えたギリシア風の古典様式で、これは合衆国議会議事堂にも用いられた建国当時の流行を下地にしている。一方で内部の会議場は高いドオムを持ち、四角い室の三方は雛壇になって長机と総数数百にも上るような座席が据え付けられている。奥の一方は会議を取り仕切る者の席や登壇して演説する時に使う壇が設けられている。バロックの様式を感じさせ、オペラか何かを開けそうな雰囲気がある。広い部屋の中央に立つだけでも圧倒されるようだが、今はその座席のほとんどが埋まっているのだから壮観である。更なることには、その顔ぶれを見れば一度は写真で目にしたことがあるような各界の大物たちばかりで、これは合衆国の偉大な人々を集めた博覧会である。政治家、実業家、銀行家、教授、術士、将校……それぞれの区画でまとまって席に着く。最後に我らが大統領が議場に姿を現し、前方の中央を陣取った。
クリーヴランドは全体に届くように一段と声を張り上げた。
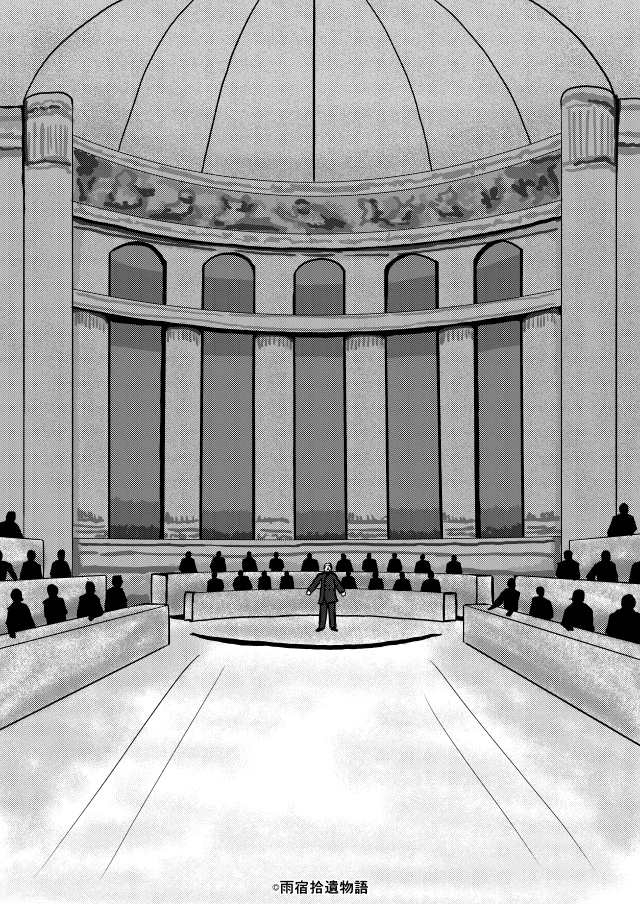
「本日お集りの皆さん、私は合衆国の大統領グロヴァ―・クリーヴランドです。こうしてこの国を愛し、この国で生きる偉大な皆さんがこの場に会したことを嬉しく思います。さて、ご存じの通り皆さんはある一つの共通した目的のためにここに集っています。それは合衆国を騒がせるある一人の技士とその研究についてでしょう。話を始める前に、一つの約束事を設けさせていただきたい。私は何よりも正義と真実を愛し、嘘と不正を憎む、それは誰にも劣らないと自負しています。願わくは、この席に着いている間は皆さんも神に誓ってそうであってもらいたい。もしも私の願いに賛同いただけない方がいらっしゃるのならば、今しばらく時間を取りましょう、その間に退席してよろしい。分かりましたね。」
彼は黙り込んだ。会場は静まり返り、立ち上がる者は誰もいない。やがて彼は頷いて静寂を破った。
「よろしいでしょう。では始めましょう。」
何人も並んだ書記が一斉にペンを執る。
「先ほども申し上げた通り、公聴会の議題は『技士ロバート・グレイヒルに対して合衆国政府は如何なる対応をするべきか』ということです。はじめに経緯を説明しましょう。サクラメントの電信技士ロバート・グレイヒルは某社の依頼を受けて電気事業の実用化に向けて同社から研究資金を受け取りました。知っての通り、送電技術は発展の途上にあり時化の影響を大きく受けるため、これを軽減することが依頼の目的でした。果たして彼はアリゾナの地で依頼を達成しうる技術の開発に成功した――それは時化そのものを抑える技術だと報じられた。ところがこれが『今後一切、術と時化の発生に関する研究を行わない』と誓ったヴィエナ宣言に反するとの指摘がなされ、合衆国、及び世界は懸念を示しています。ここまで騒動が大きくなったのは、この技術が時化と同時に術士の術を封じるものだとの報道がなされたからでしょう。批判を受けて彼は公の場に姿を現したが、十分な説明は成されず今に至ります。あらましの説明はここまでにして、現在の彼の状況について、彼の叔父であり後見人である、我らが『名将』ワトキンス・グレイヒル大佐にご説明願います。それでは将軍、よろしく。」
ワトキンスはその場に立ち上がり、事前に用意した走り書きに目を通しながら語った。
会見から数日後ロバートの家は火災で焼失し、彼は行方不明になる。しかしその後各地でそれらしい存在が確認され、彼が研究の一切を持って三人の仲間と共に東に向かう鉄道に乗っていることが分かった。ソルトレイクシティ、オマハから電報も届き、現在はネブラスカかその周辺にいると思われる。彼は正体不明の追手に何度か襲撃されている。それはおそらく彼の持つ研究が理由であろう。
「その上で、吾輩は即刻ロバートの身柄と彼の研究の保護を主張する。現在、彼の存在は外交関係を通じて安全保障上の問題に発展しており、合衆国として早期に彼を適切な保護下に置くことが求められている。また、研究の内容については彼以外誰も分かっておらず、宣言に違反するかは精査の余地ありと考える。以上がロバートの現況と自論であります。」
「ご苦労。確かに政府は既に各国から再三の懸念を表明されており、いくつかは非難声明も受け取っている。何にせよ彼を放置することは得策ではないね。それでは意見のある方は挙手をして、指名を受けたら立ち上がってください。」
呼びかけを受けて、ぱらぱらと手が挙がり始める。その中でもクリーヴランドが言い終わる前に最も早く手を挙げた、顎鬚を耳まで蓄えた男に指名がなされた。術士席である。
「大変有意義なお話をありがとうございました、『叔父上』。あなたの仰る『保護』が何を指すか私には理解しかねますが、対応なさるなら最も手っ取り早いものがある、それは技士を逮捕することです。というより、州警察はなぜそうしてこなかったのか不思議でなりませんが。」
周りの者がしきりに頷く。ワトキンスはすぐに手を挙げた。
「吾輩はあなたの『叔父上』ではないが……では問いましょう、ロバートは如何なる罪を犯しましたか。ヴィエナ宣言は技士の倫理規定であって、法律でも憲法でもない。」
「研究そのものでなくても、要は身柄を押さえられればよいでしょう。実際、彼は逃亡を続けていますし、その間に起こした列車での事件は十分逮捕理由になる。」
「逃亡ではない。事件の詳細は不明ですが、追手に襲われたのならば正当防衛だ。」
最初に発言した術士の後ろの列で手を挙げた男が発言した。
「技士の罪が分からないと仰せなら、お教えしましょう――国家反逆罪です。彼は社会に大きな不安を与え、合衆国を外交上危うい立場に追いやった。これは我々が二十年間築き上げてきた平和に対する挑戦だ。これがどうして罪でないと言えるか。将軍、かの戦乱を戦い抜いたあなたならお分かりでしょう。悲劇を繰り返さぬためにも我々は断固たる意志を持って恐れ知らずの『黒』技士に対峙せねばならない!」
一部から拍手が沸き起こる。演説じみた語り口にワトキンスは顔をしかめた。
反対側の雛壇で男が手を挙げた。リーランド・スタンフォード――セントラル・パシフィック鉄道の社長で、上院議員を務めている。
「言わせていただきましょう、私の鉄道会社は、グレイヒルの乗る列車で起きた事件で多大な損害を被ったことをお忘れなく。それからここにお集りの皆さんの中に、騒動に関連する一連の狂乱相場で大損した方がどれほどいらっしゃいますか。」
多くの者が頷いた。ここ最近の株式市場は一言で言って「グレイヒル相場」だった。彼の発言によって暴落した市場では大きな損害を被った投資家も多い。口々に不平が漏れ出す。
他の術士はロバートの仲間に対して異を唱える。
「技士が連れている者共もけしからん、アジア人やインディアンなどを連れて、これではならず者を引き連れた叛逆以外の何物でもない。あくまで厳しい対応を求める。……それよりも理解に苦しむのは、術士の娘が彼に与していることだがな。」
これに対してクリーヴランドは眉を顰める。
「白人だとか白人じゃないとかに拘った物言いを私は好かないがね。彼と共に行動する術士、アンジェラ・エマソン嬢については、その御父上がこの場にいらっしゃる。エマソン氏、何か意見があればどうぞ。」
卿は術士席の端に近い位置に座っていた。身構えてはいたが、話題に上がって名指しされると彼は狼狽えた。
「ご紹介の通り、あれは我が娘ですが、私は長らく家を離れておりますので詳しいことは分かりません。このような行動に出るのは無論初めてのことです。娘は決して不道徳な者ではありません、それだけはご理解ください。」
「『不道徳でない』と。」
「技士に篭絡されたとか、そんなところではないのか。」
「『駆け落ち旅行』に合衆国民全体を巻き込むのはやめてほしいものだ。」
議論は紛糾し、勝手な発言がいくつも見られるようになってきたので、一度静粛を取り戻す必要があった。
「率直な意見を述べるのは結構だが、最初の約束事を忘れてはいないね。みなさんはとかくグレイヒル技士を拘束することばかり考えているようだが、他の道を考えたことはないのか。確かに彼はヴィエナ宣言を破って秩序を乱したのかもしれない。だが将軍の言う通りこれは倫理規定であって、破ることで罰があるわけではないね。宣言が出されたのは一七七六年、もう百年以上昔で、当時生きていた者はもうどこにもいない。ところで、この年はもう一つ大事な宣言が出された年である――この国の独立宣言だ。ここではすべての人民が自由な権利を持つ存在であると述べている。件の技士がアメリカ人ならば、彼はここにいる者と同様に権利を持っているはずだ。――一方は古い技士の共同宣言、もう一方は我々アメリカ人に根付く崇高な精神の宣言、我々はどちらを尊ぶべきかね。若き技士を謗る前に、一人一人の胸の内にある正義に問いかけてみてくれ。」
議場は再び静まり返った。不平を述べていた者たちを一挙に黙らせるような重みがクリーヴランドの発する一言一句にはあった。
改めて最初に発言したのはやはりワトキンスだった。彼は限りなく敵ばかりのこの会議の厳しさを痛感していて、彼の主張を認められるには別な論点を見つけなければならないと考えた。
「お忘れかもしれないが、ロバートは素性の分からない追手の襲撃を受けている。それらの目的が彼の研究にあることはまず間違いないだろう。敵の目的が達されてしまった時のことをお考えになってはいかがか。何とも知れぬ者に重大な研究が持ち去られてしまう。……目下、ロバートは知識を自らの記憶と手持ちの研究資料とに留めている。それが失われることを防ぐために、政府としての対応が不可欠であることは、誰しも異論はないだろう。」
「それは将軍の言う通りだね。だが、外交部としてはそれが諸外国との関係に悪い影響を及ぼすことを懸念している。そうだね、外務大臣。」
クリーヴランドは横を見た。近くに座る男が「その通り」と頷く。
「それを差し置いても保護すべき理由があれば、その時は躊躇いますまいな、大統領。」
「全くその通り。皆さんには是非とも国益の観点に立ってこれを議論していただきたい。」
ジョージ・ウエスティングハウス、初めにロバートに仕事を依頼した男が発言する。
「私はもとより彼の研究を完全に破棄させることを完全に支持しているわけではないのです。それが時化を防ぐ非常に有益なものであるならば、彼のことを研究成果も含めて保護することもやぶさかではないと思う。」
すぐに術士席から反論が上がる。
「あなたは自分が何を仰っているか分かっていてか。大方、自分が投資した金が無駄になるのが我慢ならないといったところだろう。」
「いいや、これは私も賛同する。」
ウエスティングハウスに共鳴したのはジョン・ピアポント・モルガン、合衆国を牛耳る巨大な銀行の経営者。
「この国は術士が不足している。工場で、鉄道で日々発生する時化によってどれだけの事故が発生し、どれだけの生産力が失われているか。それを勘定した者は未だかつてありませんが……とにかく膨大だ。それだけではないぞ、術士の確保に目途が立たなかったために断念された新規工場がどれだけあったか、『生まれるはずだった』生産力までも失っているのだ。これを一挙に解決できるのならば、旧大陸の国々と多少諍いを起こすことが何だというのか。」
「到底受け容れられぬ。どうにもあなた方平民出身の実業家は我々術士のことを金食い虫として排斥したがっているきらいがある。『アメリカの夢』だとか仰るのは結構だが、機械が誰のおかげで動いているかはどうぞお忘れなく。」
大変意地悪な物言いをつけるのはこれまた術士席の男である。これですっかり雛壇のあちらとこちらで対立が起こってしまって、様々な発言が飛び交った。
「機械を動かす最重要職務に就いていると自負をお持ちなら、どうぞ我々鉄道会社にもっとご応募いただきたい。蒸気機関車の術機関士という輝かしい職務が待っていますよ。ところがあなた方ときたら機関士の仕事を汚いだの臭いだの言って手伝おうとはしないじゃありませんか。その実、運転台の横でふんぞり返って座っているだけなのに。」
合衆国の鉄道を築いた「鉄道王」ことコーネリアス・ヴァンダービルトの嫡孫であるコーネリアス二世は語る。
「それは鉄道会社が給料を出し渋っているだけでしょう。」
「そのように足元を見た態度を取っているから経営者たちが敬遠するのではないか。」
「何にせよ術士の排除は倫理に反した行為だ。魔女狩りの時代に回帰するか、そうでなくても我々は二十余年前に学んだではないか。」
話題が次第に逸れていき、すぐに勝手な発言が増えるので、度々仕切り直す場面が出てきた。
マイアー・グッゲンハイム、各地の鉱山を開発する「鉱山王」が重々しく手を挙げた。
「ロバート・グレイヒルの研究を保護するか否かは、それによって受ける『恩恵』の大きさによる。それによっては支持を考えないこともないがね。」
同じような発言がいくつかあって、ワトキンスは反論した。
「先ほどからあなた方はそればかりを気にしている、ロバートの発見した技術によって金儲けができるかということだ。それではもし、本件であなた方がさしたる利益を得られないと分かれば『彼は助けるに値しない人間だ』と仰るか。」
「――ええ、そうでしょうね。」
一人の男が答えた。ジェイ・グールド、鉄道会社と電信会社の支配によって資産を築き上げた。
「各国との関係が冷え込めば貿易会社が打撃を受け、ほとんどの業界がそのあおりを受ける。損失だったら、ここにいる投資家の多くは既に被っているんですよ。そもそもが宣言破りの『黒』技士を、さらなる損失を生み出してまで助ける理由がありますか。」
「何だと……」
「ロバート・グレイヒルの意志によって再び合衆国が引き裂かれる、それだけじゃない、反感を抱いた各国が参戦しましょう。聡明な将軍、それともあなたが国内の混乱と外国の軍隊とを一手に引き受けて勝利を勝ち取っていただけるのですか?」
「それ以上語るなよ。」
ワトキンスは遂に手を挙げずして立ち上がった。もう辛抱堪らなかった。
「あなた方は皆自己保身と金儲けのことばかり考えている。終いには先の大戦まで持ち出して我が甥を貶める始末。シヴィル・ウォーは誰か一人の意志によって火が付いたものではない。溜まり続けた不均衡なこの国の歪みが引き起こしたんだ。吾輩は鮮明に覚えている、混乱を極める社会の中で誰もが誰かを謗っていたのを、ちょうどあなた方が我が甥に対して心無い言葉を浴びせかけるようにだ。今再び歪みは増している、欲に目が眩んだ悪徳な心を持つ者たちによって。金儲けが正義だと信じて疑わず、その影で広がり続けた格差が社会を歪ませているのだ。邁進し続ける今日の合衆国を誰かは『黄金』と呼んだ、だがそれは一枚皮をめくればくすんだ石ころの表面が顔を出すような、金ぴかの金メッキだった。――明日、二度目のシヴィル・ウォーが起ころうと吾輩は驚かない。そしてそれは我が甥が、誰か一人が引き起こすのではない。この歪んだ社会を作り上げたあなた方全員によって引き起こされるのだ。我々が、シヴィル・ウォーの首謀者なのだ。」
力強い叫びはドオムの天井に虚しく響いた。誰も真剣に受け止めてはいないことをワトキンスは知っていた。長年『名将』と称えられ、その称賛の陰で抱いていた心の声がついに飛び出してとめどなくこの議場に木霊した。
「もういいだろう。」
クリーヴランドは低い調子で言った。ワトキンスはそれで我に返り、へなへなと座り込んだ。
「午前の会議はこれで終了する。」
その宣言で一時の解散が言い渡された。
昼休みにワトキンスは再び大統領の小部屋に呼び出された。朝と同じように座っているクリーヴランドがいて、その隣ではフランシスが彼の机を覗き込んでいた。ワトキンスが入室すると二人は揃って顔を上げた。
「や、本来は休憩の時間だから、どうかここでゆっくりしていくといい。といっても大統領を前に緊張するなとは難しいかもしれないね。どうかここにいるフランクを見習ってここはひとつ。」
フランシスはにっこりと微笑んだ。本当にクリーヴランドと親しげな様子である。ワトキンスは彼の机の前に立った。
「先刻は失礼を致しました。」
「そう思っているのならそれ以上言う必要はないね。将軍、はやる気持ちは分かるが、焦ってはいけない。」
「はい。」
「お気を落とさないで、わたくしは将軍の言葉に胸がすく思いがしましたわ。近頃の術士は金欲が強くていけませんわ、術士とは本来節制と自然への愛着を是として信仰に生きるものですのよ。たかだか数十年のうちにそれを忘れてしまったのだわ。」
「またまた、フランクはみいちゃんはあちゃんなんだから。」
クリーヴランドは彼女の華奢な肩を覆い隠すほどの手でぽんぽん叩いた。
「反省はしていますが、依然考えは変わっておりません。」
ワトキンスは一つしかない窓の遠くを見据えた。ここからはワシントンを象徴する広い緑地帯がよく見える。
「これは、リンカーン大統領が遺した負の遺産、シヴィル・ウォーの後腐れです。」
「ほう。」
「シヴィル・ウォーを乗り越えて国民の心を再統一するのに彼は経済成長という手段を選んだ。誰のところにも富が巡るようにすれば社会の対立は減ると考えた。実際、当時はそれでよかった。だが二十年という時を経て状況は変わった。巡る富に不均衡が生じ、開戦以前よりも格差は拡大し、それは広がる一方です。リンカーン大統領の策がまた新たな内乱の種となった。……やはり今日の合衆国はいつ内乱を迎えても不思議ではない。」
「それだけではないよ。もう一度戦火が巻き起こるのを恐れ、我々はシヴィル・ウォーという古傷をひた隠しにしてきた。向き合うことを恐れ続けていたために、合衆国は過去を清算することができなかった。だからこそかつての大火は小さく、でも確かに不気味な燻りを見せている。」
「……わたくしは当時幼くてあまり多くを覚えていませんの。それは厳しい戦いだったのでしょうね。」
「いかにも。とても厳しかった。小生は国民に銃口を向けた、それが合衆国のためと信じて。ですがこの心から躊躇いが消えたことは片時もなかった――それは今でも。大統領という偉大な指導者が無ければ、小生は戦い抜くこと叶わなかったやもしれません。我が甥は今、たった一人で世界と戦っている。」
「将軍が共にあるではありませんこと。グレイヒル技士はきっと叔父上を頼りにしておりますわ。」
フランシスは温かく、人情味のある女性だった。クリーヴランドが溺愛するのも頷けるようだ。
昼食の誘いを断ってワトキンスは部屋を後にした。
午後の会議の始まりが迫る頃、ワトキンスは議場に戻る道すがら廊下でエマソン卿を見た。卿は廊下に立ち尽くして何をするでもなくぼんやりとして、彼が近付くのを見とめて手を挙げた。
二人は挨拶をしたきり黙ってしまった。冷静に言葉を捻り出そうとしてもそれらしいものが出てこなかったのだ。お互いにこの会議が厳しいものであることを痛感していた。
「『駆け落ち旅行』もあながち間違いでないのかもしれん。」
とうとう卿はそんなことを呟いたので、ワトキンスはますます言葉が出なくなった。
「思い返すと辻褄が合うこともあるのです。」
「まさか。」
「あれはロバート君のことを愛していたかもしれません。」
「しかし、あれは幼い頃の話ではありませんか。」
「全くその通りなのですがね。」
「しかも甥は平民です。」
「そう、そうなんですがね、不可解な事なんだが。」
ワトキンスはよく分からなかった。
「……甥はあなたのことを尊敬しています。あなたに受けた恩を忘れたことはありません。」
「ああ、分かっている。」
「どうか、彼の行く末に光を灯してください。」
間もなく会議が再開される。二人は議場に入ってそれぞれの席に向かった。
午後一番の議場にクリーヴランドの声が響きわたる。
「皆さんが席に戻ったところで、再開致しましょう。」
議席の顔ぶれは変わっていない。午前は激しい議論を交わしていた者たちも平静を取り戻している。それがいつまで続くものとは分からぬが。
「技士ロバート・グレイヒルに対して国益の観点に立って我々が取れる対応とは何かということだが……確か皆さんの中のある者は技士と研究を保護することもやぶさかではないという話だったね。その続きから始めて良いだろう。繰り返しになるが、我々はいかなる時も正義と真実を愛し、嘘と不正を憎まなければならない。その上で正当な意見がある者は手を挙げてください。」
まもなく一人が手を挙げる。
「先に申し上げておきたいことがあるんですがね。それも技士の端くれとして。」
トーマス・アルバ・エジソン、彼は成功した実業家でありながら、自らも技士として多数の発明を行ってきた男で、合衆国の技士界の権威である。
「術士の皆さんには反感を抱かれるやもしれませんが、ご容赦ください。それというのは、グレイヒルの研究によって現在、技士の世界に大きな風穴が空いているということです。ヴィエナ宣言が我々にとって重要な倫理規範であることは確かですが、それはそれとして我々は今日まで時化を止める術を知らなかった、だが彼はそれを見つけました。世界中の技士が百年以上開けることの叶わなかった秘密の扉が遂に開かれたのです。扉の向こうで見たものをグレイヒルは未だ公開していませんが、その手掛かりはいくつも残した。各国の技士はそれを頼りに彼の後を必死で追おうとするはずです。それが宣言違反だと揶揄されようが、世間の明るみに出ないように『こっそり』研究しようとする者は後を絶たないでしょう。つまりどういうことか、ここで彼一人を粛清しようとも、第二第三のロバート・グレイヒルはすぐに現れるだろうということです。」
「――時間は巻き戻せない、術士の凋落はいずれ来たる定めです。残酷なことですが、どうかご理解ください。」
術士の席が一斉にどよめく。ある術士は叫び出した。
「ならばこそ後追いを出さないためにグレイヒルは徹底的に弾圧されなければならない!」
「正義においてそれは許されないね。」
クリーヴランドは言葉を遮る。
「合衆国民として、彼の思想の自由は保障されている。それを侵害することは許さない。」
「……話を続けてもよろしいですか。」
エジソンは語る。
「仮にグレイヒルに処罰を与えたとして、問題は第二のグレイヒルが現れるのは合衆国とは限らないということです。その国は彼の発見を国家として秘匿するでしょう。こうなれば我々が闇に葬った技術がみすみす他国に渡ったことになる。――私ははっきりと申し上げましょう、グレイヒルは保護され、彼の研究は合衆国の財産とされるべきです。」
「ふむ、筋は通っているようだね。何か意見のある者は。」
議場はまだざわついている。ざわめきの中でラッセル・セイジが手を挙げた。ニューヨークの実業家で数々の鉄道を支配している、ジェイ・グールドと親交のある人物である。
「私もエジソン氏の意見には共感しますがね、一つ疑問に思うのです。――果たして彼の研究は保護されなければならないほど価値あるものなのか?巷で言われているほど重大なものなのでしょうか。将軍はご存知ないのですか。」
「甥は新聞に書いてあることが事実だと――つまり時化と術を止められることは正しいと、しかしそれ以上詳しくは聞き及んでいない。」
「そこが問題なのですよ。時化を止めるにしたって、どの程度止めるのか。これで彼を保護したとして、研究の成果がおちゃらけた可愛いものでしかなかったら、経済的にも外交的にも損ばかりすることになりませんか。」
「ですから研究内容については精査の余地ありと、小生は最初に申し上げましたが。」
「確かにその通りだね。」
クリーヴランドも腕を組んで頷いた。
「皆さんは散々彼のことを『黒』技士だとか、金儲けになるとか言ってきましたが、その実研究の具体的な成果については分からない。それ次第では各々の判断も変わってくるでしょう。我々は彼を知らなさすぎるね。」
「それなら簡単なことです、調べればいい。」
ジェームズ・J・ヒル――北部に長大な鉄道路線を持つ経営者は言う。
「最終的な対応を決定する前に、彼の技術が如何ほどのものか調べればよいのです。資本家の皆さんは支持を表明するにしても、彼の研究が実用に足るものかどうかが気掛かりなのでしょう。そして術士の皆さんは彼の研究によって本当に術が封じられてしまうのかを知りたいはずだ。だからこうしましょう、どこかでグレイヒルの持つ技術を確かめるための実証実験を行う。その結果によって皆さんと政府は対応を決定すればよい。いかがですか。――ちなみに私は彼の技術が鉄道事故を防ぐために役に立つならば喜んで彼の保護に協力しましょう。」
「よろしい!このアンドリュー・カーネギー、その提案に賛同しますぞ。」
カーネギーは合衆国で最大の生産を誇るカーネギー鉄鋼会社の経営者であり、鉄鋼の国を作り上げた「鉄鋼王」だ。彼の賛同はこの議場でも大きな意味を持つものだった。
「ふむ、提案としては悪くないね。術士の皆さんはどう思うかね。」
そちら側の席に着く男たちは険しい顔をして唸ったり首を傾けたりしている。
「平民の方々は勝手に合点していらっしゃるようだが、彼が世間を――殊に術士社会に対しては大いに――騒がせていることをお忘れなく。そしてこれは外交問題でもある。」
「グレイヒルの技術が広まることで術士が職を失い、排斥されることを恐れているのだ。」
「それは大統領である私が、そして社会の皆さんが向き合うべき問題であり、グレイヒル技士の問題ではないね。とにかく、この調査を行うことに反対ではないでしょう。」
彼らの表情には不満が残っている。しかしエジソンの発言の通りなら、ロバート一人を粛清すれば済まされる問題ではないことも確かだ。
術士の一人は顔をしかめながらに語った。
「それはそれとして、やはりグレイヒルが徒に社会を動揺させたことが許されてはならない。その報いは当然必要でしょう。」
「彼の発明した技術によって機械の事故が無くなり、幾万の生命が救われるなら十分に報いたと言えますぞ。」
カーネギーは答えた。
「……もしそれが叶わなかったら?」
議場は静まり返った。クリーヴランドがその言葉に答える。
「よいでしょう、その場合は彼に相応の処罰を与え、元凶となった研究は破棄させる。この条件でどうかね。」
術士たちの沈黙は、それが少なくとも否認ではないことを示している。
「お待ちください、大統領。」
そう言いながら手を挙げたのはワトキンス。
「あなたが仰る『相応の処罰』とは何でしょう。」
「技士として重大な倫理違反、大きな社会の混乱、合衆国を外交上危うい立場に追いやった責任、その代償は非常に大きいものになるよ。」
「そんな、大統領!そもそもこの条件は彼にとって不利です!事前の同意も得ずにこのような調査に協力させられるなど。それにあなた方は結局金儲けのことから離れてはいないではないか。」
「まあ聞いてくだされ、将軍。」
ワトキンスを宥めてカーネギーは言う。
「あなたの仰るように、我々商売人は時として利益のために社会の倫理から外れる。小癪な守銭奴だとか、『泥棒男爵』だとか非難されることは慣れている。だからこそなのですぞ。我々だからこそ社会の倫理に外れる結果を招いたあなたの甥に対して、救いの手を差し伸べられるのだ。」
「将軍、あなたの御心は分かっているよ。私は大統領として合衆国民であるあなたの甥を救う義務がある。それと同時に全ての国民の命も預かっている。その両方がかけがえのないものだから――これは対等な取引なのだよ。ロバート・グレイヒルと、合衆国民とのね。」
ワトキンスは分かっている、これがロバートに対する最大の譲歩だと。午前の紛糾に比べたら大変な進歩だ、これ以上ないくらいだ。それだけど、彼の安全を確約するには至らなかった。ロバートは叔父に感謝するだろう、兄貴と義姉さんは自分を赦してくれるかもしれない。しかし――。
議場の隅、雛壇の最上段にフランシスの顔を見た。彼女は会議の成り行きをずっと見守っていて、そっとワトキンスに微笑みかけた。
ワトキンスは席に座った。
「では、次の問題はどのように調査をするかということだが……グレイヒル技士はどこにいたかな。」
「今朝方、彼から電報が届きました。オマハにいるそうです。数日前はソルトレイクシティから。」
「鉄道で東に向かっているようだね。追手を逃れているとも見えるが、鉄道を使うことを辞めないならば、急いでどこかに向かっているのだろうか。」
「分かりません。」
「すると今後も鉄道で東に向かうかもしれないね。すると、高い確率である結節点の街に辿り着くのではないだろうかね。」
「……シカゴですか。」
シカゴはイリノイ州のミシガン湖畔にある工業都市で、鉄道各社の車両基地が置かれる一大鉄道都市である。従って周辺の路線は車輪のハブとスポオクのように、自然とシカゴに集まるようにできている。
「そこで調査するというのはどうだろう。」
無言で手が挙がる。クリーヴランドはその男に発言を求めた。
「差し支えなければその役目、我に引き受けさせてくれたまえ。シカゴには我が経営する実証実験に打ってつけの場所があるのでな。」
「ほう、あなたは……。」
クリーヴランドは頷いた。
「異論のある者は。」
誰もが沈黙を守っている。
「では実証実験は彼の下で行うこととして、グレイヒル技士の研究が認められた暁に彼を支持する方はこの後署名を行ってもらいたい。合衆国政府は明日これを決定する。」
その後の一声によって公聴会はその大仰な雰囲気に反してあっけなく幕引きを迎えた。
大統領は待ち受ける激務のためにホワイトハウスに引き上げてしまった。議場を去る人の波を横目にワトキンスはまだ席に留まっていた。一人、流れに逆らってこちらに向かってくる人があった、フランシスその人である。
「ご苦労様でした、将軍。」
彼が座る席の前に立ってフランシスは言った。二人のいるところは段の高さが違っていて、ワトキンスが顔を上げるとちょうど同じくらいの高さに彼女の顔があった。
「フォルサム嬢も長い時間さぞお疲れでしょう。……大統領はすぐにホワイトハウスに戻られてしまいましたよ。」
「仕方ありませんの、それがあの人ですわ。」
彼女は頷いた。そうは言っても別れを言えなかったのは少し残念がって、どこか物憂げな目をしている。
「小生は無念でならない。これ以上の条件は不可能だと理屈では分かっているからこそ余計に歯がゆいのです。」
「心中お察しいたしますわ。」
「甥がまだ幼かった頃に兄夫婦は亡くなり、小生が彼を引き取りました。それから何もしてやることができなかった。今日もそうだった。例え彼や彼の両親が小生を赦そうとも、小生は己で己を赦すことができません。」
勢いに任せて語り過ぎてしまったと自省した。それでもフランシスという女性には全てを打ち明けてしまうような、そしてそれを受け止めてくれるような慈しい雰囲気があった。彼は顔を手で覆った。腐れ切った「名将」の仮面がぼろぼろと剥がれ落ちていくのを抑えることはできなかった。
「一つ、興味深いことを教えて差し上げますわ。クリーヴおじさんは十代の頃に御父上を亡くして、伯父上の家庭で育てられたそうですわよ。」
ワトキンスは顔を上げた。
「なんと。」
「わたくしのことといい、あなた方にはどこか運命じみたつながりを感じますわ。」
フランシスは彼に微笑む。
「――あなたの甥を、信じてくださいましね。」
「フォルサム嬢、感謝申し上げる。小生の戦争はまだ終わってはおりませぬから。」
旅程の中途、オマハに留まった一日間は彼らに休養を与えた。もっとも、長く厳しい大陸横断の旅で、道中身体に傷を負った彼らにはそれすらも十分なものとは呼べないだろう。それでもこれから先の道を進んでいく活力を養うに資するものだった。
明け方、一番の列車に乗って一行はオマハを離れた。
ミズーリ川東岸はアイオワ州、ここからミシシッピ川まで三百マイルほど走り抜けるのは豊かな草原地帯。ここをプレイリーといって、低木と背の高い草が茂る。西から始まった旅路は長いこと乾燥した砂混じりの風に吹きつけられていたが、ここには最早そのような過酷な自然はない。プレイリードッグが走り回る土地を入植者たちは穀倉地帯に変えてきた。
ところで、プレイリーの語源はフランス語で「牧草地」である。十六世紀から始まったアメリカ植民の歴史の中で、かつてこの地域はフランス王ルイの統治の下にあって、その土地をルイジアナといった。トマス・ジェファーソン大統領はミシシッピ以西のフランス植民地の購入を決断、南はルイジアナ州から北はモンタナ州に至るまでの広大な土地は合衆国の版図に加えられた。独立以来大英帝国から勝ち取ったのみの領土に初めて第三国より手に入れた領土が加わった瞬間である。合衆国はアメリカという大陸を舞台にして幾度もの拡大を続けてきた。
鉄道各社は自らの鉄道で長い列車旅がいかに快適に過ごせるかを競って宣伝しているが、実際のところ――以前よりずっと改善されたとはいえ――全く不自由がないのとは程遠かった。乾燥して味の落ちた食事、風通しの悪い車内や、首肩腰が痛むような硬い座席は当然のことで、寝ても取れない疲労は日毎に彼らにも蓄積していた。そういうわけでオマハでの一日は素晴らしいものだったが、また移動を続ける日々に戻るとは考えようによっては襲撃よりも厳しいものだったりする。
公聴会については今朝の朝刊に記事が載せられていた。一日がかりで行われた会議の中ではある重要な決定がなされたらしい。その詳細について述べられていない。だが参加した資産家への取材によれば、「技士ロバート・グレイヒルは今日明日処罰されるものではない」とのこと。合衆国政府は今日にも決断を下すとみられ、合衆国のみならず外国の市民や為政者までがその発表を待ち受けていた。
ロバートはといえば、論文の執筆が進まないというので頭を抱えていた。仮に平穏無事な行程だったならニューヨークに着くまでに書き上げられようはずもないのだが、種々の事態で遅れが生じている分「到着までに論文が書き上がるのではないか」とにわかに思い始めるようになっていた。ところが実際は、目標とする進捗に達しない日ばかり、誤字は絶えず、考え直して章をまるごと書き直したりして、周りの者が想像するほどの十分の一も進んでいないのである。
大学の教授が何年もかけて論文を仕上げる者もあるところ、たった二週間かそこいら前に調査が終わったものを即席でしたためるのは十分異例なことだが、どれだけ残されているか分からない時間で彼は何としても仕上げなければならない。
列車はアイオワ中部のデモインを過ぎて、さらに東へ向かう。車窓は四角く整った土地区画の農場が広がっている。
「広い畑。」
窓の外を眺めるリニーは呟く。左肩は動かさないように固定して、控えめに身体を傾ける。ポンチョは洗って着られるようにしたが、どことなく生地が弱くなっている。それでも彼女は変わらず身に着けていた。
「トウモロコシであるな。」
「あんなに広くて、どれだけの人が作業してるんだろう。」
「小作人がたくさんいるのね。私も街での暮らしに飽きたら平和な自然の中で暮らしたいものよ。少しくらい、生活が不便でも構わなくてよ。」
話を聞いていたロバートは考え事をやめて顔を上げた。
「プレイリー狂に罹るぞ。」
「何よそれ。」
「プレイリー狂というのはある種の神経衰弱だ。だだっ広い土地に入植した者のいくらかは、この何もない世界に堪えられなくなって数年と経たぬうちに半狂乱に陥るそうだ。これをプレイリーの呪いだって言うんだ。」
「あなたは平気で気を悪くさせるような話をしてよね。」
アンジェラは呆れて息が出た。
「何ゆえそうなるか。」
「この土地に何もないことが問題なんだ。ホームステッド法の下、入植者は五年間同じ土地に住み続けなければならない。人もいない、娯楽もない、夏の乾燥と冬の寒波に晒される土地に留まることで堪え難い孤独を覚えるそうだ。それで精神は乱れ、神経衰弱に陥ってしまう。」
「――どんなに気丈な者にも、孤独という毒はゆっくりと回っていく。気付いた時には引き返せないほど身体を蝕まれているんだ。……だが、プレイリー狂はなにも大平原に限ったことじゃないかもしれない。大都市の真ん中にあっても、誰もいない荒地に立っているような孤独に苛まれることはあると思うんだ。」
「人の心はいつだって時化得るものよ。それは術士でも防げない……シヴィル・ウォーのように。」
「そう語る人もあるけど、僕はそれを認めたくはない。起きることを防げないものを『時化』と呼んで仕方ないと諦めてしまうのは違うと思うんだ。人の心を繋ぐ手立てはきっとある。……それにさ、時化だって防げないものじゃないと分かっただろう?」
トウモロコシ畑の先に集落が見えてきた、それは大平原という海原に浮かぶ小さな島のようである。この列車はあといくつの島を越えて、次の都市に辿り着くだろうか。
四人は午後にアイオワ州の東端、ダベンポートに到着した。ミシシッピ川にかかる鉄道橋を渡り、対岸のイリノイ州に入ったところで列車は駅のホームで停止した。ロバートはすぐにホームの様子が平生と違っていることに気付いた。やけに張り詰めた空気で、車窓からそっと覗いたところ、そこには黒い軍服を着た男たちが並んで立っているのが異様に目立っていた。三人もそれを見とめ、緊張が走った。
「合衆国陸軍だ。なんでこんなところに……なんて考える必要はないな。」
兵卒は一人一人が標準兵装のライフルを肩に掛けていた。
「ロバートを探しておるのだな。」
列車は今や完全に停止し、飛び出てきた車掌と小隊長らしき先頭の男が会話をしている。
「どうするの、今の内なら後ろの車両から逃れられてよ。」
「まさか。陸軍が動くのならついに合衆国政府が腰を上げたんだ。こうなったら逃げも隠れもできないさ。」
「捕まえられちゃうかもしれないよ。」
「それも顔を合わせれば分かることさ。」
合図と共に小隊は分散して各車両のデッキの前に立った。これですべての扉を封鎖している。
「座っているんだ。堂々とね。」
そう言ってロバートはどっかり座り込んだ。
数分が経過した。ついに車両の扉が開く音がして、軍靴が床を鳴らし、一直線に向かってくる。音はすぐ横で止まった。
「……あなたがロバート・グレイヒルですか。」
名前を呼ばれて彼は顔を上げた。そこには車窓越しに遠巻きに見た階級の高い軍人と車掌の姿があった。
「そうだが?」
「あの研究資料をお持ちですか。」
「『あの』が何を指すか分からないが、僕の輝かしい研究の成果なら今ここにあるがね。」
ロバートは小脇に抱えた鞄を指で叩いた。
「我々はロックアイランド兵廠の者ですが、大統領命令によりあなたの身柄を確保せよと指令を受けている。どうかご足労願いたい。」
「拒否権はないようだな。僕を連れて行ってどうするつもりなんだね。」
「我々に説明できることはありません。」
二人の沈黙を周りの者も固く見守っていた。しばらくして男が口を開く。
「ワトキンス・グレイヒル大佐から電報を預かっています。」
「早くそれを言ってくれよ。」
電報を差し出されるや否や、ロバートはそれをもぎ取った。そこにはこのように書いてあった。
「コノ モノラニ ツキテ シカゴヘ ユケ カノ トシニテ ワレ デンワス」
シカゴに行けば叔父さんと電話する機会がある。政府の結論はそこで語られるのだろう。一言で示されないあたりがどうにも煮え切らなかった。政府は少々複雑な決定を下したというわけか。
ロバートは電報を折り畳んで懐にしまった。
「いいだろう、言う通りにする。だが、ここにいる者はどうなる。」
「お連れ様もご一緒にとのことです。」
ロバートが順番に目を合わせると、三人は頷いた。
「案内してくれ。」
彼は荷物を抱えて立ち上がった。
アイオワ州ダベンポートとイリノイ州ロックアイランドの間、ミシシッピ川の中州にあるのがロックアイランド兵廠である。大河の中ほどにあって防衛上優れた土地であるこの中州には早くから陸軍基地が置かれた。その後島には刑務所が建設され、シヴィル・ウォーで拘束された者の一部はここに収監された。現在はここに陸軍の兵廠が稼働し、銃器や火砲の生産を行っている。また、ロックアイランドはある歴史的偉業が成し遂げられた場所でもある。
ミシシッピ川――全長二千三百マイルに及ぶアメリカ大陸の河川。先住民の言葉で「大きな川」という語源の通り、蛇行する流れはミネソタ州に源流があってルイジアナ州の河口まで流れる。誕生間もない合衆国にとってミシシッピ川は最初のフロンティアを隔てる境界であった。その流れを利用し水運によって発展を続けてきた流域の都市に対し、西岸は手つかずの大地が広がっていた。鉄道が急拡大を続けていく時代にあってもその母なる川の流れは鉄道の伸長を妨げてきた。この状況がついに打ち破られたのは一八五六年、トマス・デュラントのミシシッピ・アンド・ミズーリ鉄道によって、ロックアイランドから兵廠を通りダベンポートに架かる鉄道橋が完成した。これによってミシシッピ川を越えて西に物資が供給される……かと思われたが、橋は蒸気船の衝突によって完成から僅か二週間で焼け落ちる。鉄道に物流を奪われることに危機感を抱いていた船会社は鉄道橋の立地の悪さを糾弾したが、優秀な弁護人によって鉄道会社の権利は守られる。その弁護人の名はエイブラハム・リンカーンといった。
現在では新たな橋が架かり、一日中ひっきりなしに列車が往来する。困難な事業を成し遂げた人々の意志によって、ミシシッピ西岸はもうフロンティアではなく、農業が栄える穀倉地帯になった。
ロバートはロックアイランド兵廠に留め置かれた。彼はすぐにでもシカゴヘ護送されるものと思っていたがそうではなかった。特別列車を手配してあって、夜行でシカゴに向かうらしい。彼らはその時間まで島のある区画内で過ごすようにと命じられた。
待合室には練兵場の小さな一棟が与えられている。テーブルが並んだ広間の他に小室がいくつかあって、それらも使ってよいということだったので、ロバートは三人を広間に置いてその一つを借りた。発車時刻まで時間いっぱい執筆作業にあてるつもりでいたが、予想外に身が入らなかった。この先シカゴで待ち受けるものが分からなかったからだ。少し書いては休んで、また書いてを繰り返し、とうとう集中が切れた彼は諦めて一切をしまい込んでしまった。
広間には誰もいない。おそらく彼らも小室で休息を取っている。この後夕食まで用意されているというので、その時には再び会えるだろうと思った。警備の者に外に出てよいかを尋ねると、少し散歩できるような小道があるのでそこならばよいと言われた。付き従う兵士はいない、まさか逃げ出したりはしないと見立てているのだろう。
小道というのは島の外郭の道で、ミシシッピの流れを見ることができた。向こう岸までざっと何ヤードあるか分からない、とにかく幅の広い川で、蒸気船が上流へ、下流へ、煙を吐きながら行き来しているのを確認できた。河岸には刈り揃えられた草っ原などがあって、一本の木が佇む木陰に見慣れた人影を見た。アンジェラが腰を下ろして流れを遠く見つめていた。ロバートは足音を忍ばせて背後に近寄る。
「こんなところにいて、川に落ちたりしないか。」
彼女は振り向いてにやりとした。ロバートは無言で隣に腰掛けて、一緒になって川の景色を眺めた。
「お仕事はどうしたの。」
「少し休憩。」
日は西に傾いて、太陽が水面を輝かせている。
「話には聞いていたけれど、ミシシッピ川は本当に広くてよね。サクラメント川よりずっと。」
「ああ、立派だな。」
「こんな広い川に落っこちたら、誰も助けてはくれなくてよね。」
「君、まだ泳げないのか。」
「そうよ!だから何?」
負けず嫌いの彼女にしては珍しく開き直ったものだから、本当に泳げないのだろうなと彼は思った。
「構わないさ。君が落ちた時は僕がまた助けるよ。」

アンジェラはため息をついた。
「私はずっと、あの時偶然居合わせたあなたが救ってくれたと思っていたけれど、本当は日頃から私のことを観察してたんですってね。どうして?」
「えっと、それはだな……一人で川遊びなんかしてたら危なっかしいからだ。他に理由はない。」
「ともあれ、『覗き魔さん』のおかげで私は助かったのね。ありがとう。」
彼はきまり悪くなって帽子を深く被った。
「私がとんだヘマをしなかったら、私たちはこんなところにはいなくて、あなたも技士になっていなかったかもしれないわね。」
「今よりは安泰で退屈な生活を送っていたろうな。」
「それよりも『私があなたを家に招かなかったら』ね。」
「招待してくださったのはエマソン卿だろう。……そういえば前もそんなこと言ってたよな。『僕を見出したのは私だ』って。」
またしてもため息がこぼれる。
「あなたが知らなくても当然よね。よくってよ、真実を教えてあげる。」
やけにすごんだ言い方で、ロバートは生唾を飲んだ。
「彼の娘の命を救ってくれた恩人に対して、お父様は彼と彼の叔父上とにお礼の品を差し上げるつもりでいたわ、でもそれだけ。私はしばらく外出禁止を言い渡されていて、これでは私が礼を言うことができないからって、お父様に言ったのよ。せめて彼をお茶会にお誘いするくらいはさせてください、って。そうしてお父様は我が家に二人を招待することに決めたの。」
「……それ、本当か?」
「本当よ。私が言い出さなきゃお父様があなたの資質を認めることはなかったのよ。」
それでロバートは考え込んだ。
「しかし、茶会なんてあったかなあ。」
「あなた、私の隣で本を読んでたじゃない!お庭の戸外室のテーブルに、書斎から持ってきた古っぽい本をこれでもかと積み上げて!」
「あ、ああ……あれは茶会だったのか。」
「もう最悪!置いてあったクッキーも黙ってバリボリ食べて……あれを焼いたのは誰だと思って?」
「……まさかあ。」
「その『まさか』よ。」
「それだけ美味かったってことだろう……な?」
「私になんかちっとも興味はなかったのね……あれだけ準備したのに。」
一通り憤慨してから彼女は萎れたようになってしまった。これは本当に悪いことをしたと思ってロバートは流石に平謝りした。「今は昔のことでしょう」とアンジェラは言った。
「挽回させてくれ、今度一緒にお茶しよう、な?どこだって君の好きなように――それで君がアップルパイを焼いてくれるんだ。僕はあれが気に入ったんだ。」
「あれは店のオーブンがよいものだったのよ。」
「優れた機械だって、使いこなす者がいなければ役に立たないだろう。料理は材料や道具じゃないさ。また作ってくれないか。」
「そんなに必死にならなくても、もういいのよ。」
「いいや、僕は君と一緒がいいんだ。」
「……いいわ。」
「やった!君は最高だ!」
アンジェラは呆れて口から笑みがこぼれた。少しか機嫌を取り戻してくれたかと、ロバートは安心した。
蒸気船がすれ違う。低い唸り声のような汽笛を上げた。河岸の近くで魚が跳ねる。波立つ水面。
「お父様もいけないのよ、折角娘がもてなしを用意しているのに、すっかりロバートを気に入ってずっと本を与えるのだから。」
「それがエマソン卿のいいところだよ。僕のような子供に対しても丁寧に接してくれる。」
「そうね、お父様は立派な人。世間に対して――家族に対してもそうあろうとしただけ。それを受け容れられなかったのは私の方。」
彼はアンジェラを見た。河岸のこちら側に視線を落として、どこか虚ろげで、何だか今日は本当に調子が良くなさそうで心配だ。エマソン卿は公聴会に出席したのだろうか。そうだとすれば、会議で何を聴き何を語ったのだろう。今現在命を追われている娘にどう思っているのだろう。
「私ね、あなたにお手紙を出そうとしたことがあってよ。」
「へえ。文通か、それも楽しかっただろうにな。」
「だけどお父様はお許しにならなくて。彼に迷惑だろうからと言っていたけれど、本当は送らせたくなかったのね。どうしてもとお願いしたら、送る前に自分が読んで内容を確かめるからと言った。だから私は諦めてよ。人に送った手紙を別な人に検閲されるって、そんなの許せる?」
ロバートは首を横に振った。
「でもそれで諦めたわけじゃなくてよ。あなたが東海岸の学校に進学してからも送ろうとしたことがあったの。ちょうど冬の季節で、あちらはカリフォルニアより寒いでしょうからって――赤いマフラーを。手紙を添えなければ読まれることもないでしょうと考えたのだけれど。これでもしあなたが私に返事をくれたら、お父様はきっと読むでしょう。それが嫌だったから私は諦めた。」
卿の行動が全く度を越しているかといえば、そうでもない。娘の交際関係を気にするのは当たり前のことだし、術士の家系なら尚更だから。家長として家庭を治めることは当然だ。それはアンジェラにも分かっている。
「あなたがお父様に送っていた手紙、私もこっそり読んでいたのよ。とっても楽しかった、何を学んだとか、誰に会ったとか、全然分からないけどあなたが楽しそうなのは分かった。あれくらいしかあなたを感じる手がかりが無かったから……。」
「アンジー、」
彼女は顔を上げた。隣の彼は川の向こう、夕と宵が混じった空を見据えていた。
「散々躓いた挙句、大それたことまでやらかしたけど、僕はこの技士の仕事がどうしようもなく天職だと思っているよ。だから僕をこの道に引き合わせてくれた君には感謝してもし尽せない。」
「命を狙われても?」
「死んだような毎日から僕を救い出してくれるのはいつも君なんだ――」
「――必ず最後まで辿り着いてみせる。もう少しだけ一緒に乗ってくれないか。」
「ええ、喜んで。」
日没後、四人を乗せた列車がロックアイランドを出発した。たった二両編成の特別列車――一両目が護送を任された警官隊が乗る車両、二両目が四人が乗る車両。機関車のボイラーが発電機能を持った新式のもので、車両にも電気の照明が点いている。例によって時化やすく、そのままでは使い物にならないが、ここには二人の術士がいるから安定して点灯している。
列車はイリノイ州を進み、明け方にはシカゴに到着するだろう。一晩を列車で越すことになる。
夜の世界は暗い。地平線と夜空との境が見えて、夜空の方がいくらか明るく見えるのだ。農場ばかりの片田舎に瓦斯灯などはなく、夜が深まれば人家の明かりも消えて世界は原始の闇に包まれる。そんな中を駆け抜ける一つの列車は暗闇に咲いた一輪の光の花。花であれば蝶々が集まり、光であれば羽虫が集る。この光に誘き出され、集まるものはいったい――。
発車前に夕食を済ませてしまえば殺風景な列車ではいよいよすることが無くなって、寝る以外に手立てがない。これまで車内で夜を越す時は誰か一人は必ず起きているようにしていたが、護衛付きの特別列車ではそのような用心も必要なかろう。安心して、だが武器だけはしっかりと抱え込んで、各々は座席を独占して横になることができた。
ロバートは夜半に目を覚ました。床に就いてからしばらく寝て起きてを繰り返しながら浅い眠りに浸っていたが、とうとう眼が冴えて起き出した。眠れないのは支給の毛布が肌に合わないからか、術士の手を離れて時化だした照明が頭上で明滅するせいか、それともこれから待ち受けることを思ってか。その全てであって、どれでもないようで、さっぱり見当もつかない。
車窓の鎧戸を開けてみても、闇という扉で閉ざされた世界だけ。さっき目を覚ました時は列車が止まっていた。あれからどれくらい時間が経ったか分からないが、もう日付は越していると思う。夜のため速力を落とした列車も、シカゴまでの道のりの半分は越したはずだ。
「ロビン……どうかしたの。」
背後から眠たい声がして彼は驚いた。向こうの座席で眠っていたアンジェラが上体を起こして目を擦っている。
「悪い、起こすつもりはなかったんだけど。」
「さっきからあまり寝付けなくてよ。」
気が付けば車内では全員目を覚ましていた。どうやら誰も皆この夜に慣れていないようだった。
「列車はどこまで来た?」
「さあ……でも夜明けも決して遠くはないだろう、この際だから着くまで起きていようか。」
「同意する。」
「前の車両に行けばコーヒーがもらえるだろうか。ついでだから今はどの辺りにいるか尋ねてみよう。他に欲しい人いる?」
三人とも手を挙げた。
「私も行くわ。」
「いいよ、ここで待っていてくれ。」
立ち上がろうとする彼女を制して、ロバートは前方に進んでいった。
「足元気を付けてね。」
「ああ。」
扉を開けると夜の空気が頬に吹いた。デッキの冷えた鉄の手すりが体温を奪う。彼は向こうの乗務員車両に移って、扉をノックしてから開きざまに声をかける。
「すまないが、コーヒーを貰えないだろうか……」
「何なンだよお前ェ!」
ブースは彼に跳びかかる。その身のこなしの早いこと、座席数個分の距離はあっという間に詰められた。頭に強い衝撃を受けて意識が朦朧としていたロバートは、一瞬の隙が命取りになった。黒い拳銃を持つ腕に掴みかかり、彼は自らの腕が削れるような音を聞いた。激痛――それが自分の腕でなくなったような感覚。
彼は車両の前方まで突き飛ばされ、扉の前に倒れ込んだ。外の冷気が身に染みる。ブースはロバートの右肩に足をかけて彼を見下げた。
「ドタマに撃ち込まれて生きてるなんて筋書きにねえけどよぉ、どうってことねえよな。」
「思い出した、その名前……」
呼吸をするだけで痛みが走る。ブースは彼の声を聞こうと、踏みつけた足にさらに体重をかけて顔を近付けた。ロバートは思わず迫真の叫びを上げる。
「リンカーン大統領を、暗殺した男……有名な俳優で、名前は……ジョン・ウィルクス・ブース。」
「そうだ!名誉だな技士ン坊!大統領閣下と同じ、このブース様が墓場に送ってやんのよ。」
「なぜだ……死んだはずじゃ?」
「でも生きてる!殺し屋が死んでちゃ誰が地獄行の片道切符をくれてやれるンだ?――技士ン坊、おしゃべりは終わりな。お前さんの研究渡してくれな、鞄にさ、入ってンだろ?」
顔を歪めながら、ロバートは鼻で笑った。
「あんなものは紙切れだ。研究の全てが入ってるのは――ここだ。」
人差し指で頭をコツコツ叩く。
「そか、お前さんら殺してのんびり探すや。ゆっくり眠ってくれな。」
ブースの手がロバートの喉元に伸びる。指先が触れようとした瞬間、列車の車輪が一斉に金切り声を上げた。全力の急ブレエキがかかったのだ。
ブースは慣性の力で前に投げ出される。そのまま扉の外に放り出され、デッキの柵に身体を打ちつけた。
ロバートは肩を押さえながら立ち上がって、すぐさま彼に掴みかかった。激しく喚き散らす彼の手を振りほどきながら、側方の乗降口に向かって力いっぱい体当たりをした。
「貴様ぁぁあ!!」
身体をよろけさせ、ブースは闇の中に消えていく。火花を散らす車輪が刹那に憎しみに燃えた彼の表情を照らし出して、ロバートは写真の感光板のようにそれが目に焼き付いた。
前方に向かう慣性の力が無くなって、その場に崩れ落ちる。間もなく前の車両から名前を呼ぶ声が聞こえてきた。
「グレイヒル技士!」
機関士の服を着た男が駆け寄って来る。不用意に肩を掴むので、彼は情けない声を上げた。
「銃声が聴こえたので様子を見に来たら、何があったんだ、なぜ全員殺されている?」
「今すぐ列車を出せ!」
そう叫んで、ロバートはむせ返った。
「何が……」
「いいから列車を出せ!敵が外にいるんだ!」
並々ならぬ殺気を感じて機関士は頷くなりとんぼ返りしていった。
右腕は動かない。肩の関節が馬鹿になったらしい。一度立ち上がってはみたが、再び走り出す列車の中ではまっすぐ歩くこともままならなくてまた倒れ込んでしまった。ロバートは車両の通路を這い進んだ。その先の床が血で汚れている。
「アンジー!稲熊!リニー!」
「こっちよ……」
血濡れた床の先から声がした。這いつくばって進むと、座席の陰でアンジェラが真っ赤な手を押さえていた。
「大丈夫か。」
「……なんとかね。」
「主こそ平気か。」反対側の座席から稲熊が言った。制服の上着を脱いで、血染みが広がる白いシャツを露わにしている。
「腕が使い物にならない。リニーは。」
「向こうの座席に。意識がないみたい。」
「畜生……あいつ、ブースと名乗っていた。死んだのじゃなかったのか……。」
ロバートはもうこれ以上動けそうもなかった。列車の揺れすらも痛みに響く。それぞれは力なく床に座り込んで救護が来るのを待ち続けた。
夜明け前のシカゴ。特別列車は駅のホームではなく車庫に向かうように予め線路の分岐器が切り替えられていた。車庫の中ではシカゴ市警と合衆国陸軍の一団が要人の到着を待っていた。護衛が全員物言わぬ屍となって辿り着いたことに彼らは揃って慄いた。
車両には元々応急手当を行う道具の一式が揃っていて、四人はシカゴに到着するまでそれで堪え凌いだ。ロバートは事態の説明より前に救急車を手配して三人を治療に送り、一人残って事情を話した。襲撃犯についてはぼかした。たった一人にこれだけやられたと言っても信じられないし、それがシヴィル・ウォーで散ったはずの亡霊だなんて口にできるはずもない。
本当はロバートも治療が必要な状態にあったのだが、自分が無様に倒れている間に大事な荷物が回収されてしまわないかを恐れていた。病院への搬送を進める警察官に彼は目の下を真っ青にしながらとことん食い下がり、結局、病院での処置が終わるまでは当初の予定も事件の捜査も後回しにするということで合意した。救急車で運ばれる最中も、彼は残った腕で片時も鞄を手放さなかった。その場に居合わせた者は彼の執念に動揺の色を隠せなかった。
ワシントンからは必要であれば今しばらく療養を続けてよいと電報が届いた。しかしロバートは午前の内に立ち直ってもう動けると言い張った。実際は腕と身体中の痛みで絶えず気を張っていないと倒れてしまいそうなくらいだが、一刻も早く叔父さんと電話を繋ぎたいと思っていた。重要なことは全てその電話で伝えられるだろうから、話さないことには煮え切らない。
案内されたのはシカゴの高級ホテル。十階分もあるような高層の建物で、部屋数は数百に上るだろう。大理石の壁と床、ガラスのシャンデリア、金色の手すりに装飾。自費で泊まったら一体いくらかかるか見積もることもできない。ここに電話はあった。ホテルの宿泊客は専ら政治家や資産家なのだろう、だからこうして東海岸の都市から長々と電話線を引いて繋がるようにしてあるのだ。
ロバートは電話を使ったことがないではない。電信技士の職務の延長として電話機に触ったことがある。電話というのは、聴くところと話すところがある。すなわち、受話器と送話器だ。向こう側の音声を聴くために耳に受話器をあてて、目の前の朝顔型のらっぱに声を吹き込む。そして、忘れてはいけないのが術電話士。そのまま使ったのでは絶えず時化の雑音が入って音が届かない。こちら側とあちら側に術電話士がいて、二人羽織で電話線の時化を止めて初めて会話ができるようになる。自分が術士なら一人でできようが、そうでなければ隣に術電話士を座らせる。
一階の一部屋にある電話の周りを、陸軍の兵卒が取り囲んでいる。こんな仰々しい空気の中で話さねばならぬと思うと気が滅入ってますます身体が痛む。ロバートは促された通りに受話器を取って、それを耳にあてた。
雑音、滝の音のようにざらざら響く。術士が電話線に手を触れた。するとある時雑音はピタリと止まって、徐々に意味のある音が聴こえてくるようになる。列車が隧道を抜けて、パッと視界が明るくなったかのように。
「――もし?こちらはワトキンス・グレイヒル。」
電話越しでも分かる、懐かしい声。
「聴こえるよ、叔父さん。僕だ、ロバートだよ。」
「おお、ロビン。また襲撃に遭ったと聞いたが、大丈夫か。」
「平気だよ。」
こうしているとどことなく痛みも和らぐようだった。
「何はともあれ、お前とこうして再び声を交わすことができて本当に良かった。ここに来るまで辛く厳しかったろう。お前はよくやった。」
「どうってことないよ。」
「他の者は無事か。」
「みんなは大丈夫、ひどい怪我じゃない。」
「ならばよかった。」
暫し声が途切れた。再会を喜ぶのは顔を合わせた時にしよう、今は本題がある。
「ロビン、いろいろ分からぬことも多いだろう。今から電話を替わるから、話してくれ。吾輩は隣で聴いているから安心しなさい。彼はとても重要な方だから、真摯にな。」
「はい。」
叔父さんが電話口を離れた。物音がして、新たな者が送話器の前に着いたらしい。
「もし。」
「もし。ロバート・グレイヒルと申します。」
「や。初めまして……といっても実際に会ったわけではないがね。私は合衆国大統領、グロヴァー・クリーヴランドだ。分かるかね。」
大統領――ロバートの肩に力が入る。
「はい、大統領閣下。」
「ロバート君、君は何か愛してやまないものがあるかね。」
「は。何でしょうか……。」
「何でもいいんだ、気に入っているものでもいい。」
これは打ち解けるための会話だろうか。彼はかえって頭が真っ白になってしまって、言葉にならない言葉を繰り返した。
「研究、でしょうか。」
「そうかね。仕事熱心でよろしい。私はね、愛してやまないものがある。それは正義と真実だ。それらを愛し、またそれらを愛する人民を大切に思っている。その逆に、私は何よりも嘘と不正を憎むんだ。それらは人を堕落させ、社会に悪をもたらす病だ。願わくは、君が私に共感してくれる男だとよいのだがね。」
「――さて、前置きはこれくらいにしようか。ロバート・グレイヒル技士、君は今合衆国で最も注目されている技士と言ってよい。理由は分かるね、君の研究が大きく世間を騒がせているからだ。それについて、私は政府としての行動を決断した。こうして私と話しているのは、その一環なのだ。……手始めに質問をさせてくれないかね。」
「どうぞ。」
「よろしい。」クリーヴランドは呟いて、次の質問を投げかける。
「君の研究は、新聞で報じられている通りに『時化と術とを止める』ものなのかね。」
「はい、そうです。」
「その内容を知っているのは君の他にはいないのかな。お連れ君たちはどうかね。」
「内容を理解しているのは僕だけです。それ以外には誰にも見せていません。」
「よし。君は鉄道で移動を続けていたが、どこかに目的地があるのかね。そこに何があるのかね。」
この質問には渋った。大統領が何を意図して問うているのかは分からない。これを言えば旅の目的は失われるかもしれない。だがそれよりもはっきりしたことは――ここで嘘をつけば、二度と彼の信頼は得られない。
「ニューヨークです。匿名の者から手紙が届いて『君の命は守れないが、研究を安全に保管してやることはできる』と。それが誰かは分かりません。」
「ふむ、つまり君はその正体不明の、存在するか否かも分からぬ相手に研究成果を届けようとしていたのだね。なぜそのようなことを。」
「これは人類の宝です。例え僕の命が奪われようと、人類の技術の新しい一歩だけは決して失われてはならない。黙って奪われるよりは、僅かな可能性に賭けて行動を起こしたのです。」
「……いいだろう。ではその人類の宝とやらを見せてもらおうか。」
そう言ってクリーヴランドは経緯を語り始めた。
合衆国としては研究がヴィエナ宣言に抵触しているか否かよりも、それが社会に与えた影響の方を重視している。同時にロバートにも基本的な権利があって、それが不当に侵され理不尽に命を狙われていることを看過できない。また研究内容そのものの価値についても一定の評価をしている。とはいえ、ロバート・グレイヒルとその研究を保護することは外交的にも危ない橋を渡る行為に他ならない。そこで政府は研究内容を精査することを決定した。
「今から君はある者の協力の下、技術の実証実験を行ってもらう。その新技術が本当に時化の発生を防ぎ、実用足るものならば、多くの人々を救うことのできる大変価値あるものだ。従って、実証実験が成功した暁には合衆国が総力を挙げて君を保護すると約束しよう。」
「そうでなかったらどうなりますか。」
クリーヴランドの声の調子が下がった。
「もし、実験で十分な効果が確認できず失敗と判断された場合。君はありもしないことを嘯いて二十年前の災禍を繰り返させるような大きな社会不安を招き、合衆国を外交上危うい立場に追いやった。その罪は重い――政府は君を国家反逆罪で提訴する。有罪が確定すれば無期懲役……少なくとも、叔父上が生きている間に塀の外の世界を見ることは叶わないだろう。」
突き付けられる、残酷な未来の可能性。
「僕と一緒に来てくれた仲間はどうなりますか。」
「君が罪人となったならば、それを助けた彼らも相応の処罰が下ることを覚悟してほしい。」
ここへ来ていよいよ、三人の末路を自分が決めることになるのだ。
「なお、君にはここまでの旅路でいくつかの犯罪行為が見られるから、この場で君を逮捕する。実験の期間中は自由な行動を保証するが、万が一途中で実験を放棄したり、参加を拒否することがあれば、それらの容疑でただちに身柄を拘束するよ。」
ロバートは周りを見た。部屋には陸軍に混じって市警も背後に立っている。
「最初から道は一つなんですね。」
「ロバート君、私はね、君の崇高な精神を評価している。自分でも不思議なことに、会ったこともないのに君のことを気に入ってすらいる。だからこそ、その精神に試練を与えよう。精神の高邁さは実在の効用によって評価されるべきだ。新技術で新たな地平を開拓したと豪語するならば、それが社会に役立つことを証明してみせなさい。それができた時初めて、君の精神は真に合衆国を導くものとなるだろうね。」
「――返事を聞かせてくれ、ロバート君。」
一世一代の大勝負だ。こんな一方的に押し付けられた勝負、理不尽にも程がある。負けることも、受けないことも許されない。助かりたければ、みんなを守りたければ、勝つ以外にない。こんなひどいことがあるかって、その場にうずくまって、泣き出してしまいそうだ――昔の自分なら。
ロバートは電話の脇に置いた鞄に目をやった。これは僕のものだ。何もかも諦めようと決めた時に、それでも一つだけ、どうしても諦めきれなかったものだ。この研究を信じろ。自分を信じろ。
「負けるわけが、ないじゃないか。」
大きく息を吸い込んで、痛む胸をふくらませる。何百マイルも彼方にいる相手にこの声が届くように。
「大統領閣下、僕にやらせてください。」
「よく言った。」
その声がひどく嬉しそうに聴こえたのは気のせいではなかったろう。
「実験に協力し、その成否を判断する者がそちらに行っている。詳細は彼から聞いてくれるかね。」
「分かりました。」
「ロバート君、君の叔父上は勇敢だ。議場にあって、時に心無い言葉を浴びせかけられながらも、君の名誉のために立ち続けた。その恩に報いる方法は一つしかないね、励みなさい。」
「はい。」
「電話を替わるからね」と言って、電話口の人が消えた。すぐに叔父さんの声が聞こえた。
「叔父さん、ありがとうございます。」
「礼には及ばない。ロビン、お前は立派な技士だ。どのような結果になろうとも、吾輩が家族を見捨てることは絶対にないとここで誓う。」
別れを言って電話が切れた。ロバートは受話器を置いて立ち上がった。振り向くと、目の前に警察官が立っている。
「ロバート・グレイヒル、あなたを放火、傷害、殺人、鉄道の業務妨害と器物損壊その他の容疑で逮捕します。」
左右を警察官に誘導され、ロバートはホテルの正面入口に立った。扉を開けた途端、眼前を覆い尽くす記者たちが彼に詰めかける。その数は会見場にいたのよりずっと多く思えた。通りのこちら側、あちら側、建物の窓からも多くの見物人がたった一人を見つめている。警察は記者たちと押し合いへし合いを繰り広げて、被疑者をホテルの前に止めた馬車へと誘導した。六頭立ての馬車で、鉄道馬車と見紛うような大きさの車はその装飾もわざとらしく、どう見ても警察車両ではない。
警官の一人が扉を開け、促されるまま乗り込んで後部側の中央に座る。次いで数人の警官が彼を囲んで周りを固めた。
ロバートが乗る前から車には一人の男が乗っていて、彼の乗車を待っていた。ロバートは顔を上げた。薄暗い車内に目が慣れて、真向いに座る口髭を蓄えた顔が次第にはっきりと見えてきた。
「驚いたな。技士は青い目の男だと聞いていたが、顔まで真っ青なのか。」
初老の男は見るからに上質な背広を着て、背中を伸ばし足を組んでゆったりと構えていた。
「少々、傷を負っていましてね。」
「構わん、技士ならば頭があればそれでよい。我はそれ以外に興味はないのでな。」
ロバートはその顔をどこかで見ていると思った。顔を合わせたことはないだろうが、全く初めてという気がしない。その予感は彼の自己紹介によって全て明らかになった。
「我はジョン・D・ロックフェラー、知らぬとは言わせないぞ、グレイヒル技士。お前の夜を照らしている油がどこで精製されているかを知っているのか?この国の石油産業を支配するスタンダード・オイルの最高経営責任者は我だ。」
ロックフェラー――その名を知らぬ者はいない、スタンダード・オイルの経営者。競合他社をすべて飲み込む暴力的な経営手腕で石油産業を支配し、今や合衆国の石油は――世界の石油までもを、この巨大な企業連合が生産している。
ロバートは処置を終えた右腕がまたキリキリ痛み出すようだった。
「車を出せ。」
合図で馬車は走り出す。好奇心に駆られた群集を遠ざけ、定められた目的地へ向かう。
「ロバート・グレイヒル、お前がサクラメントの大それた技士か。ここに来るまでさぞかし波乱に満ちた冒険を送ってきたのだろうな。だがそれに興味はない、なぜならお前は成功者ではないからだ。成功を収めること叶わなかった者の与太話に耳を貸すのは、寂れた酒場の落ちぶれたウエイトレスだけだ。」
この男、会うなり手厳しいことを言う。それでもロバートは黙っていた。誰もが知る大富豪に言い返すほど鯔背ではないし、もしくはただ単に口論するほどの気力が残っていなかったのかもしれない。ただ押し黙ってロックフェラーの目を見つめ返していた。
「クリーヴランド大統領とは電話で話したろう。彼から説明があった通り、合衆国はお前に対する態度を決定した。そしてお前はそれに協力すると宣言した。だから我はここにいる。これより我がお前の技術とやらの実証実験を主導する。そしてその効果の如何を判定するのも我だ。分かるか、お前の命運は我によって定められるということだ。文句があれば聞こう。」
「いいえ。」
「よかろう。老婆心で一つ教えてやろう、先人には礼を尽くすことだ。我はリンカーン大統領を敬愛している。大統領の下で戦ったお前の叔父上は英雄だ。だがそれはお前に何の影響も及ぼさない。たとえ自分の子であっても我は特別に扱ったりしない。」
ロックフェラーの語ることは彼の信念らしかった。
馬車が工場の敷地で止まった。この辺りは貨物用の鉄道が敷かれているようで、機関車庫に続く路線がいくつも見えている。
「ついて来い、これから実験の内容を説明する。」
一行は馬車を降りて、貨物路線に用意された列車に乗り込んだ。旅客営業用のものではなく工場の労働者を乗せる簡素な車両で、トロッコと呼ぶに近しいものだ。
全員の乗車を確認して列車が出発する。車窓には巨大な液体貯蔵庫、人の背丈はあるような管、もくもくと黒い煙を吐き出す煙突の群れなどが次々に移ろっていく。次第に敷地を離れ、シカゴ近郊の低湿地を走るようになった。
列車に揺られ続け、ある時平原の景色が様変わりした。土地にいくつもの巨大な工作物が立っている。それは鋼で作られた櫓のようで、見える範囲に数十本は立っている。ロバートはこれが何だか一目で分かった。
「油井を見るのは初めてか。」
「ええ。話には聞いたことがあります。」
「あれは原油を掘り出す井戸だ。この一帯の地下数百フィートには油田があり、そこから汲み上げている。全て、我のものだ。」
列車は停止した。この駅は辺り一帯の油井に通じる基地だ。多くの作業員が服を油で黒く染めながら行き来している。現場監督の男が一行を出迎えた。
移動する間、ロバートは油臭さと泥臭さが混じった鼻をつく臭いを始終嗅いだ。油井のある一帯がこの堪え難い臭いで満たされているのだ。警官らは顔をしかめて鼻をつまんだりなどしていたが、ロックフェラーは意に介さず進む。ロバートはこれを機械油と似たものだと思って気にしないようにした。
一基の油井の前に立って、ロックフェラーはそれを見上げた。先刻のホテルにも劣らない高さの櫓の中央に採掘する穴が掘ってあって、絶え間なく上下するポムプが原油を汲み上げている。
「これが油井だ。汲み上げた原油は多量の砂と砂利とを含んでいる。向こうの機械で油だけを濾し取って、輸送管でシカゴの精製工場まで送っているのだ。全ての油井で幾万バレルもの原油が汲みだされ、それが石油となって全世界に流通する。……グレイヒル技士、ここを『汚い』とか『臭い』と思ったか?」
「……ええ、まあ。」
「だろうな。だがこれは黒い金塊だ。これを掘り出すことは億万長者への道であり、現に我はこれで莫大な財を成した。そしてここが、実験の舞台だ。」
ロックフェラーは現場監督に問いかける。
「今日の稼働率は。」
「ひどいですよ。三割か、そこいらでしょうな。」
彼は再びロバートに振り返る。
「聞いたか。知っての通り、機械には時化がつきものだが、それは油井も例外ではない。むしろ、油井はその激しい時化によって生産量が著しく変動する。採油は時化に脆弱な産業なのだ。術士がいれば幾分マシになろうが、この数の油井全てに配置することはできない。加えて、臭いにこの轟音。お高く留まった術士らは決してこのような場所で働こうとはしない。」
「――グレイヒル技士、お前に与えられた試練は、この油井を時化の支配から解放し、最大の産出量を維持することだ。実験はここの油井を使って行う、計測時間は十二時間。その間油井の効率が低下することなく産出を続けたならば実験は成功と認める。逆に、少しでも汲上の勢いに衰えが見られたら実験は失敗だ。社会は大いに失望し、お前はその報いを受ける。計測は機械で行うから、不正は見逃されないぞ。」
一行はその場を離れ、近くの作業員詰所に入った。鼻が曲がる悪臭から解放されて警官は息を吹き返す。
二人は向かい合って席に着いて、ロックフェラーは書類を取り出した。突き付けられた書類にロバートは目を通した。目を引くのは、紙の中ほどに多数の資産家の名前が記されていることである。
「よく聞け。本取引はロバート・グレイヒルとそこに名のある実業家たちとの間で交わされるものだ。契約は次の通り。お前はこの課題を合格すること。実験は三週間後、それまでに必要な機器の全てを揃え、実験の準備を進めろ。これには非常に多くの企業が参加を表明しているから、設計図面さえ寄越せば彼らが何でも用意するだろう。」
改めて読み上げると、誰もが名を知るような偉大な資産家ばかりである。これらは公聴会に出席して政府の決定に賛同した者と、追随して名乗りを上げた者だ。
「実験が成功すれば、そこに名を記した者は皆お前の研究を支持する。加えて政府がお前を保護する。これだけの者が集まったのだ、合衆国経済そのものと言っていい。これら大企業の恩恵に与かるアメリカ社会はお前を讃えるだろう。だがそれには条件がある。ここに名を連ねた者たちに本技術を無償で提供すること。よいな。」
仮に技術が認められても彼らからは特許料を取ることができない。つまり資産家たちはロバートを支持する見返りに技術による効用をタダで受け取るということだ。
「はい。」
「それと、実験の成功はそれすなわちこの世に術を封じる手段が誕生したことを意味する。それが世界に与える影響が大きいことは承知したまえ。」
「それはもう分かっています。」
「失敗した場合、我々は今回の実験にかかった費用を全額請求する。既に我は少なからぬ金額をお前のために投じているしな。まあ実際のところお前は即日刑務所に収監されるのだから、補償をするのは後見人の叔父上になろう。」
「――そこに署名した時点で契約は有効となり、お前の試練は始まる。これは切符だ、その行先は栄光か、地獄か――それを決めるのはお前自身だ。」
目の前にペンが置いてある。ロバートは左手で迷わず手に取った。
不格好な字で名を記す。最後のLの字はペン先が斜めにズレて不格好に跳ね上がってしまった。
ペンを置いて、契約書を差し出す。ロックフェラーは署名を確認してそれを側近に預けると鼻を鳴らした。
「胆力はある男のようだな。お前の幸運を祈る。」
「見せてあげますよ、僕が見つけたものを。」
その日はすぐに列車でシカゴに引き返した。約束の日まで三週間。
イリノイ州、シカゴ。『アメリカの地中海』とも称される五大湖の内の一つ、ミシガン湖の南端に位置する工業都市。東海岸の都市群を除けば合衆国で最も巨大な都市であり、今なお成長を続けている。この地域が発展を遂げたのは他ならぬ五大湖の水運、そして付近の鉱山から産出する豊かな資源による。中でも鉄鋼業は栄え、西へ西へと拡大を続けた鉄道の路線を造り出したのはこの都市からである。一帯の鉄道が発展してからは各社の車両基地が揃う鉄道の街としても知られるようになり、日々何万もの人々が列車に乗って往来を続ける。集まった人の力は膨張し、シカゴの文化の蕾は開かんとしている。
シカゴについて特筆すべきは一八七一年に発生した大火であろう。ある晩、小さな家屋の納屋から上がった火の手は五大湖岸の強烈な乾燥と強風によって瞬く間に燃え広がった。素早く延焼を広げる火の手に消防車は為す術なく、一夜にして市街の大部分が灰に埋もれた。合衆国建国史上最悪とも呼ばれる火災に、シカゴの街は「死んだ」。
だがそれで終わりではなかった。積もった灰の下では既に新しい都市の芽が出ていたのである。雑多な道路は再整備され、延焼しない石造の建築が推奨され、それはシカゴに多数の高層建築をもたらした。大火を経てもこの地に集まる人の流れは止まることなく、見違えるような復興を遂げた。開拓者が何もない荒地に街を興すように、市民の不屈の精神がシカゴを蘇らせたのだ。
高級ホテルがある中心市街もかつてはシヴィル・ウォーの被害を上回る廃墟となった地区だ。そこから数分歩くと、市の大病院が構えている。彼の仲間はここの特別病室にいて、傷が癒えてホテルに泊まれるようになるまではここで療養することになっている。
ロバートは救急車で搬送されて以来初めてここを訪れる。一階で顔を見せれば即座に案内の者がついて、エレベイターで最上階まで上がり、病室の前まで彼を案内してくれた。
ホテルの個室よりずっと広い部屋に三床のベッドがあって、それぞれがカーテンで仕切れるようにできている。傍にはラムプを置いた机もついていて、ひょっとするとホテルより落ち着ける場所かもしれない。三人はそれぞれベッドに座って、部屋の入口に立つ彼を見てはあんぐり口を開けていた。
「やあ。どうしたってそんな顔するんだ。」
「どうしたもこうしたも……ロバート、二日も顔を見せないと思ったらいきなりひょっこり現れるんだもん。」
「しかもホットドッグなんかつまんでね。」
彼は口元のマスタードを拭って、これ見よがしに食べかけのホットドッグを見せた。
「死ぬほど腹が減っていたんだ。さっき外の出店で買ったんだよ。なんでかこのピクルス、甘いんだよな。しかもケチャップがないし、こんなのは初めてだ。食べるかい?」
彼は残りのホットドッグを口に押し込んで、右腕を首のところと括りつけて固定している布の中からもう一つのホットドッグをするりと出した。
「いいえ、遠慮するわ。」
「某らは昼飯を食うたばかりでな。」
「ありがたい、実を言うとこれも自分で食うつもりで買ったんだ。」
言うなり彼がまたホットドッグを貪り始めるのを、三人は呆れた顔で見つめていた。
ロバートは傍にあった椅子に腰かけた。窓際のベッドでリニーは頭に包帯を巻いていて、肩の怪我も包帯を替えてある。アンジェラは長いブロンドを下ろして、左手を布団の中に隠している。稲熊は傍の机に帽子と刀とを置いて、見えないが腕と脚とに怪我をしていた。みんなひどい負傷だった。
「何にしても、無事でよかったよ。しばらくゆっくり休んでいてくれ。」
「あなたこそね。」
「ずっと心配してたんだよ。二日も何してたの?」
「それが僕にも分からない。」
その言葉に眉を顰めずにはいられなかった。
「ロックフェラー氏と会った後、ホテルに戻ってベッドに横になったところまでは覚えてるんだ。気が付いたらリネンが蝸牛が這い回ったようにぐっしょり濡れていて――日付が飛んでたんだ。」
「えっと、熱を出して倒れてたってこと?」
「僕もそう推理している。」
「腹が減っておったのはそれ故か。」
「呆れた。まあ良かったんじゃない、あの日はあなたひどい顔をしていてよ。」
アンジェラは机の上の新聞を差し出した。前日の日付で、見出しに「グレイヒル、真っ青な凱旋」「目の下の『黒い』技士」などと書かれて、挿絵には弾痕のついた帽子を被った醜悪な男が描かれている。
「ねえ、それ切り抜きにしてもいいかしら?」
「駄目に決まってるだろ。」
「あなたの顔が新聞に載った記念よ。」
「最悪だ。」
アンジェラは新聞を奪い返してふふんと笑った。面白可笑しく描かれたナンセンスな似顔絵に何の価値があるのか本人には理解できない。
「話は聞き及んでおる。勝負を受けたそうだな。」
「ああそうさ。僕は逮捕された。……結局みんなのことも巻き込んでしまったな。」
「今更何を言うか。主が居らぬではここまで辿り着けぬ旅だった。」
「正直に答えなさいな、勝算はあるの?」
ロバートは俯いた。
「どうかな……。」
「気を落とすことないよ、きっとできるよ。」
「左手だけで書くのは骨が折れる……本当に骨は折れてるけどね。」
「つまらないわ。この期に及んで論文を先に仕上げるつもり?」
「折角三週間もあるんだ、この機会に書き上げてしまわないと。」
「実験の方はどうするのよ。機械を作らなきゃいけないのでなくて。」
「そっちか?図面なんて一日あれば上がるよ。」
平然と言い放つ、相当に自信を持っていた。
「主、やれるのか。」
「なぜできないって思うんだ?」
彼は目を鋭くした。それで安心して皆の顔から笑みがこぼれた。
ロバートは水差しを取ってそれを汲んだ。コップ一杯の水を飲んで食後の喉を潤す。ハンカチを取り出して口を拭った。
「――とはいえ、しばらくは忙しくするからここに顔を出せる機会は減るだろうな。」
「気にしないで。」
「この部屋に欲しいものがあったら言ってくれ。僕は実験に必要なものはすべて用意してもらえるから、その権限で拝借してやろう。……そうだ、僕の部屋にタイプライタを用意しよう。それで続きが書ける。」
「横領であるか。」
「正当な権利だ。」
立ち上がり、ロバートは「それともう一つ……」と言いかける。
「アンジー、電話使ったことある?」
「勿論。家にあるのよ。」
「手伝ってくれないか。叔父さんと話したいんだ。」
「いいけれど……ホテルに専任の術士がいるでしょう?」
「そうだが聴かれたくないんだ。叔父さんにあの話を伝えておきたい――僕らを襲った敵の話を。」
アンジェラはすぐに察して黙って頷いた。
「明日の昼でいいか。」
「分かったわ。」
彼はホットドッグの包みをくしゃと丸めてポケットに押し込み、後ろ手に手を振って病室を後にした。
明くる日にロバートが病室を訪れた時、アンジェラはリニーに手伝ってもらって髪をまとめている最中だった。普段着は少々血で汚れている部分があるが、それも患者の着る服よりはいくらか見てくれがいい。思えば彼の上着も荒野の砂塵と戦闘の傷とにすっかり汚れ、縫い目が解れて力を入れれば破けそうな状態で、おまけに帽子は弾痕で凹んでいる有様だから、あまり他人のことを言ってもいられない。
彼女はロバートの左側に立って隣を歩いた。左手を後ろに回して、彼が怪我の調子を訊いても「大したことない」と答えるばかり。彼女が努めて隠そうとしているのはあからさまで、ロバートはそれが心苦しかった。
ホテルの電話は彼がいつでも使ってよいということになっていた。この電話は会社が提携する他のホテルと電話線を繋いでいて、ワシントンの他、ニューヨークや各都市と接続があって、各界の重鎮が至急の連絡を入れる時に使うのである。
電話は合衆国の名技士アレクサンダー・グラハム・ベルによって発明された。彼は助手のトーマス・ワトソンと共に音声通信の研究を進め、一八七六年、電話は壁で隔たれた部屋にいる二人の声を繋いだ。最初に発された言葉は「ワトソン君、来てくれ、用事があるんだ!」である。
ロバートは数日前にやったように、アンジェラを術電話士の席に座らせて受話器を手に取った。電話線に術をかけるには両手で触れる――その時彼は初めて包帯が巻かれた彼女の左手を見た。彼女は諦め調子で、目が合うときまりが悪そうに目を閉じた。
電話口の叔父さんに事の子細を話した。「これはまだ僕らしか知らないことだ」と前置いて、例の襲撃犯について語る。叔父さんははじめ驚き、そこから黙って甥の話を真摯に傾聴した。
ジョン・ウィルクス・ブースはリンカーン大統領の暗殺犯、表向きの顔は人気の舞台俳優でありながら、裏では反乱軍の諜報員として合衆国軍が不利になる情報の収集を行っていた。シヴィル・ウォーの戦火が終息した頃、大統領は劇場で暗殺された。ブースはそれから警察の追跡に遭って射殺されたと公式では発表されている。だが、それが偽装で本当の彼は逃げおおせているとしたら――当時彼は二十代の後半だから、生きていれば今頃四十代の後半ということになる。それは明滅する照明の中で見たかの襲撃犯の外見と違っていない。
「繰り返すが、それは本当なんだな。」
叔父さんが問う。
「奴は確かにそう言っていました。僕は当時の記憶なんてほとんどないから、本人かどうかを判別することはできない。だけど問題はそこじゃない、模倣犯であったにせよ――その名を名乗る人物が現れたことが重要だ。そうでしょう?」
電話口に唸り声が聴こえる。
「お前を追う者は先の戦の反乱軍と関係がある、そう言いたいのだな。」
「はい。」
「……分かっていたのだ、本当は。」
そう言って彼は二十年前の記憶を回顧した。
「反乱軍の大半は戦場に出たこともない市民、戦うことについては素人……それにしては統制が取れていた、取れすぎていた。高度な作戦に基づいて、時には我ら正規軍を出し抜くほどの知略を見せた。彼らを指揮する高度な戦略家がいて、それが反乱軍を扇動しているのだと考えるのは容易だった。『合衆国の敵たるシヴィル・ウォーの首謀者を必ず撃滅せねばならない』、吾輩は内乱末期に大統領にそう進言したのだ。」
「それはどうなったんですか。」
「……ロビン、大統領を責めてはならん。彼は『今はそれをすべき時ではない』と仰った。戦火に打ちひしがれた合衆国の再建こそ第一の目標であり、徒に戦いを再燃させるような行為は慎むべきとお考えになったのだ。」
「だが、影の組織は確実に存在していた。そして奴らは今僕に牙を剥いている。」
「お前を危険な目に遭わせてしまうのなら、やはりあの時頑なに追討を主張すべきだった。」
「叔父様、ご自分をお責めになってはなりません。」
アンジェラが隣から声をかけた。「そこにいるのはエマソン嬢か」と叔父さんが反応する。
「僕を追う敵の動員の早さも、用意の周到さも、これで全て説明がつく。叔父さん、僕たちは認めなければならない――ずっと前からこの国には、合衆国を貶めんとする影なる組織が暗躍しているということを。シヴィル・ウォーは、まだ終わってなどいません。」
「そのようだな。」
叔父さんは押し黙った後に「分かった」と声を上げた。
「この件は吾輩に任せなさい。大統領と、軍の上層部とで話し合ってみよう。その線で捜査を進めれば何か有力な情報が得られるかもしれない。お前は自分の仕事に集中なさい。」
「僕がどうなろうとも、この問題だけは悔恨が残らぬようにしてください。」
「それがロビンの意志ならば、その通りにしよう。」
まもなく叔父さんは電話口から去った。それからアンジェラがふと彼の袖を引いて、口元に耳を寄せさせた。
「ねえ、そういえばこの会話、向こう側にいる術電話士に聴かれていてよね。内密にする話だけど、彼は信用できるの?」
「ああ、問題ないよ。」
ロバートは実にあっけらかんとして答えた。
「というか君、向こう側にいる術士が誰か分からなかったの?」
「分かるはずないわ!」
すると彼はアンジェラの耳に受話器を押し当てた。
「……アンジェラ、お前だな?」
機械越しの耳慣れた声。彼女は目を見開いた。
「お父様?」
ロバートはにこりと笑って送話器に声を吹き込む。
「エマソン卿、ありがとうございました。僕はこれで失礼しますから、お電話替わります。」
受話器を彼女の手に持たせ、席を譲って立ちあがる。
「ちょっと、待ってよ!」
「僕は仕事に戻るから。アンジー、彼に声を聞かせてあげるんだよ。」
彼女の頭を手でぽんぽんやって、それから踵を返して部屋を出て行ってしまった。アンジェラは一人残されて左手で電話線に触れた。言われてみれば確かに、線を通じて感じる他人の術はどこか波長が合った気もする。
「……もし。」
「アンジェラなのだな。」
「ええ、お父様。お久しゅう。」
「いろいろ聞きたいことはあるが……ロバート君といつ出会ったのだ。」
「十四年前……という答えがご不満なら、お父様に頼まれてロサンゼルスの発電所に行った時です。」
「それから彼について行ったのか。」
「はい。」
「どうせお前から言い出したのだろうな。」
「ええ勿論。そうやってどんな時でも他人は擁護しようとするところ、お父様らしいですわね。」
卿は閉口した。しばらく無言で受話器に雑音が流れる。
「なぜ彼に付き従ったんだ。自分のやったことが分かっているのか。」
「それは、彼の偉大な精神が理不尽に奪われるのが認められなかったからです。彼はお父様を今も尊敬していますの。片時もあなたへの尊敬と憧れをとを絶やしたことはないそうです。」
「だが彼の研究がどういうものかは分かっているだろう。平民嫌いのお前がなぜ。」
「大した問題ではないでしょう。古いおとぎ話では術士は皆森の中で暮らしてきた、それに戻るだけではありませんこと。彼の研究は術士の地位を貶めるものなどではない、『機械を動かすための機械』にされた私たちを解放するものなのよ。」
しばしば家を離れて森の中の別宅で狩猟などして暮らす彼女のことだから、術士本来の感性に近いものをもっているのだろうと卿は思った。だがそれは彼女の行動を正当化する理屈にはならないはずだ。
アンジェラは続けて語る。
「お父様はいつも仰られていたではありませんこと――我が家の家訓、フロンティア・スピリット。まだ何もない土地に人間が根差す、その最初の一歩となることを至上の歓びとする。彼の意志はまさにそれでしょう。」
「――お父様、私にはレイルが見えるのです。荒れ果てた荒野にあって、その険しい土地をまっすぐに貫く二本の平行な線、等間隔で渡された枕木。彼はいつだって迷うことなくそこを突き進んで、未来を開拓している。私はただ彼の隣にいて、そのレイルを共に進めたならこれ以上の幸せはありません。」
「アンジェラ……」
その無言が苦しかった。何か言ってほしかった。激昂して怒鳴ってくれればそれだけ言い返すこともできたろうに。顔が見えないのに声だけは鮮明に聴きとれるなんて、どんなに酷な機械なのだろう。電話線は強く時化だして、みるみる雑音が入ってくるようになった。アンジェラは今一度電話線に術を込めて声を伝えた。
「散々勝手なことをして申し訳ございませんでした。今日限りであなたの娘ではないとお思いくださいまし。もう話すこともございませんでしょうから、どうかお元気で。」
返事なんて待てない、すぐさま受話器を置いて、部屋を駆け出した。
病室に戻った時二人がどこか散歩に出かけて不在だったのは、良かった。一番嫌いな自分を彼らに見せずに済んだから。
世紀の大勝負の幕が開けてから実に一週間経った。この頃には各々の怪我も快復に向かっていて、病室でなくてホテルに移って個室で生活するようになっていた。
同じ階層で隣り合う部屋に泊まっていながら、三人がロバートの顔を見ることはなかった。実験に使う油井に顔を出したのも一日限りで、あれこれ調べた後はまた部屋に引っ込んでしまったと聞いている。日々の食事は部屋まで運ばせて、言付けがあれば料理と一緒に紙に書いて盆に乗せておくと、綺麗に平らげられた皿と一緒に返事が貰える。記者の前に姿を現さないので新聞には旗色悪しだとか好き放題に書かれているが、当人は浮世離れしているのでそれすら関係のないことだ。
代わりに忙しなくしているのは稲熊である。リニーとアンジェラは部屋に集って茶会などしていたが、彼は毎日外出する。廊下で出くわした時に話を聞いたところ、仕事の話だとか言っていた。
稲熊はシカゴに来て、合衆国に上陸した船に同船していた日本の技士使節団と合流した。彼を巡る事の顛末は本国の政府も把握していて、諸外国との外交関係を踏まえて非常に憂慮していた。軍法会議の話も上がっているという。ワシントンの領事を介して本国と接触した彼は協議を続けていた。彼が主張するには、ロバートの技術こそ富国強兵を成し遂げる切札に他ならず、ここは合衆国の肩を持って恩を売るべきであると。稲熊と知り合ったことで彼の技術は易々と日本にも提供されるであろうから、その点では稲熊の行動は会心のものである。これを本国に納得させるべく交渉を続けていた。政府としては合衆国への協力もやぶさかではないとしつつも、それにつけても列強の反発を招くことから態度を決めかねていた。やはり決定打となるのは実証実験の成否であり、仮に失敗するようなことがあれば、日本政府は自国への飛び火を避けるために稲熊の首を切るというのが既定の路線だ。失敗を少しも疑わない稲熊の姿勢に、彼らは光明を見出しつつあった。
アンジェラは東を向いた部屋の窓の前に立った。格子状の枠がついたガラスの向こうにはミシガン湖の水平線が見えて、その前の空中にこちらと向かい合った自分の姿が浮かんでいる。今日は波もあって、ここからではカリフォルニアの海岸の景色と大差ない。
彼女はライフルを構えた。左手はまだ物を掴めないから、曲げた左肘を突き出して腕に銃身を乗せて重さを支える。そうして自分と自分が銃口を向け合った。左腕で銃を挟んで装填レバーを操作し、もう一度狙いを定める。
精度も装填速度も下がったが、それでも銃は持てる。まだ、戦える。
臙脂色のケエスにライフルをしまってベッドの下に押し込んで、立ち上がってため息を一つ。ここ数日調子が出ないのは、怪我のせいか――否。ここの一階で電話をした時のことが尾を引いているのだ。ロビンときたら、すかした顔して気を利かせたつもりでいる、それが嫌いだ。彼は全ての親子は仲がいいという神話を信じている。将軍のように父親よりも父親らしい人なんて、それの方が珍しいのに。そう思いかけて、彼は実父を知らないのだと思い出す。
自分がそうできない分、私には親と和解してほしいのかしら。
でもそれは全て終わったこと。
こう部屋に詰めていては陰鬱とするばかりだから、外へ出ることにした。
シカゴは灰色の街だ。空は煤煙で薄黒く曇り、建物はどれも無機質な石だ。高層建築に挟まれた通りは昼間でも瓦斯灯がほしくなるくらいに薄暗い。おまけにひっきりなしに人が車が往来するから、道路が見た目以上に狭い。知らない街で迷子になったでは敵わないから、ホテルの周りをうろつくだけにしよう。まっすぐ歩いて湖岸を見て、それで帰ろう。
道の途中に出店があった。これは例のホットドッグ屋かもしれない。ロバートが食べているのに惹かれたわけではないが、午後の腹ごなしに一つ買ってみる気になった。
「一ついただくわ。」
焼けたソオセージ色のエプロンをした店主は不愛想に答えた。金を払って差し出されたホットドッグを受け取って、歩き出しざまに一口かじろうと思ってはたと気付いた。すぐに振り返って店主を見る。
「ねえ、ケチャップがなくてよ。」
男は首を横に振った。無い、そういうことらしい。
「ケチャップがなくてはホットドッグでないわ。」
尚も男はかたかた首を振る。アンジェラが呆れてため息も出ないでいると、後ろから女性の声がした。
「ケチャップがないのがシカゴ流ですよ。」
アンジェラと同じくらいの年齢で、凛とした目の女性がそこに立っていた。彼女は首を傾げて肩をすくめ、店主に向かって「一つくださいな」と注文する。
「あなた、アンジェラ・エマソンではないですか。さっきあのホテルから出てくるのが見えまして。」
即座に素性を当てられたのでアンジェラは身構えた。すると女性は微笑む。
「怪しい者じゃありませんよ、あなたを尊敬してるんです。私、ジェーン・アダムズです、どうぞよろしく。気軽にジェニーとお呼びください。」
「ええと、ジェーン、囲み取材ならお断りよ。」
「滅相もない、アンジェラ、新聞であなたを知ってから一度お話ししたかったんですよ。」
「そう。話せてよかったわね。それじゃ。」
「ちょっと、待ってください!」
「ホットドッグが出来上がるまでそこで待っていなさい。」
彼女を出店の前に置き去りにしてアンジェラがホテルに戻ろうとすると、アダムズは彼女を追いかけた。
「アンジェラ、あなた方は全ての術士の女性の解放者ですよ!」
アンジェラは立ち止まり振り返ってじっとりとした目を向けた。
「世間はあなたのことを『術士の風上にも置けない』と言いますけど、あなたこそ誰よりも未来を見据えている。」
「……何者なのよ、あなた。」
「ジェーン・アダムズです!」
二人は湖岸の公園にくつろいだ。雑多な市街と湖面とのわずかな間に作られた緑地帯は憩いの場として大変愛されているようだ。アンジェラから向けられる警戒した視線を意に介さず、アダムズは自らの思いを語る。
「女性の一生は生まれながらに決められています。男性と違って教育も受けられないで社会にも参加できないで、すなわち良妻賢母になることが女性の生きる目的なんです。でもそれってなんて面白くないことなんでしょう。殊に術士の方々はもっと気の毒です。術士としての仕事に就く他の道はなく、その血統を守るために結婚相手も家庭が決める。彼女らは暗黒時代のような封建的な世界から未だ抜け出せていないんですよ。」
「同感ね。」
「ですがグレイヒル技士の技術は術士がいなくても機械を動かせるというじゃないですか。これによって救われるのは労働者だけじゃない、それよりもむしろ、術士の方々こそ救われるんですよ。工業機械の傍に縛りつけられることなく、もっと他の仕事ができるようになる。今は皆さんも仕事が奪われるんじゃないかと心配してますけど、いずれきっとこのことに気が付くでしょう。そうではないですか?」
「ジェーン、私はこの目であの人の発明品を見た。それは間違いなく時化を鎮めるものだった、そして同時に、あの機械が動いている時私は術が使えなくなったのよ。」
アダムズは凛とした目を一層輝かせた。
「やはり解放者ですよ!機械から離れた時、術士は『機械を動かすための機械』ではなくなるのです。」
奇遇だ。この人、私と同じことを言うのだなとアンジェラは思った。
「あなたはそれが分かっていたから家庭を飛び出して彼に協力したんですね。とっても勇敢なことですよ。」
「勇敢……ねえ。本当のところは幼い反抗心よ、父親へのね。」
気が付けば彼女はアダムズに先日の電話で話したことを打ち明けていた。今さっき出会ったばかりの相手に話すなんてどうかしている。実際は誰でもよかったのかもしれない。彼女がそれを真摯に聴いてくれたことは幸運だった。
「すると、アンジェラは御父上がたいそうお好きなんですねえ。」
両手を顎に触れて、アダムズはぼーっとして呟いた。
「あなた話を聞いていて?どうしてそんな結論になってよ。」
「私と同じですから。」
「はあ?」
アンジェラはため息をついて、やはり話すべきでなかったかと激しく後悔し始めていた。彼女はそんなことを一切意に介さない。
「実は私の父はあのリンカーン大統領の友人であるジョン・アダムズです。ご存じないですか?それならそれで構いませんが、とにかく名のある人です。幼い時に母を亡くし、父の下で暮らしてきました。末娘の私を父は可愛がってくれましたが、私はそれがどうにも居心地が悪かった。元々病弱で見てくれの悪い私は立派な彼の隣に立つべきじゃないと思っていたんです。そんな父が初めて私の前で涙を見せて憚らなかったことがあって、それは父がリンカーン大統領の訃報を受け取った時でした。その時初めて私は神の如きに見えていた父が一人の人間として感じられました。」
「――彼が娘の前で悲しみに暮れるほどの相手、リンカーン大統領とはどんな方なのだろうと人伝に彼の話を聞いているうちに、私は既に亡くなった大統領に対して憧れを抱いていきました。その時に気付いたんですね、それは私が父に向けているまなざしと同じなのだと。私は自らに感じた負い目から父を避けておりましたけど、本当は彼に憧れていました。今では彼のように隣人を愛し、人を助ける存在でありたいです。女だからってそれができないはずはない、一番大切なのは精神、でしょう。」
「あなたの方がよっぽど勇敢じゃない。私とは違くてよ。」
もう十分だ。アンジェラは部屋に戻ろうと思った。アダムズは彼女の顔を覗き込んだ。
「アンジェラは本当に御父上がお嫌いですか。絶縁を口にしたのは自分のせいで彼の名誉が傷つくことを恐れたからではないですか。」
「そんな悠長な話でないわ。」
「御父上のこと、手が届かないほど遠くの人だと思ってはいませんか。同じ場所に立っている人間だと見とめた時、初めて面と向き合うことができるんですよ。」
「もういいでしょう、放っておいてよ。」
「失礼しました」とアダムズは萎む。
アンジェラはその場を去るべく立ち上がった。
「やっぱりあなたに会えてよかったです。私、惚れっぽいところがあるから、あなたが私と同年代の、普通の女性だって分かっただけでも。」
答えずに歩き出す。
「しばらくどこか遠くの街に行くなんてどうですか。私、ヨーロッパを回ったことがあるんですよ。そのうちにまた行こうと思ってます。」
立ち止まって振り返って、横顔で微笑んだ。
「ジェニー、あなたの名前はいずれどこかで聞くことになるのでしょうね。そんな気がするの。」
シカゴは灰色の街だ。だが街に集まる人の活力がある限り、そこには凛とした花が咲く。
さらに一週間が経過して、ロバート・グレイヒルの大勝負を負け調子で報道する新聞が一層増えた。これにはいくつか理由があった。
彼は期間中全く報道陣の前に姿を現さなかったが、それは機械の設計を頼まれた工場の社員に対してもだった。ある日、設計担当の各社は衝撃の事実を明かした。ロバートからほとんど設計図を受け取っていないのだという。彼がこれまでに寄越した設計図は数点の部品に留まるのみで、装置全体を構成するには到底不足している。期限も迫っているのにこれでは完成させる気がないのだと批判的に報じられた。当人は完成した部品を鉄道の車両庫を一つ貸し切った中に運ばせて、ここ数日は一人でそこにお籠りである。工作機械の音は響いているが、完成には足りない僅かな部品で何をしているのか。その様子が中世の伝説に語られる、深い森の中に籠る黒魔導士のようで、定着しつつある彼の呼び名「『黒』技士」を更に印象付けるように報じられた。
加えて、欧州からは暗雲が立ち込めている。先日、列強の連合艦隊が大西洋上に集結しつつあり、合衆国に向かっているという情報が流れた。合衆国政府に圧力を加える目的は明白で、ある情報筋によればヴィエナ宣言違反を糾弾するための教会勢力と学術連盟が同船しているともされる。これが本当ならば大艦隊はロバートを異端審問にかけ、合衆国を屈服させるための「十字軍」だ。一部には今すぐ実証実験を中止すべきとの声も聞かれる。だが、艦隊がこちらに向かっていよう段階においても、政府は取引を反故にしなかった。
約束の期日は迫る。市民の間ではグレイヒルの実験が成功するか失敗するかの賭け事が盛んに行われていたが、最も有力な賭場では失敗の倍率が下がり、成功の倍率は上がり続けていた。
迎えた当日。車両基地に集まった記者、写真家、実験に協力した実業家、興味津々の技士、物好きな術士などが集う中に、その男は姿を現した。新聞の挿絵に描かれたのと同じ、土色の解れたジャケット、汚れたカーキ色のズボン、腕の固定具は取れて、血の色が抜けきらないゲートルに弾痕で抉れた帽子は頭の上、その下からは寝不足気味の青い目を見せて。
「皆さん、お待たせしました。」
ロックフェラー氏はロバートの前に立ちはだかった。
「調子がいいようだな、グレイヒル技士。自信があるのは大変結構。」
「お見せしますよ、僕の発明品の力を。」
「昨夜の内に設営を完了させたそうだな。稼働の準備は整っているのか。」
「ええ勿論。皆さんと一緒に現場へ向かいましょう。」
貨物鉄道には今日のために客車が用意され、その場に集まった者は押し込められて油井へ向かった。始終、ロバートは落ち着いていて、周りを警官に固められた中でも飄々と座って座席から動かなかった。
現場に到着した観衆が目にしたのは、油井の櫓の前に立った鉄塔。芯は国旗の掲揚台のように太く長く天を仰いで、その間に細い金属棒が縦横に組み合わされて伸び、まるでそれは鉄の樹であった。根元には電気設備を置いて、このために石油を燃やす小型の発電機を据え付けさせていた。発電機からは観衆席を取り囲むように並べた電球にも電力を供給していて、簡易な電柱に吊るされた照明は不規則な明滅を繰り返していて目に悪かった。
「ほう……お前、いつの間にこんなものを組み上げたのだ。」
「約束の期間中に。主要な組み立ては全部僕がやったので昨夜の設営係を除けばこれを目にするのはあなた方が初めてですよ。ちゃんとした電源が得られたので、試作品より大出力にできました。」
油井の現場監督が二人の下に駆け寄ってきた。
「現在の採掘量は向こうの油圧計で常に確認できます。今朝の稼働率は三割強でした。」
「ご苦労。不運だったなグレイヒル技士、今日は特に時化がひどいぞ。」
「ちょうどいい、時化るほどこれの効果がよく分かるというものでしょう。今から稼働前の最終確認をします。」
「準備ができたら観衆の前に立て。」
ロバートは電信機械の点検を行うように、装置の裏蓋を開けて中の配線の具合を確かめた。
三人にはこの場に来ないように言いつけておいた。これだけ人がいる中で見世物のように衆目を浴びて、心無い言葉をかけられるのが嫌だったからだ。何も心配することはないと言って、ホテルで祝いの席でも用意して待っていてほしいと伝えた。そんな彼を信じているから彼らも黙ってそれに従った。
確認を終えて、あとは電源さえ入れればよい。ロバートは立ち上がって即席に用意された演台に上がった。隣のロックフェラー氏が彼を指し示しながら声高に語る。
「諸君、ここにいる技士、ロバート・グレイヒルは前代未聞の研究を世に示した。その内容は社会に大きな不安を呼び起こし、世界中が震撼した。一方でそれは我々の工業を長らく悩ませ、多くの労働者の命を奪ってきた時化を克服し、多大な恩恵をもたらすものだとも言う。ここに合衆国政府と我ジョン・D・ロックフェラーをはじめとする慈善的な実業家らは一つの決断をしました。グレイヒルの研究の真価を見定めるのです。彼の精神の崇高さは実在の効用によって示されるべきであるという我々の信念のもとに。これより世紀の実験は開始されます。技士の技術が本物であるならば、諸君は我と共に今日ここで歴史の証人となるのです。」
「――それでは始めるとしよう。」
合図と共に、ロバートは主電源を入れる。
「稼働しました。」
装置に変化は何もない。するとまず最初に周囲の電灯に変化が見られた。不規則な明滅は終わり、一斉に明るく輝きだしたのだ。幾人もが感嘆の声を漏らした。
「感心するのはまだ早い。観察の対象は油井だからな。」
そう口にした途端、油圧計にも変化が現れた。低いところで左右していた油圧計の針が上昇を始めた。これにはロックフェラー氏も目を見開いた。
「なんと。産油量が増加している。」
ざわめく観衆。彼らが計器の針に夢中になっている間に、ロバートはポットとマグを持ってこさせていた。
「ロックフェラー氏、実験は十二時間もありますから、ひとまずゆっくりコーヒーでも飲みませんか。」
ポットから黒い液体を二つのマグに注いで、呑気にそれを勧める。
「少し熱くし過ぎたかな。ご親切な術士の方、これを冷ましていただけませんか。」
前列に並んだ来賓席の術士たちの前にマグを置く。「どうぞ」と示すと、一人の男性が手を差し出したがやがて急に慌てだす。異変に気付いた彼らは途端に驚いたり首を傾げたりする様子を見せ始めた。ロバートは微笑んでマグを取り上げ、一口飲んだ。
「まだ熱いですね。」
「お前、まさか……」
ロックフェラー氏が彼を向いた。
「術の基本原理は時化のそれと同じ。この機械の周りにいる皆さんは、自らの術が上手く使えなくなっていることにお気付きでしょう。」
観衆席に走る動揺。平然とマグを傾ける彼の姿を多くのカメラが捉えた。
「正直……予想以上だな、グレイヒル技士。」
「会長!大変です!」
作業員が演台の下に駆け寄って来る。
「向こうの本流の送油管が……!」
「どうした、時化か!?」
「詰まりそうなんです!あっちも、こっちも、ここら一帯の産油量が急激に増加して、根元の管の輸送量が限界なんです!」
ロックフェラー氏は髭の下の口をあんぐり開けて、顔を覆った。そのまま黙り込んでしまったので作業員も、観衆も不可思議に思って視線を集めた。
顔から手を外したその表情は笑っていた。どうしようもないくらい可笑しくて、笑いが止まらなかった。
「前言撤回だ、予想を『遥かに』超えている!グレイヒル、お前の技術は本物だ!」
ロバートは帽子を取って応えた。
「実験は十二時間、観察は続けるが……我の答えは決まったようなものだ。ここにいる記者共は号外を発行する用意をしろ。このように書くのだぞ――」
「――実験は大成功!我々は時化を克服した、とな!」
「――我は本実験の責任者として、技士ロバート・グレイヒルを認める。彼は成功者だ。これより先、この偉大な成功者に謂れなき誹謗を寄せる者、それが誰であれ、スタンダード・オイルのジョン・D・ロックフェラーを敵に回すことと思え。そしてそれは彼の盟友に対しても同じだ。讃えよ、開拓者の精神に満ち溢れた若き名技士を!」
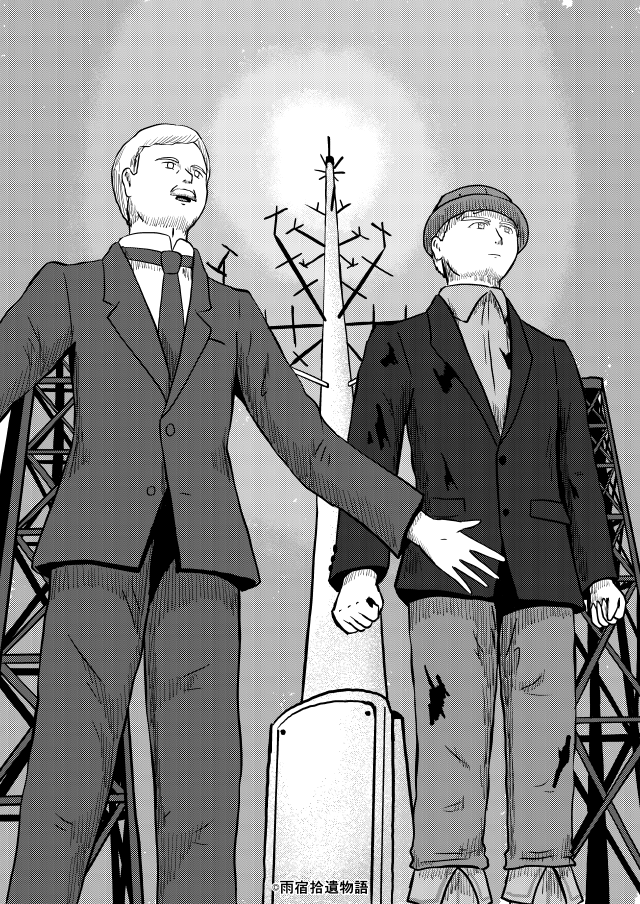
後日、実験場に居合わせた者は当時をこう語る。はじめに歓声を上げたのは周りにいた作業員たちだった。それは次第に伝播し、ついにはその場にいた全員が彼の名を歓喜と共に叫んでいて、熱狂が収まることはなかったと。
定められた計測期間である十二時間のあいだ、一度たりとも機械に時化が発生することはなかった。噂を聞きつけた人々は世紀の発明を一目見ようと、次々に列車を使って会場へ足を運んでは奇怪な塔に釘付けになった。始終世間を騒がせてきて、今度は名技士として名を馳せることになるロバートは記者団にもみくちゃにされ、連日の徹夜もあって目の焦点も合わない調子で、見かねたロックフェラー氏に囲み取材から引き剥がされてしばらく休むことにした。
計測終了の間際に再び起き出して会場に姿を見せた。観衆はほとんどいなくなっていた。日は暮れたが、電灯を用意したおかげで辺りは瓦斯灯の灯る市街地よりずっと明るい。同じく会場に舞い戻ったロックフェラー氏が正式に実験の終了を宣言し、ここにロバート・グレイヒルの研究に対する実証実験は彼の栄光に照らされて幕を閉じた。実験成功の報は電信で全国に伝わり、海底の電信線を伝って外国にも届けられる。
彼がシカゴの街に戻ったのは夜も更けてからだった。勇者の凱旋を市民は出迎え、彼は車から顔を出して受け応えてやった。ホテルの前に車をつけてから建物に入るまでが一番長い道のりで、サクラメントからここまで来るよりずっと厳しかった。
ガラス戸の内側に入った途端に外の喧騒から解放されて、待合室が静かなのが不自然にすら思えた。彼の耳の奥では歓声の残響が消えないでいる。
大理石の床と柱、ガラスのシャンデリア、金の装飾。順番に見回して、三週間もこんなところに泊まっていたのかと開いた口が塞がらない。本来なら自分には一切縁がないような場所だ。
「おかえりなさい。」
前方から耳馴染みの良い声がした。そこには彼の一番信頼している仲間が、並んで立って迎えていた。
「やったんだね、ロバート。」
「天晴であった。」
気が付けば、走り出していた。頭の帽子がずり落ちて、大理石に固い音を響かせる。ロバートはアンジェラを強く抱きしめた。
「みんな、助かってよかった……!」
もっと強く抱きしめる、もっと。
「本当はずっと不安だったんだ、うまくいかないんじゃないかって、僕がヘマして全部台無しにしてしまうんじゃないかって、そんな考えが頭の中から離れなかったんだ。」
涙を堪えなかった。情けないとかみっともないとか、そんな考えは少しも浮かんでこない。流れるまま流してやった。
「叔父さんや信じてくれた人たちを裏切ってしまわないかって。何より、僕はこんなところで終わりたくなかった――僕はもっと生きていたい。」
アンジェラは自らの顔の横にある琥珀色の髪の毛にそっと手を触れた。
「もう大丈夫。あなたは自分の意志と、私たちと、みんなとを守ったのよ。あなたは立派によくやったわ。だからもう大丈夫。」
「僕は、みんながいなければここまで辿り着けなかった。わがままを聞いてくれ――もう少し一緒にいてほしいんだ。」
三人とも黙って頷いた。彼がいなければこの道を進んでこられなかったのは、彼らも同じこと。
「さあ、技士さん、もう泣かなくてもよくってよ。明日からあなたはもっと人気者になるんだから、めそめそなんてしていられないわ。」
彼女が肩をぽんと叩くと、ロバートは腕を解いて向かい合った。目を合わせて頷いて、手のひらで頬を拭うと傍に落ちている帽子を被り直した。
「僕の旅はまだ終わっていない。進み続けるんだ、このレイルを。」
いくら一日にして時の人になったからといって、平凡な朝を迎えたいと願うのは誰だって当然のことだろう。ところがこの日ばかりはそうもさせてくれない。朝食にロオストチキンなぞが出るのだから、大変なことだ。大皿の周りにはワイルドライス、川魚の燻製に付け合わせの蒸し野菜とマッシュポテトがあって、おまけにメエプルシュガーをかけたシナモンロオルまでついてくると堪ったものではない。高級ホテルの料理はいつだって贅沢の限りを尽くされてきたが、こんな朝は初めてだった。
ロバートは大量の皿を前にしてあまり無理はしないようにと最初に忠告しておいた。四人は一階のホールで白いクロスの敷かれた円卓を囲み、他の宿泊客と同じようにして山盛りの食事に手をつけた。
ロバートはリニーの皿にシナモンロオルが残っていないのを見やった。
「それ、気に入ったか。僕の分もやるよ。」
「え、別にいい……。」
謙遜というより正直な答えだ。彼女はこれらを食べきれる気がしなかったので、満腹になってしまう前においしそうなものを先につまんだというわけだ。彼の食事の調子がいつもより遅いことに各人は気付いた。
「どうかしたの?」
「今日は取材の予定が詰まっていて、『戦略的』な判断だ。膨れた腹で苦しそうに答えるわけにもいかないだろう。」
「技士さんはお忙しくてね。」
「そうは言えどロバート、生きとし生ける者をいただいておるのだ、残すのは礼節を欠く行いなるぞ。」
「だけどなあ仕方ないだろう!……ああそうだ、みんなは今日の内に街へ行ってよそ行きの服を設えて来るんだ。今晩はここで祝賀会があるんだ。」
「あら、初めて耳にしたわ。」
「仕方ないさ、こうも注目されちゃ。歯が浮くような思いだけどね。」
彼は肩をすくめながらに言う。
「私、初めてだな……。」
「平気よ、この私が立ち振る舞いを教えてあげるから。ロビン、あなたもね。」
「僕の何が問題なんだ。」
「ほとんど全部。」
呆れてため息しか出てこない。
食事を始めて一時間も経った頃、ホテルの従業員がロバートに寄って彼を呼びつけた。
「お電話が入っております。」
彼はしめたと思った。もう少し残っているチキンを腹に押し込むのも限界に達していたので、ちょうどよく席を離れる口実ができてよかった。カトラリーを置いてナプキンで口を拭く。
「よし、僕は行ってくるから、もう少し楽しんでいてくれ。」
「某も参ろう。」
「なんだ、まだ料理が残っているじゃないか。礼節を欠く行為だぞ。」
「この世に合衆国陸軍大佐の電話より大事な食事はあるまい。」
ロバートは眉を顰めた。
結局全員が都合よく食事を抜け出し、電話のある部屋に移動した。術士が取り次いでいるところ、ロバートは息苦しそうに席に着いて受話器を取った。
「もし、ロバートですが。」
「吾輩だ。ロビン、久しゅう。よくやったようだな。」
声の主は叔父さんだった。彼の言葉が街で掛けられたどの賞賛よりも嬉しかった。
「ありがとう。叔父さん、どうしましたか。」
「まずはそれを伝えたかったのだ。無論用件は他にもあって、この先のお前の予定のことなのだが――まだ安心するのは早い。大統領にお渡しするから、暫し待て。」
受話器を握り直す。三人も電話の周囲に立って聞き耳を立てた。
「おはよう、ロバート君。まずは君に拍手を送ろう。君は君自身の精神が本物であることを証明してみせた。取り決め通り、合衆国政府は君を支援するよ。」
「ありがとうございます、大統領。」
電話の向こうで大統領はしきりに頷いた。
「それでは本題に入るがいいかね。君が当初サクラメントを飛び出した理由を覚えているね、君に協力を申し出る者がニューヨークにいると。」
「ええ。」
「その正体を政府は既に突き止めた。ロバート君、君の研究を匿うと持ち掛けたのは、合衆国の技士連盟だ。」
「ええ、何ですって?まさか、そんなはずは。」
「それが本当なのだ。」
リニーは隣に立つアンジェラに囁きかける。
「技士連盟って何。」
「さあ。」
稲熊も首を横に振る。頭の上に疑問符を浮かべている三人を見てロバートは大統領に断りを入れてから小声で説明した。
技士連盟はヴィエナ宣言後に組織された技士で作る国際的な連盟。それ以前、学問の世界では成果発表とその証明が個人の手に委ねられていたことで、研究の盗用や提唱者を巡る争いが絶えなかった。この紛争を解決するためにヴィエナ宣言を発した技士たちは研究を「整理」する組織を立ち上げた。技士が自らの研究を世に知らしめるには連盟に論文を提出する。それが承認されることで知見は世界に広められ、信憑性のある正当な研究として認められる。
「――つまり、技士連盟は正規の手順を辿る時に論文を提出するはずだった場所だ。僕は大学を出ていないから連盟の会員になる機会はなかったが、高等教育を受けずに技士の世界に入る人間はしばしばいるんだ。」
説明を終えると彼は送話器に顔を戻した。
「しかし大統領、連盟はヴィエナ宣言を掲げる云わば本丸、それなのに僕の研究を受け取るつもりでいたのですか。信じ難いことです。」
「組織としては宣言を是としている。だがそこにいる一人一人の人間は技士だ。才知に溢れた同志の若き芽が花開こうとしているのを摘んでしまうのは忍びないと考える者がいたって不思議ではないだろうね。まして、ここはアメリカだ。旧大陸の伝統に囚われるよりも新大陸の自然に鍛え上げられた新しい精神を尊ぶ。」
「……敵ばかりじゃなかったんだ。」
彼は思いが口を突いて出た。
「それでだロバート君、ロックフェラー氏と交わした契約を覚えているね。彼らに君の技術を無償で提供することになっていたね。」
「はい、その通りです。」
「技術提供のためにはまずその研究が君のものであることを技士連盟が承認し、ついでに合衆国の特許局が君の特許を認めることだ。であるから、契約の履行のためには君の論文を連盟に提出しなければならない。ところがここに問題があるんだ。近々列強の連合艦隊がニューヨークに到着することを知っているね。」
「ええと?」
ロバートは顔を上げた。三人が首を縦に振る。
「知らないのか。そうか君、仕事にかかりきりで世の中の情勢を知らないのだな。」
「……申し訳ながら。」
クリーヴランドは「仕方あるまいね」と優しく微笑んだ。
「艦隊に同船している勢力が明らかになった。国際技士連盟と、教会だよ。もし合衆国の技士連盟が君の研究を承認するようなら、彼らは連盟の委員を全て更迭して自分たちで成り代わるつもりらしい。そうなれば君の研究は決して認められない。そしてさらに問題なのが教会だ。中心組織が聖職者の術士で構成された教会は合衆国に君の身柄を差し出すことを要求している。それが何を意味するか分かるかね。」
「ロビンを宗教裁判にかけようっていうの!?それじゃあやってることが魔女狩りと同じじゃないの!」
「む、君は……」
「彼女はアンジェラ・エマソンです、大統領閣下。」
アンジェラはロバートの隣に座って送話器に声が届くように話した。
「そもそも暗黒時代に魔女狩りを主導したのは王宮や聖堂に巣食っている権力者の術士たちよ。森の中で慎ましく暮らしてきた彼らを追いたてて……あの頃から本質は何も変わっていなくてね。」
「アンジー、落ち着いて。大統領閣下、いかがなさるおつもりでしょうか。」
「決まっているさ、」クリーヴランドは言った。
「私は君と約束をした、そして君はそれに応えた。ならば私も同じようにするだけだ。例えニューヨークに砲門を向けられ、喉元にナイフを突き付けられたとしても、それに勝る価値を君は示した、違うかね。」
「しかしその代償は大きすぎます。」
「そうだな、それに技士連盟の委員更迭に関しては政府にはどうしようもない。」
「折角実験は成功したのに……」
リニーは肩を落とす。
「まだ、諦めてはいけないよ。」
「艦隊が君を奪いに来るならば、それより前に合衆国の技士連盟が研究を承認してしまえばよいだけのことだ。一度承認したものは取り消せない、着いた日には時すでに遅しと分かれば、いくら連合艦隊でも合衆国と戦端を開く理由はなくなる。海軍の後ろ盾がなくなった教会の要求など、撥ね退けるのは容易いよ。」
「左様でありますか。さすれば今すぐ承認を……」
「いや、待て。普通論文が承認されるには少なくとも二週間はかかるんだ。それじゃあ間に合いませんよ。」
「超法規的措置だよ。」
ロバートは受話器を握って聴こえてきたその言葉を繰り返した。
「どういうことですか。」
「昨日の実験によって技術は十分に証明されたものとして、連盟は研究を即日承認すると約束した。条件はこうだ、論文と実演に使った装置とをニューヨークの合衆国技士連盟本部に持ち込むこと。そうすれば君の研究は即座に正式な承認を得る。ロバート君、両方用意できるかね。」
「ええ勿論です、論文はここにありますし、実験に使った装置なら……」
彼の背後で扉が開く音がした。誰かが駆け込んできて、振り返るとそれはロックフェラー氏だった。
「電話中失礼、グレイヒル技士、問題発生だぞ。」
ロバートは電話口に事情を説明し、彼の話を聞くために席を立った。
「今朝方、実験現場で装置が破壊されているのを作業員が発見したそうだ。完璧に破壊されている、これは何者かの犯行だ。」
「本当に!?」
「間違いない。作業員が残骸の一部を持って我のもとに駆け込んできた。」
三人が一斉にロバートに顔を向ける。
「それじゃあニューヨークに装置を持って行けないじゃない!」
「これも敵の仕業か。三週間息を潜めておったかと思えば。」
ロバートは黙っていた。慌てるとか怒るとかせず、黙って立っていた。
「ロックフェラー氏、怪我人はありませんでしたか。」
「お前、そのようなことを言っている場合か。」
「大事なことですよ。怪我人はありませんでしたか。」
「む……そのような報告は聞いていない。」
「それは良かった。」
彼は微笑む。不安の色はなかった。
「安心してください、破壊されたのはただの鉄くずですよ。僕は同じような鉄塔をもう一つ作って、昨夜の内に実験場に建てた装置を偽物にすり替えておいたんですよ。本物は貸し切った車両庫の中にあります。」
「何だと。」
「敵が破壊工作に出るのは予想通りだ。八十四の工場に部品の分散発注をかけておいてよかった。」
「何と。各社に届いた設計図がやけに少なかったのはそのためか。」
「この振り分け作業が無ければもっと早く完成させられたんですがね。」
「まさかお前……設計を一社に任せず、組み立ても一人で行ったのは、担当した作業員が口封じに遭うのを防ぐためだったというのか。」
首を縦に振る。ロックフェラー氏は思わず頭を抱えた。
「発言を修正する。お前は単なる名技士ではない、英雄だ。」
帽子を取って一礼して、ロバートは再び電話に向かった。
「聴こえていらっしゃいましたか。」
「ああ。君は最高だ。」
「ニューヨークに向かいます。」
「ロビン、我々陸軍が護衛しよう。」
そんな折、今度は電話の向こうで誰かが駆け込んできた様子だった。大統領がいるという部屋の扉を激しく開けるなど、どんな人物かと彼は思った。
「クリーヴおじさん、大変ですわ。」
女性の声がした。それは大統領を「おじさん」と慕う世界で唯一の女性、フランシスである。電話の向こうで会話が繰り広げられる。
「あら将軍、ご機嫌麗しゅう。お電話中でしたのね、すみません。」
「フランク、そうやって廊下を走るものじゃないよ。まったく、おてんばなんだから。私たちは今ロバート君と話しているんだからね。」
「まあ、グレイヒル技士がお電話の向こうにいらっしゃいますの。ぜひともお声を拝聴させてくださいまし。」
「今は大事な話をしているんだからね。それでフランク、何があったんだね。」
「丁度よいですわ、お電話の向こうのグレイヒル技士にもお伝えくださいまし。この声明文ですの。」
クリーヴランドは彼女から紙を取り上げてそれを読んだ。電話口では暫し無言の時が流れる。リニーはロバートの横で受話器に耳を傾けた。
「どうしたのかな。」
「……あら、あなたがグレイヒル技士?とってもかわいい声をしていらっしゃいますのね。いいえ、素敵ですことよ。」
瞬時にアンジェラと稲熊は口元を覆って顔を背ける。彼は苦虫を嚙み潰したような顔をして話す。
「あの、僕が本物のロバート・グレイヒルですが。」
「まあわたくしったら。……ええと、本人もかわいい声でしてよ。」
それでとうとう堪えきれなくなって二人は噴き出した。
「こらフランク、電話で遊んじゃいけないよ。」
「ごめんなさい。」
「ロビン、この方は大統領閣下が後見人を務めていらっしゃる娘さんで、フランシス・フォルサム嬢だ。お前とお歳も近い女性だ。」
「ありがとうございます、将軍。私がフランシス・フォルサムですわ。グレイヒル技士、将軍共々応援させていただいております。」
「はあ、ありがとうございます。」
大統領は声明文を読み終えて、フランシスを脇にやって電話に向かった。
「これまた別な問題だな。」
「どうされましたか。」
「ルイジアナの複数の術士らによる共同声明だ。全文は電報で送るが、きっと新聞にも載っているだろうね。要約すると、『ロバート・グレイヒルの技術は社会不安を呼び起こすものであり、これを非難する』と、そういう話だそうだ。シヴィル・ウォーの再燃を恐れているのだね。」
「今でも僕を敵と呼ぶ人はいるのですね。僕は全国民に支持されたわけではない、少々舞い上がっていたかもしれないな。」
彼の後ろでロックフェラー氏が鼻で笑った。
「戯言を。今さら何を言おうと術士を取り巻く社会は大きく変わる、それはもう変えられないことだ。グレイヒル技士、成功者を妬むものは必ず現れる、いちいち気にしないことだ。」
「そうよ。私たちは変わらなければならなくてよ。古い術士は取り残されていくだけだわ。」
「エマソン嬢といったか、もっともなことを言う。大体いつまで二十年前に終わった戦いを引っ張り出してくるというのだ。お前たちは若く、当時のことなど覚えていないだろう。そこのインディアンの娘など生まれてもいなかったであろうな。」
リニーが頷いた。受話器を持たない手で帽子を深く被る。
「終わった戦い、か……そうではないかもしれません。そうですよね、叔父さん?」
朝顔型の送話器の真っ暗な穴の向こうに、叔父さんの顔を覗いた。彼はやがて短く答えた。
「ロビン、これは内政の問題だ。お前の気にするべきことではない。」
「その通りだよ、ロバート君。」
「大統領閣下、艦隊のニューヨーク着は何日後ですか。」
「四日後、早くて明朝。おそらくはその日のうちに。」
「ロバート、主は何を考えておるか。」
帽子のつばに手を掛け、送話器に声を吹き込む。
「ルイジアナに、行きます。」
シカゴとワシントン、離れた二つの部屋にいる人々が息を吞んだ。正気とは思えないその決断に。それでもワトキンスには見えていた、見えないはずの彼の青い瞳が、決意に満ちて輝いているのを。
「僕が直接行けば、彼らも納得してくれるかもしれない。彼らが納得すれば、この国で他に不満を持っている人々も認めてくれるかもしれない。」
「お前、本気で言っているのか。」
「ニューヨークには君自身が研究を持ち込まなければならないのは分かっているだろうね。」
「はい。ルイジアナを訪れて、それからニューヨークへ向かいます。明日の内に出発できれば間に合う。ロックフェラー氏、申し訳ありませんが今夜の祝賀会には出席できません。」
「それだったら先にニューヨークに行って、それから改めてルイジアナを目指せばよくってよ。」
「駄目なんだよアンジー。論文を承認させて、もう覆せない状態にしてから会いに行くなんて、彼らにしてみれば納得できるはずがないさ。」
「あなたが優しい人なのは分かってる、だから敢えて言わせてよ。あなたが説明しに行ったって、それは徒労に終わるかもしれない。言いたい者には言わせておけばよくてよ。誰が何と言おうと、私たちはあなたが立派なことを知ってるわ。」
「ありがとう。君の言葉は正しい、いつだって僕のために言ってくれるんだ。」
二人は目を合わせる。ロバートは弱く微笑んだ。
「だけど、リンカーン大統領だったらそうは考えないはずだ。」
「――二十年前、この国は災禍の炎に呑まれた。そのせいで叔父さんは『名将』の肩書と引き換えに本当は罪のない反乱軍の人々を打ち倒さねばならなかった。どうしてそんなことをしなきゃいけなかったんだ。今になって、それがまた繰り返されると噂されている。その原因は僕のせいか、この国に蔓延る『亡霊』か、歪みが膨れ上がった社会か――。真の原因はそうじゃない、人々の中にシヴィル・ウォーの後腐れが、災禍を恐れる心が存在しているからだ。時化は直せる、それを僕は証明した。今度は僕たちが証明するんだ、人の心は時化たりなんかしない。」
「お前、本物の英雄になるつもりか。」
「ご立派ですわ、グレイヒル技士。」

ロバートはもう一度電話に話しかける。
「大統領閣下、お教えください。声明を出した術士はどこにいますか。」
クリーヴランドは鼻から大きく息を吐いた。
「それでは、ニューオーリンズのデイビス先生を訪ねなさい。この声明の筆頭に名を連ねているから。彼なら話を聞いてくれるだろうね。」
「大統領、デイビスと言えばジェファーソン・デイビスでありますか。反乱軍の指導者の一人で、いつぞやに恩赦がなされたという。」
「叔父さん、僕はニューオーリンズに行きます。」
「しかしロビン、お前は吾輩の甥だ。二十年前のことを思えば、彼らはまだ吾輩を恨んでいるだろう。」
「過去の蟠りを乗り越えられぬのなら、端からこの戦いを終わらせることはできませんから。」
「そうだな。……大統領、ご決断を。」
フランシスが彼の大きな肩に触れる。クリーヴランドはそれに自らの手を重ね、それから送話器に手を掛けた。
「大統領令を出そう。本作戦の司令はグレイヒル大佐に任せる。」
「御意。」
「ありがとうございます。」
ロバートは振り返りつつ立ち上がって、ロックフェラー氏に手を差し出した。
「出発の準備に力を貸していただけますか。」
「……いいだろう。これは投資だ。いずれ全国民がお前に抱えきれぬ恩を受けることになるのだからな。」
アンジェラ、稲熊、リニー。ロバートは三人と顔を合わせた。
「みんなは……」
「よもや主、某を置いて行くつもりではあるまいな。」
「私も行くよ。あなたが許してくれなくたって、座席の下にこっそり忍び込むから。」
「参ったなあ。アンジー……」
「誰のおかげでここまで来られたと思っていてよ。」
「君のおかげだよ。」
「そう。じゃあもう少し付き合ってあげるわ。」
腕を組んでアンジェラは頷く。それからにっこり笑って、四人は互いに目を合わせて笑った。
「さあ、忙しくなるぞ。」
各人は準備を進めるため、電話室を離れようとした。電話を切る直前にリニーはロバートを呼び止めた。
「ちょっとその電話、貸してくれない?」
「何か話すことが?」
「うん。」
「じゃあ僕たちは先に戻っていてもいいか。」
「うん。」
一人残る彼女に受話器を託して、一行はそれぞれの仕事に向かった。
その日、大統領は一つの演説を行なった。決して長くないその演説はシカゴ発の大移動作戦を前に国民の理解を得るためのもので、長らくロバートを追い詰めてきた敵の組織に関する情報を全国民に公開した上で、団結を求めるものだった。
本日、我々は、正義と真実を愛する国民の皆さんにある一つの事実をお伝えせねばなりません。それは我らの偉大な大統領、リンカーン氏が遺した「課題」ともいえるものについてです。
今から二十四年前、私たちを引き裂く悲惨な内乱がこの国を襲いました。リンカーン大統領は傑出した指導力によって勇敢な将兵を率い、このシヴィル・ウォーを終結に導きました。ですが、それで全ての危機が去ったわけではなかったのです。これまで語られてこなかったことですが、かの戦いでは国民の不安を利用し、反乱軍を扇動し、合衆国に仇なさんと欲する邪悪な組織が暗躍していたのです。彼らは巧妙に姿を隠し、偉大な大統領さえもその全てを打ち倒すことは叶いませんでした。追跡を逃れた影なる組織はこの二十年間合衆国の内側に巣食い、密かに再起の時を窺ってきました。これは「シヴィル・ウォーの亡霊」です。
そして亡霊は今再び動き始めました。私たちの名技士、ロバート・グレイヒルの命を狙って。彼が崇高な精神によって拓いた技術によって合衆国が前に進むことを拒もうとしているのです。我々はいかなる時も嘘と不正を憎まねばなりません。卑劣な手段で仇なす魔の手から私たち自身がこの国を守らねばなりません。かつて私たちの先祖が独立を勝ち取り、侵略者と戦ってきたのと同じように。
亡霊は巧みに姿を隠し、私たちがその正体を見破るのは容易な事ではありません。しかしもうこれ以上隣人を疑い、友人を憎む必要もありません。私たちが恐怖を抱くことこそが亡霊の思う壺であるから。
星条旗を掲げましょう。太い条と輝く星の旗がたなびく下に集いましょう。私たちが同じ旗を掲げて団結すれば、亡霊は決して私たちを、祖国を脅かすことはできません。
私たちの名技士はこれから最後の旅に出ます。全ての敵からこの国を守るために。彼と同じ意志を持つあなた方は、星条旗を掲げましょう。それだけで私たちは団結できます、繋がることができます、打ち勝つことができます。
あなた方の大統領 グロヴァー・クリーヴランド
実験の成功で合衆国政府が態度を決定したことは全世界に報じられ、翌日には各国の反応が届いていた。失望、非難、それは同時に連合艦隊の作戦が続行されることも示している。だが一国だけは違っていた。太平洋の向こう、極東の島国――日本政府は「グレイヒル技士の成果を讃え、米国の決断を支持するものである」と声明を出した。これは世界に大きな衝撃を与え、孤立無援だった合衆国に勇気を与えた。
一昼夜を経て午後、ロバートはホテルの部屋で姿見の前に立って自らの外見を確かめる。手には使い慣れた拳銃を持って、引き金にかけた人差し指でくるくると回す。それからもう一度持ち直して、大切にホルスターに挿した。脇に置いた書類鞄を拾い上げ、最後にベッドの上にのせてあった探検帽を左手に取った。
一度は僕の命を救ってくれた帽子だ、それを思えば安い買い物だった。もっとも、あの時はこんなことになるなんて思いもよらなかったけれど。――もう少しよろしくな、相棒。ロバートは相棒を頭に乗せて廊下に出た。
部屋の前でリニーが彼を待っていた。変わらぬ服装のようで、ポンチョが胸のところで開いてケエプのようになっている。これはブースとの戦闘で縦に斬られたのを、アンジェラの機転で首元に紐を通して結べるようにしたのだ。彼女はこれを気に入っていた。
もう一つ、彼女には違っているところがあった。
「花飾り、つけていないのか。」
リニーは耳の上のお下げ髪に手を触れた。
「包帯してる間はつけてなかったから、習慣がなくなって。片方失くしちゃったし、もういいかなって。それに私、女の子らしくないからね。」
「女の人は負けん気が強いくらいがちょうどよくってよ。」
扉が開いて、アンジェラが話に混ざった。ライフルが入った臙脂色のケエスは長旅で擦れているが、まだまだ健在だ。後ろでまとめ上げたブロンドの髪に帽子を被り、左手にはグローブをはめているが引き金と装填レバーを操作する右手の方は素手のままでいる。
「それは自分のことを言ってるのか?」
「何か問題?」
彼はわざと不貞腐れたような顔をした。リニーはふふと笑う。
「ロバートはだらしがないから少し厳しい女の人の方がいいよ。」
二人は思わず「それどういうこと」と口にして、それが同時に出てしまったものだから変に気まずくなって黙り込んだ。それでリニーはまた笑顔になった。
「む、某が最後か。これは失敬。」
稲熊が三人の前に立った。ブースとの一戦で顎に傷跡がある。軍帽にも切り欠きが入ったが、大切な官給品だというのでそのまま着用していた。
「構わないよ。」
「刀磨きは終わってかしら。」
「完璧だ。渡米した技士に元刀鍛冶の男が居ってな、某の刀を砥ぎ直しいただいた。刀に触れるのが久しかったのであろう、喜んで砥いでおった。よく斬れるぞ。」
稲熊は脇に携えた刀の柄をぽんと触る。
「では車両基地に行こう。」
慣れない高級ホテルだったが、離れるとなると名残惜しく感じられるものだった。
四人は鉄道会社の車両基地で陸軍と合流することになっていた。馬車で進む道中、建物の窓で星条旗がはためいているのを見た。あちらこちらの窓から、一階の店舗でも、急ごしらえで用意したであろうものまで、おしなべて建物の間を抜けていく風に吹かれていた。皆彼らを祝福している証である。
車両基地に着いて車を降りると、転車台の近くの資材置場で陸軍の部隊が整列しているのを見た。首にスカーフを巻いた士官はこちらに気が付くと駆け寄って敬礼した。ロバートは士官学校時代に染みついた癖が返礼をさせる。
「グレイヒル技士ですね。私はシカゴ基地のウヱイン大尉だ。我が中隊がニューヨークまで同乗して護衛する。」
壮年の士官はそう名乗った。
「よろしく。」
「作戦を説明する、どうぞこちらへ。」
案内されたのは資材置場に設営されたテント。大尉と下士官はテントに入る。中央の机に鉄道路線の記されたアメリカ東部の地図を広げてあった。傍のラムプで照らしながら大尉は地図をなぞった。
「我々はこの路線を使用する。シカゴから南へ、ミシシッピ川とオハイオ川の合流地点にある鉄橋を渡ってケンタッキー州に入り、メンフィス、ジャクソンを経由してニューオーリンズに到着するのは明日午後の予定だ。事前に決定された給水地点では警備が行われており、原則途中駅で停車はしない。我々の列車が通る間は該当区間を閉塞するため、行き違いの列車もない。ニューヨークへの道のりはこっち、ニューオーリンズを出てモントゴメリ、アトランタ、シャーロット、リッチモンド、ワシントンを経由する。ワシントン駅では大統領による激励があるため、一度停車する。それ以外では丸一日以上かかる長距離移動だが、機関車の補給の他には停車は一切しない。作戦では沿線各州に駐屯する部隊が路線の警戒を行っている。なお、作戦本部はワシントン駅、総指揮官はワトキンス・グレイヒル大佐です。」
「――道中では『亡霊』による襲撃、妨害工作が予想されるのでご注意ください。また、線路に併設した鉄道電信は敵術士によるサボタアジュが予想されるので、その場合不測の事態への対応は列車内での決断を最優先とするように定められている。従って決定権は中隊長の私と、グレイヒル技士、あなたにある。」
ロバートは顔を上げて大尉を見た。
「僕が決めるのか。」
「第一にあなたが本作戦の最重要人物ですから。正確にはあなたの判断をもとに私の権限で決定する。私が再起不能に陥った場合はここにいる下士官か、その場で最も階級の高い者があなたに従うでしょう。」
「分かった。」
「正直なところ、亡霊がどこまで合衆国の内部に蔓延っているか我々にも想像がつかない。こちらの手の内は敵に知られているという前提で動くことです。」
「失礼してもよろしいか。」
テントの外から声がした。ロックフェラー氏だ。ロバートは「今伺います」と答えて外に出た。彼はそこに立っていた。
「この作戦に必要なものは全て取り揃えた。このジョン・D・ロックフェラーが必要な交渉は全て済ませた。」
「ありがとうございました。」
「協力する民間事業者の選定には苦労したぞ。」
「無理もないことです。敵の姿は闇に包まれ、普通なら無謀としか思えないから。」
「逆だ。誰も彼も諸手を上げるので適任の選定に手間取ったのだ。」
思わず目を丸くした。
「何を驚くか。英雄に手を貸すのは当然のことだ。……まあ半分は、将来を見越してお前に恩を売っておきたいのだろうがな。」
「嬉しいですよ、僕に協力してくれるなんて。」
「お前、街の星条旗を見てきただろう。あれらは全てお前のために掲げられているのだ。――誰もが無事を祈っている。」
「はい。」
大尉は下士官を中隊の移動に行かせた。
「グレイヒル技士、列車に向かいましょう。」
「ああそうだ、列車はどこにあるんだ。」
「ロバート」と稲熊が声をかける。その表情はどこか得意気だ。
「某が案内せん。」
彼の様子に三人は首を傾げた。
一行は車両基地の中を歩く。並んだ線路にはバラ積み用や石油用など多種多様な貨物車両が停められている。途切れ途切れに並ぶ車両は迷路のようで、その中を抜けていった。
「我が国の政府が主を支持する声明を出したのは知っておろう。」
「ああ。君のおかげなんだろう。」
「左様。彼らも真に価値あるものは何か察してのことぞ。そこでロバート、両国の友好の証として主に贈り物を用意した。」
「一国の政府から贈り物なんて、大したものね。」
「某が導いたが故、某からの贈り物といってもよいかしらん。」
「ああ、そりゃ嬉しいな。」
「ちょっと稲熊、買い被り過ぎじゃない。」
アンジェラは目を鋭くして言った。
「これアンジェラ、妬くな。」
「妬いてない!」
やがて、一つの車両庫の前に来た。扉の前では背広の日本人が三人いて、彼らを待ち受けていた。
「此方は我が国の技士である。」
「初めまして、グレイヒル技士。お会いできて光栄です。私たちは日本政府の使者としてこちらに参りました。」
技士の一人が声をかける。ロバートは「やあどうも。」と握手を交わした。」
「両国関係のさらなる発展を願って、此度は日本政府があなた方のために機関車を貸与することを決定しました。」
彼は稲熊の顔を見た。彼の笑顔に、ロバートは事情を理解して表情が明るくなる。
「この機関車は日本の鉄道を広く世界に知らしめるために貴国の鉄道会社に特別に開発を依頼していたものです。最新の技術を取り入れ、客車を牽引して巡行時速六十マイルは堅い。」
「六十!。なんてこった、これならあっという間だ。」
技士たちも満足そうに頷く。
「さあロバート、此方ぞ。この中に列車がある。」
合図で二人の兵士によって車両庫の正面扉が開かれる。午後の太陽が細く差し込み、扉が開くにつれそれが幅の広い光の線に変わって倉庫の中を照らしていく。
「時にロバート、日本という国の名の由来を知っておるや否や。」
「いいや。」
「日の本、日出ずる処という意味ぞ。だがこの大陸で言うなら、日出ずる処は某らが向かう先、ニューヨークであるな。」
「ああ……それがどうかしたか。」
代わりに技士の一人が答えた。
「開発段階でこの機関車につけられた名前があります。それは――」